赤ちゃんの成長は、本当に一人ひとり違います。
わかってはいても、「うちの子、まだハイハイしないけど大丈夫?」「あの子はもうつかまり立ちしてるのに…」なんて、周りの子と比べて心配になってしまうこと、ありますよね。
初めての育児ならなおさら、何が“普通”なのか分からず、不安になる瞬間も多いはず。
成長のサインである「ハイハイ」や「つかまり立ち」は特に、時期が気になるポイントのひとつ。
でも、実はこれらの動きにはとても大きな“個人差”があるんです。
この記事では、ハイハイやつかまり立ちが始まる目安の月齢、よくある発達のパターン、そして「ちょっと遅いかも?」と感じたときの考え方や対応まで、幅広くご紹介します。
実際のママ・パパたちの体験談も交えながら、「成長にはいろんなカタチがある」という安心を届けられる内容を目指しました。
不安になりがちな時期だからこそ、ひと息つきながら読み進めてみてくださいね。
きっと「うちの子なりのペースで大丈夫」と思えるヒントが見つかるはずです。
【総額7,660円OFFクーポン】【特典付き】
初回限定キャンペーンでお得にGETできる!
(画像引用:モグモ公式サイト)
「子どもが小さいうちは、仕事も家事も育児も全部フル回転。気づけば自分の時間はゼロ…」
「健康的なご飯を準備してあげたいけど、うまく時間を作れない…」
そんなママの一番の悩みは“毎日のごはん作り”ではないでしょうか。そんな時におすすめなのが『モグモ』です。
モグモは1歳半〜6歳向けの幼児食宅配サービスで、無添加で栄養バランスに優れた冷凍ごはんが届くため、冷凍庫にストックしておけばいつでも使えるので安心です。
- 保育園帰りで子どもが「お腹すいた!」と言っても、レンジで数分チンするだけ
- 献立に悩む時間がなくなる
- 子どもが食べやすい味付け・サイズだから、食べムラが減る
「今日は疲れてごはんを作りたくない…」「子供にも栄養バランスが整った食事を摂らせたい」そんなときに助けてくれるんです。
家族の食卓を無理なく支えながら、ママに“心のゆとり”を取り戻してくれるはずです。今なら全額返金保証付きで安心して試せるので、気軽に始めてみてくださいね!
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ![]()
ハイハイは何ヶ月からする?早い子の特徴は?
赤ちゃんの成長の中で、「ハイハイ」は初めての自立的な移動手段。
親としても「そろそろかな?」「まだしないけど大丈夫?」と、気になりやすい時期のひとつです。
ハイハイの開始時期や、早く始める子の特徴について詳しく見ていきましょう。
平均的なハイハイの時期は?
一般的に、赤ちゃんがハイハイを始めるのは生後7〜10ヶ月ごろが目安とされています。
ただし、これはあくまで“平均”の話。
中には6ヶ月で始める子もいれば、10ヶ月を過ぎてから始める子もいて、個人差がとても大きい発達段階のひとつです。
実際には、うつ伏せの姿勢でしっかりと頭を持ち上げられるようになったり、手や足に力がついてきた時期に、自然と前進や後退を試みるようになります。
最初は「ズリバイ」や「お尻を引きずる移動」など、いろいろなスタイルが見られ、いきなりきれいなハイハイになるわけではありません。
ハイハイが早い子の特徴
「うちの子、もうハイハイ始めたの?」と驚くくらい、早い段階で動き始める赤ちゃんもいます。
そんな“早い子”にはいくつか共通した特徴があります。
-
筋力と体幹の発達が早い
首すわりや寝返り、うつ伏せ遊びなどを早くから好む赤ちゃんは、筋力やバランス感覚が育ちやすく、ハイハイにも早く移行しやすい傾向があります。
-
好奇心が旺盛
じっとしているより「触りたい」「近づきたい」という欲求が強い赤ちゃんは、自分で動こうとする気持ちが強く、それがハイハイにつながります。
-
寝返りやズリバイの段階をたくさん経験している
動くことが好きな子は、寝返りやズリバイの期間も活発で、自然と次のステップであるハイハイに進む準備が整っていることが多いです。
-
周囲の刺激が豊か
兄姉がいる家庭や、大人とたくさん関わる環境では、動きたいという刺激が増え、ハイハイが早まることもあります。
一方で、ハイハイをなかなか始めないと「うちの子、大丈夫かな…」と不安になることもありますよね。
でも、赤ちゃんの発達には大きな個人差があるため、10ヶ月頃までは様子を見るのが一般的です。
特に注意が必要なのは、「寝返りもせず、ズリバイも全くしない」「足や手の動きが左右で極端に違う」などのケース。
こうした場合は、念のため小児科や保健師さんに相談してみるのも安心材料になります。
近年では、ハイハイの時期をほとんど飛ばして、つかまり立ちや伝い歩きに移行する赤ちゃんも珍しくありません。
「ハイハイをしないと発達に影響があるのでは?」と心配されることもありますが、他の発達に遅れが見られなければ、それ自体が問題になることは少ないとされています。
ただ、ハイハイは肩・腕・腰・脚など、全身の筋力バランスやバランス感覚を育てる大切な動きでもあります。
無理にさせる必要はありませんが、うつ伏せ遊びや床で過ごす時間を多めにすることで、自然と興味を持ちやすくなりますよ。
「できればハイハイしてほしい」と感じるママ・パパには、赤ちゃんが自由に動ける環境づくりがおすすめです。
-
安全なプレイマットや畳の上で自由に過ごせるスペースをつくる
-
赤ちゃんの目の前にお気に入りのおもちゃを置いてみる
-
親が床に一緒に寝転んで「こっちおいで〜!」と声をかける
こうした“ちょっとした誘い”が、赤ちゃんのやる気スイッチを押してくれることもあります。
「早い」「遅い」ではなく、その子のペースで育っているということを大切に見守っていけたら安心ですね。
次は、つかまり立ちについても見ていきましょう!
発達障害のハイハイの仕方の特徴はある?ハイハイが早い?
赤ちゃんのハイハイは、成長を見守るうえで大切なひとつのサイン。
でも、ふとした瞬間に「このハイハイの仕方、普通かな?」「発達障害と関係があるの?」と心配になることもあるかもしれません。
ここでは、ハイハイと発達障害との関係について、特徴的な動きや、ハイハイの早さとの関連について詳しく解説していきます。
まず前提として知っておきたいのは、ハイハイの仕方だけで発達障害を判断することはできないということです。
発達障害(自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)など)は、主に「社会性」「コミュニケーション能力」「行動面」に特徴が現れます。
そのため、乳児期の段階では、運動面だけを見ても判断は非常に難しいのが現実です。
とはいえ、過去の研究や臨床経験から、発達に個性がある赤ちゃんの中には、ハイハイの仕方や発達パターンに「少し違いがある」と感じられる場合もあることが知られています。
発達障害の可能性がある場合に見られるハイハイの特徴
以下は、発達に特性がある子どもに時々見られると言われるハイハイの特徴です。
ただし、これらがあったからといって、必ずしも発達障害を意味するわけではありません。
-
左右どちらか一方に体重を極端にかける(左右差が大きい)
→ 手足の動かし方にアンバランスが見られることがある。
-
片手片足だけを使うような移動(スパイダー・ハイハイ)
→ 両手両足をバランスよく使わない場合がある。
-
全くハイハイをせず、立ち上がろうとする
→ 移動を飛ばしてつかまり立ちや歩行に進むケースも。
-
ハイハイ中の姿勢が不自然(背中が丸まりすぎる・反りすぎる)
→ 体幹のバランスや筋肉の使い方に特徴が現れる場合がある。
-
極端に短期間でハイハイを終える
→ ハイハイにほとんど興味を示さず、すぐ別の動作に移ることがある。
ただし、これらはあくまで参考情報です。成長中の赤ちゃんは誰でも多少なりともアンバランスな動きをするもの。
1つや2つ当てはまっただけで心配しすぎないことが大切です。
ハイハイが早い子は発達障害と関係ある?
「ハイハイが早いと発達障害かも?」と心配されることもありますが、ハイハイが早いこと自体は発達障害とは基本的に関係ありません。
むしろ、筋力や好奇心が旺盛な赤ちゃんほど、早く動き出す傾向があります。
発達障害がある場合も早めに動き始める子はいますが、それだけで診断がつくわけではありません。
一方で、発達障害のひとつである自閉スペクトラム症(ASD)の子どもに、「運動発達が早い」「特定の運動スキルに秀でている」特徴がみられることもあるため、極端に早すぎたり、運動面と対人面の発達に大きなギャップがある場合は、将来の成長を見守っていく一つのポイントにはなります。
以下のような点が気になる場合は、かかりつけ医や自治体の乳児健診、保健師さんに相談してみると安心です。
-
何か月も片方の手足だけしか使わない
-
ハイハイ時の左右差がとても大きい
-
ハイハイ以外にも、目が合わない、呼びかけに反応しないなどがある
-
運動面だけでなく、言葉や人との関わりにも気になる点がある
特に、発達障害は「乳児期に必ず気づける」ものではないため、1歳半検診や3歳児検診などの節目で専門家と一緒に見守っていくことが推奨されています。
育児をしていると、どうしても「大丈夫かな?」「他の子と違うかも」と不安になる瞬間があります。
でも、赤ちゃんはひとりひとり違ったスピードで成長していくもの。
ハイハイの仕方に少し個性があっても、「その子の個性」として受け止め、たっぷり愛情を注ぎながら、無理なく見守ることが何より大切です。
気になることがあれば、ひとりで抱え込まず、早めに相談できる環境を整えておきましょう。
ずりばいは何ヶ月からするのが目安?ズリバイからハイハイにならない場合は?
赤ちゃんの成長はとても個性的。
寝返りができるようになったと思ったら、次にやってくるのが「ずりばい」です。
腕や足を使って少しずつ前に進む姿はとても愛らしく、初めて見た時には感動するママ・パパも多いのではないでしょうか。
では、この「ずりばい」はいつ頃から始まるのが目安なのでしょうか?
また、ずりばいからハイハイに進まない赤ちゃんもいると聞きますが、それは大丈夫なのでしょうか?
今回は、そんな「ずりばい」について詳しく解説していきます。
ずりばいの目安は生後6〜9ヶ月ごろ
一般的に、赤ちゃんがずりばいを始めるのは生後6〜9ヶ月ごろとされています。
早い子では5ヶ月ごろから、お腹をつけたまま前に進むような動きを見せることもあります。
ずりばいの始まりには、次のようなサインが見られます:
-
うつ伏せで頭と胸をしっかり持ち上げられるようになる
-
腕や足をバタバタ動かしながら、前に進もうとする
-
おもちゃに向かって体をずらしながら近づく
-
体をひねって左右に動こうとする
これらは「動きたい」という気持ちの現れであり、全身の筋肉が少しずつ育っている証拠でもあります。
ずりばいができるようになると、赤ちゃんは視野が一気に広がり、好奇心がさらに旺盛になっていきます。
実は、ずりばいをまったくしない赤ちゃんも少なくありません。
中には寝返りのあと、すぐにつかまり立ちやハイハイに進む子もいます。
ずりばいをしない理由にはさまざまあります:
-
体のつくりや筋力バランスの個人差
-
仰向けや座った姿勢が好きでうつ伏せを好まない
-
手足の力がバラバラに発達していて前進しにくい
-
ズリバイの必要がない環境(欲しいものが手元にある等)
そのため、「ずりばいをしなかった=発達に問題がある」というわけではありません。
ずりばいを経ずにいきなりつかまり立ちや歩行を始めたという子も多くいます。
ズリバイからハイハイにならない?それって大丈夫?
多くの赤ちゃんは、ずりばいの後にハイハイに移行しますが、ずりばいからハイハイを飛ばしてつかまり立ちや歩行に進む赤ちゃんもいます。
これは心配しなくて大丈夫なことがほとんどです。
ずりばいが長く続く子もいれば、数日で終わってしまう子もいます。
また、ハイハイをする時期も個人差があり、早い子で6ヶ月、遅い子では10ヶ月以降になることも。
ただし、以下のような場合は、一度専門家に相談してみてもよいでしょう
-
ハイハイやつかまり立ちがまったくできないまま1歳を過ぎる
-
手足を左右対称に使わず、動き方に極端な偏りがある
-
床にうつ伏せで置かれても、ほとんど動こうとしない
-
首すわりや寝返りも遅れていた場合
こういった場合は、筋力やバランスの発達に偏りがある可能性もあるため、小児科や保健師さんに相談することで安心できます。
ハイハイに進まない場合も、焦る必要はありませんが、赤ちゃんの運動意欲を引き出すための環境づくりはとても大切です。
-
広いスペースを用意する:ベビーベッドの中よりも、広いプレイマットや畳などで自由に動ける環境が理想的です。
-
うつ伏せ時間(Tummy Time)を増やす:日中、遊びとしてうつ伏せの時間を少しずつ増やしてあげることで、背中や首、腕の筋肉が鍛えられます。
-
興味を引くおもちゃを距離を置いて置く:赤ちゃんの「取りに行きたい!」という気持ちを育てる工夫もポイントです。
-
親が一緒に寝転んで遊ぶ:赤ちゃんと目線を合わせて遊ぶことで、安心しながら挑戦する気持ちが高まります。
赤ちゃんのやる気を引き出す関わり方や遊び方は、運動のステップアップにもつながっていきます。
ずりばいが長い子もいれば、すぐにハイハイやつかまり立ちに進む子もいます。
発達の過程は“一本道”ではなく、それぞれの赤ちゃんが自分のペースで進んでいくもの。
大人ができるのは、動きたくなる環境を用意してあげることと、たくさんの「できたね!」を届けること。
ずりばいをしないことやハイハイに移行しないことに過度に不安を感じる必要はありません。
心配なことがあったら、いつでも専門家に相談できる体制も整っているので、安心しながら見守っていきましょう。
10ヶ月でハイハイがしないのは障害がある?
赤ちゃんの成長を見守るなかで、「あれ?もう10ヶ月なのに、まだハイハイをしない…」と心配になる方は少なくありません。
特に周りの赤ちゃんが活発に動いている姿を見ると、「うちの子だけ遅れてる?」「もしかして何か障害があるのでは…」と不安になってしまうことも。
10ヶ月でハイハイをしない場合に考えられる原因や、発達障害との関連性、様子を見るポイントについて詳しく解説します。
まず知っておきたいのは、赤ちゃんの発達にはとても大きな個人差があるということです。
ハイハイを始める時期は一般的に生後7〜10ヶ月頃が目安とされていますが、これはあくまで「平均値」。
6ヶ月で始める子もいれば、11ヶ月や12ヶ月ごろにようやく始める子もいます。
また、必ずしもすべての赤ちゃんが「ハイハイ」というスタイルを通るわけではありません。
以下のようなケースも多く見られます
-
ズリバイだけで移動して、ハイハイを飛ばす子
-
お尻をつけたまま進む“お尻歩き”のスタイル
-
ハイハイを経ずに、つかまり立ち→伝い歩きに移行する子
つまり、10ヶ月でハイハイをしていないからといって、すぐに「発達に問題がある」と結びつける必要はありません。
それでもやっぱり、「発達障害と関係があるのでは?」と気になることもあると思います。
結論から言えば、ハイハイをしていないだけでは、発達障害の判断材料にはなりません。
発達障害は、主に以下のような分野に特徴が現れます
-
社会性や人との関わり方(例:目が合いにくい、呼びかけに反応しない)
-
言葉やコミュニケーションの発達
-
特定の動きや行動に偏りがある(極端に同じ動きを繰り返す など)
これらは通常、1歳半〜3歳以降に明確になってくることが多く、乳児期の段階で障害の有無をはっきりと判断するのは非常に難しいのです。
ただし、以下のような点が複数当てはまる場合には、専門家に相談してみるとよいでしょう
-
寝返りやおすわりも遅れ気味だった
-
足や腕の動きに左右差が大きい
-
体を動かしたがらず、うつ伏せを嫌がる
-
表情が乏しく、人とのやりとりに反応が少ない
-
呼びかけに振り向かない・目が合わない
これらの様子がある場合は、単なる発達の個人差ではなく、運動機能や神経の発達に関連する要因がある可能性もあります。
「様子を見ても大丈夫」と思いたくても、不安が消えないこともありますよね。そんな時は、遠慮せずに専門機関に相談してみましょう。以下のようなタイミングが相談の目安です
-
1歳になってもハイハイも伝い歩きも見られない
-
左右どちらかの手足ばかり使っている
-
全身の筋肉がフニャフニャと頼りない感じがある
-
首すわりやおすわりの時期も大きくずれていた
市区町村で実施される10ヶ月健診や1歳健診でも、こうした運動発達の確認がされます。
少しでも気になることがあれば、保健師さんや小児科医に気軽に相談してみましょう。
早期に気づくことで、必要な支援やリハビリなどを適切な時期に受けられる場合もあります。
10ヶ月でハイハイをしていない場合でも、遊びの中で自然にやる気を引き出すことができるかもしれません。以下のような方法を取り入れてみましょう。
-
床で過ごす時間を増やす
うつ伏せやゴロゴロ遊びができるスペースを作ってあげましょう。
-
おもちゃで誘導する
少し離れた場所にお気に入りのおもちゃを置いて、取りに行こうとする動きをサポートします。
-
親が一緒に動いて見せる
親がハイハイの姿勢を見せたり、声をかけながら床遊びすることで、赤ちゃんのやる気を刺激します。
焦らず、楽しみながら赤ちゃんの動きを見守ることが大切です。
大人が思う「もう〇ヶ月だからこう動いてほしい」という目安は、あくまでひとつの参考値。
赤ちゃんにはそれぞれのペースがあります。
周囲と比べて不安になることもありますが、大切なのは「今、その子がどう成長しているか」に目を向けることです。
もし不安や疑問があれば、一人で抱え込まずに、専門家のアドバイスを受けながら赤ちゃんの育ちを見守っていきましょう。
心配しすぎず、でもちゃんと気にかけてあげる――そのバランスが、赤ちゃんにとって何よりの安心につながります。
ハイハイが早い子の特徴は?
赤ちゃんの成長には個人差があるとはいえ、「もうハイハイしてるの!?」「うちの子、まだなのに…」と、早くから活発に動く赤ちゃんを見ると驚くことがありますよね。
実は、ハイハイを早く始める赤ちゃんにはいくつかの共通した特徴があります。
「ハイハイが早い子」にはどんな傾向があるのかを、体の発達、性格的な傾向、環境の影響など多角的にご紹介します。
まず、ハイハイは一般的に生後7~10ヶ月ごろに始まる子が多いと言われています。
中には6ヶ月前後からハイハイをし始める子もおり、こうした子が「早いタイプ」とされます。
「うつ伏せの状態で方向転換をしながら進む」「ズリバイをほとんどせずに、いきなり手足を使ったハイハイに移行した」といったケースも見られます。
では、こうした“早くハイハイを始める子”にはどんな特徴があるのでしょうか?
最も大きな要因のひとつが筋力や体幹(体の軸)の発達が早いことです。
早い時期から首がすわり、寝返りやおすわりをスムーズにクリアしてきた赤ちゃんは、腕や脚の筋肉、背筋、腹筋がバランスよく育っている傾向があります。
これにより、体を支えながら前に進む「ハイハイ」の動作がスムーズにできるようになるのです。
また、運動発達のスピードは個性によるところも大きく、遺伝的な体格や筋肉のつきやすさなども影響していると考えられています。
「なんでも触りたい!」「あっちに行きたい!」という強い好奇心も、早いハイハイに結びつく大きな特徴のひとつです。
こうした赤ちゃんは、仰向けでじっとしているよりも、手足を動かして探索することが好きで、「前に進みたい!」という気持ちが体を動かす原動力になります。
ハイハイは、意欲と運動が結びつく発達のステップ。
興味を持つものに向かって自ら進もうとする意思の強さが、ハイハイの早さに影響していると言えるでしょう。
赤ちゃんの発達には、「Tummy Time(たみーたいむ)」と呼ばれるうつ伏せ遊びの時間が非常に重要です。
うつ伏せで遊ぶことで、首・背中・腕の筋肉がバランスよく発達し、ハイハイへの準備が進みます。
早くハイハイを始める赤ちゃんは、比較的うつ伏せを嫌がらず、床で過ごす時間が長かったという傾向が見られます。
これは、日常の遊びの中で自然と筋力が育ち、動き出す準備が整っていたからとも言えるでしょう。
周囲に年の近い兄弟姉妹がいる、あるいは家庭内でよく話しかけられたり、目の前で大人が動き回っている環境では、赤ちゃんにとっての刺激が多く、動く意欲も引き出されやすくなります。
「お兄ちゃんのあとを追いかけたい!」「みんなのところに行きたい!」という思いから、自分で移動しようとする意欲が強くなり、ハイハイの開始が早まるケースも少なくありません。
生まれながらにして活発で「先に進みたい!」という気質を持っている子は、成長のステップも早く進むことがあります。一方で、マイペースな子はゆっくりと、じっくりと動きを覚えていくタイプ。
どちらが良い・悪いではなく、あくまで「その子らしさ」の表れです。気質によって発達のスピードに違いが出るのは自然なことなので、周りと比べすぎずに見守っていくことが大切です。
「ハイハイが早いと運動能力が高くなるの?」という声もありますが、実際にはハイハイの開始時期と将来の運動能力に直接的な相関はないとされています。
ただ、早い段階で自分の体を積極的に使ってきた経験は、筋力やバランス感覚を育てるうえでプラスに働くことは確かです。
だからといって、遅く始めた子が運動が苦手になるわけではありません。むしろ、本人の興味や好きな遊び方によって、運動能力はその後も大きく伸びていくのです。
ハイハイが早い子には、筋力の発達、好奇心、環境の影響など、いくつかの特徴があります。
ただし、どれも「こうだったら良い・悪い」というものではなく、すべてはその子自身の発達リズム。
ハイハイの早さに一喜一憂するよりも、「今、何に興味を持っているのか」「どんな動きをしようとしているのか」に目を向けて、たくさん声をかけながら応援してあげましょう。
それが、赤ちゃんの「もっとやってみたい!」という気持ちにつながっていきますよ!

(画像引用:モグモ公式サイト)
「今日のごはん、どうしよう…」
仕事から帰ってきて、保育園から子どもを迎えて、買い物して、夕飯を作って…毎日そんな繰り返しに疲れていませんか?
そんな忙しいママにおすすめなのが、幼児食宅配サービス mogumo(モグモ)。
1歳半〜6歳の子ども向けに、管理栄養士が考えた無添加・冷凍のおかずをお届けしてくれるんです。
✔ レンジでチンするだけ、調理はほぼゼロ!
✔ 栄養バランスもバッチリで偏食対策にも◎
✔ 忙しい夕食時に“あと1品”としても使える
「子どもがパクパク食べてくれる」だけで、ママの心もぐっと軽くなりますよ。
毎日の食事作りを少しラクにして、子どもと笑顔で過ごす時間を増やしてみませんか?
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ をタップ
をタップ






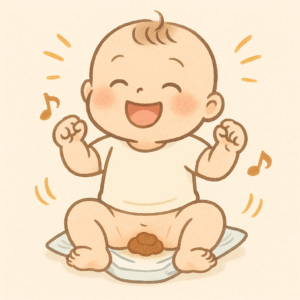



コメント