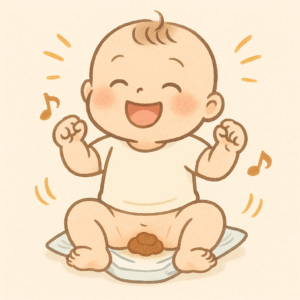赤ちゃんの成長を支えるために、母乳とミルクを上手に使い分ける「混合育児」。
だけど、「ミルクと母乳を交互にあげていたら母乳の出が減ってきた気がする」「夜だけミルクにしてるけど、このままでいいの?」と、不安を感じているママは少なくありません。
特に初めての育児では、「母乳の量はこのままで大丈夫?」「ミルクをどれくらい足せばいいの?」など、悩みは尽きないものです。
本記事では、混合育児でよくある悩みに寄り添いながら、「母乳量が減る原因と対策」「交互授乳のやり方」「夜だけミルクのメリット・デメリット」など、実践的なスケジュール例やミルクの適量も交えてわかりやすく解説します。
「完母でも完ミでもない、あなたらしい育児」がきっと見つかるよう、やさしく丁寧にお伝えしていきます。
【総額7,660円OFFクーポン】【特典付き】
初回限定キャンペーンでお得にGETできる!
(画像引用:モグモ公式サイト)
「子どもが小さいうちは、仕事も家事も育児も全部フル回転。気づけば自分の時間はゼロ…」
「健康的なご飯を準備してあげたいけど、うまく時間を作れない…」
そんなママの一番の悩みは“毎日のごはん作り”ではないでしょうか。そんな時におすすめなのが『モグモ』です。
モグモは1歳半〜6歳向けの幼児食宅配サービスで、無添加で栄養バランスに優れた冷凍ごはんが届くため、冷凍庫にストックしておけばいつでも使えるので安心です。
- 保育園帰りで子どもが「お腹すいた!」と言っても、レンジで数分チンするだけ
- 献立に悩む時間がなくなる
- 子どもが食べやすい味付け・サイズだから、食べムラが減る
「今日は疲れてごはんを作りたくない…」「子供にも栄養バランスが整った食事を摂らせたい」そんなときに助けてくれるんです。
家族の食卓を無理なく支えながら、ママに“心のゆとり”を取り戻してくれるはずです。今なら全額返金保証付きで安心して試せるので、気軽に始めてみてくださいね!
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ![]()
混合育児でミルクと母乳を交互にあげると母乳量が減る理由はコレ!
混合育児を始めたばかりのママからよく聞くのが、「ミルクと母乳を交互にあげていたら、母乳が出にくくなった気がする」という声です。
実際に、交互授乳を続けることで母乳量が減少するケースもあり、不安に感じるのは当然のこと。
しかし、これは授乳の仕組みを理解することで防げる可能性もあるのです。
母乳の分泌は「需要と供給」のバランスで決まる
母乳は赤ちゃんが吸うことで刺激を受け、脳から「プロラクチン」というホルモンが分泌され、乳腺が母乳をつくります。
このサイクルは「需要と供給」の関係で成り立っていて、赤ちゃんが吸えば吸うほど、母乳はつくられる仕組みです。
つまり、母乳を与える頻度が減る=需要が減る=供給も減るという流れが生まれてしまうため、交互にミルクを挟むと、母乳量が自然と減ってしまう可能性があるのです。
ミルクに頼りすぎると、母乳を出すタイミングを逃す。
「母乳の出が悪いからミルクを足す」のは悪いことではありません。
しかし、それが毎回の授乳で続くと、母乳を飲む回数が減る → さらに出にくくなる → ミルクがメインになるというサイクルに陥ることも。
とくに、ママの体が母乳を安定して作るまでの産後2〜3ヶ月頃は、この影響を受けやすい時期です。
ミルクを足しながらも、「できるだけ母乳を先にあげる」「ミルクをあげる前に搾乳する」など、母乳を出す刺激をキープする工夫が大切になります。
では、ミルクと母乳を交互にあげながら、母乳量を減らさずに育児を続けるにはどうすればよいのでしょうか?以下のような工夫がおすすめです。
母乳を先にあげるようにする:毎回、母乳からスタートすることで吸う回数を増やし、刺激を維持。
赤ちゃんが満足しない場合だけミルクを足す:「とりあえずミルク」ではなく、母乳の後に必要量だけ足すことを意識。
ミルクの回数が増えたら搾乳をする:夜などに母乳を与えずミルクだけにした場合でも、搾乳で刺激を与えると母乳の分泌が保たれやすくなります。
頻回授乳でリカバリー:日中に余裕があるときは、赤ちゃんに頻繁に吸ってもらうことで母乳量を取り戻すことが可能です。
赤ちゃんの満足度=母乳量ではない
注意しておきたいのは、「赤ちゃんがすぐ寝る=母乳が足りていない」とは限らないということ。
母乳は消化がよいため、ミルクよりも飲んだ後に眠りが浅くなることも多いです。そのため、「母乳では寝ないのに、ミルクを飲むとぐっすり寝る」からといって、母乳が出ていないと決めつけるのは早計です。
体重の増え方や、おしっこの回数などの客観的なサインを確認しながら、母乳・ミルクのバランスを見直していきましょう。
混合育児のスケジュール例と交互授乳の上手な取り入れ方
混合育児を続ける中で、多くのママたちが悩むのが「どんなスケジュールで授乳をすればよいの?」という点です。
特にミルクと母乳を交互に取り入れる場合、タイミングやバランスによって母乳の分泌量や赤ちゃんの満足度に影響することもあります。
ここでは、月齢別におすすめの混合授乳スケジュールや、「夜だけミルク」などの交互授乳のやり方について具体的に紹介します。
混合育児は「母乳とミルクのいいとこ取り」ができる育児方法です。母乳の免疫力やスキンシップのメリットを活かしつつ、ミルクの補助で赤ちゃんに必要な栄養と安心を与えることができます。
ただし、スケジュールの組み方次第では母乳の分泌が減ってしまったり、赤ちゃんが哺乳瓶を好みすぎて母乳を拒否するようになることも。
そのため、「ミルクは補助的に」「母乳の刺激を絶やさない」ことを意識したスケジューリングがポイントです。
■ 新生児期(0〜1ヶ月)
|
時間帯 |
授乳内容 |
|---|---|
|
6:00 |
母乳 + ミルク20〜30ml |
|
9:00 |
母乳のみ |
|
12:00 |
母乳 + ミルク20〜40ml |
|
15:00 |
母乳のみ |
|
18:00 |
母乳 + ミルク20〜40ml |
|
21:00 |
母乳のみ |
|
0:00 |
ミルクのみ50〜60ml(夜だけミルクの一例) |
|
3:00 |
母乳またはミルク40ml |
この時期は授乳回数が多く、夜中の授乳も必要です。母乳を優先しつつ、赤ちゃんの体重増加が緩やかな場合はミルクでサポートします。
■ 生後2〜3ヶ月
|
時間帯 |
授乳内容 |
|---|---|
|
6:00 |
母乳 |
|
9:00 |
母乳 + ミルク30ml |
|
12:00 |
母乳 |
|
15:00 |
母乳 + ミルク40ml |
|
18:00 |
母乳 |
|
21:00 |
母乳 or ミルク50ml(夜だけミルク) |
|
0:00 |
ミルク50〜60ml |
母乳の分泌が安定してくる時期。夜だけミルクに切り替える家庭も多くなります。
■ 生後4〜5ヶ月
この時期からは授乳間隔が少しずつあき始め、1日の授乳回数も5〜6回に。
離乳食が始まる前の準備期間でもあり、赤ちゃんによって必要な量に差が出てきます。夜だけミルクの導入で、ママが少し楽になるタイミングでもあります。
夜の授乳だけミルクに切り替えることで、赤ちゃんが満足して長く寝てくれる、というメリットがあります。
ママの睡眠時間の確保や、パパとの育児分担もしやすくなるため、近年とても注目されています。
成功のポイントは以下の3つ:
夜のタイミングに限定することを意識する → 夜間に母乳を与えないと母乳量が減るリスクがあるため、搾乳して刺激を保つのがおすすめです。
哺乳瓶の乳首を母乳に近いタイプにする → 哺乳瓶に慣れすぎて母乳を拒否しないよう工夫しましょう。
「寝かしつけ用ミルク」に頼りすぎない → ミルクに頼りきるのではなく、日中にしっかり母乳をあげてバランスをとることが大切です。
混合育児は「柔軟さ」が最大の強み
スケジュール通りにいかない日もあって当然。赤ちゃんの成長やママの体調によって、柔軟にやり方を調整するのが混合育児の魅力です。
母乳をベースにしながら、ミルクでサポートするという考え方を基本に、“赤ちゃんもママも無理なく過ごせるペース”を見つけていくことが、いちばん大切です。
混合育児でのミルクの量がわからない…適切な目安を月齢別で紹介
混合育児をしていると、「母乳がどれくらい出ているかわからないから、ミルクをどれくらい足せばいいのか迷う…」という声を多く聞きます。
完ミなら量がはっきりしていて管理しやすいのに、母乳とのバランスを考えると急に難しく感じるものです。
ここでは、赤ちゃんに必要なミルクの目安量や、母乳とミルクのバランスの取り方についてわかりやすく解説します。
なぜ「ミルクの量」がわかりにくいの?
混合育児では、母乳の出る量が個人差によって大きく異なります。
また、赤ちゃんの飲む量にも差があり、「飲みムラ」も日によって違うため、どうしても「足りてるのか不安…」となりがちです。
特に新生児期は母乳の分泌が安定していない時期でもあり、赤ちゃんの満足度=必要な栄養が足りているとは限らないため、適切な見極めが大切です。
混合育児の場合、ミルクは「補助」として考え、赤ちゃんの様子や母乳の出具合を見ながら足すのが基本です。
以下はあくまで目安ですが、参考にしやすいようにまとめました。
授乳回数:1日8〜10回(うちミルクは3〜5回程度) ミルクの量:1回あたり20〜60ml
※母乳を飲んだ後に「まだ口をパクパクする」「手足をバタバタさせて不機嫌」などの様子があれば、ミルクを少量足して調整します。
授乳回数:1日6〜8回 ミルクの量:1回あたり40〜80ml
この頃から母乳の分泌が安定してくる人も増えてきます。日中は母乳だけ、夜や夕方だけミルクというスタイルもおすすめです。
授乳回数:1日5〜6回 ミルクの量:1回あたり60〜100ml
赤ちゃんの体重増加や機嫌を見ながら、必要なときだけ補助的に足します。昼間は母乳中心、夜だけミルクにして睡眠時間を確保する家庭も多いです。
「なんとなく泣いてるからミルクを足す」ことが習慣になると、赤ちゃんがお腹が空いていなくても飲んでしまい、あげすぎになることがあります。
あげすぎを防ぐために、次のようなサインに注目しましょう。
飲んだ直後によく吐き戻す お腹がパンパンに張っている 授乳間隔が1時間未満で頻繁 体重が急激に増えすぎている(1ヶ月で1.5kg以上など)
特に母乳とミルクを交互にあげていると、ミルクの量だけがどんどん増えていくこともあるので注意が必要です。
ミルクの量は「赤ちゃんのサイン」で調整しよう
最も大切なのは、ミルクの量をママが決めすぎないことです。赤ちゃんの満足そうな表情、授乳後の様子、おしっこの量、便の状態など、体が発するサインを見ながら柔軟に対応することが大切です。
例えば…
授乳後にウトウトしてリラックスしている→足りている可能性が高い 授乳後すぐに泣き出して口を動かす→まだお腹が空いているかも 授乳間隔が2〜3時間あいて機嫌がいい→適切な量で満足している証拠
体重の増え方も目安になる
1日ごとの体重増加に一喜一憂する必要はありませんが、1週間で150〜200gほど増えていれば、栄養はしっかり足りていると判断できます。
定期的に母子手帳に記録する、家庭用のベビースケールで確認するなど、客観的な数値で判断するクセをつけておくと安心です。
無理に「決まった量」をあげなくてOK
混合育児では、「この月齢だからこの量を絶対飲まなきゃ」と神経質になるよりも、その時の赤ちゃんの状態に合わせて調整することが成功のカギです。
日によって飲む量に波があって当然。昨日たくさん飲んだから今日は少なくても大丈夫、と長い目で見守る気持ちを大切にしましょう。
混合育児で夜だけミルクを使うメリットとデメリット
「日中は母乳中心、夜だけミルクを足してぐっすり寝かせたい」
そんな願いから、夜だけミルクを取り入れる混合育児を実践しているママは少なくありません。
実際、夜だけミルクにはたくさんのメリットがある一方で、注意点やデメリットもあるのが現実です。
ここでは、夜だけミルク育児の効果や、母乳への影響、注意点について詳しく解説します。
夜だけミルクのスタイルとは?
混合育児における「夜だけミルク」とは、日中の授乳は母乳を中心に行い、夜間だけミルクを与えるスタイルのことです。とくに、寝る前の21時〜24時ごろにミルクを飲ませることで、赤ちゃんが長く寝てくれやすくなり、ママの睡眠も確保しやすくなるという利点があります。
夜だけミルクのメリット
① 赤ちゃんが長く眠ってくれる可能性がある
母乳は消化が早いため、母乳だけではすぐにお腹が空いて夜中に起きてしまうこともあります
。一方、ミルクは消化に時間がかかるため、赤ちゃんが3〜4時間まとまって寝てくれる傾向があります。
「夜だけでも長く眠れる時間が欲しい…」というママにとって、これは大きなメリットです。
② ママの体力回復につながる
産後はただでさえ寝不足が続く毎日。夜間の授乳を1回でも減らすことで、ママの体力や気力を回復する時間が取れるようになります。
ミルクをあげる時間はパパや祖父母に任せて、ママがしっかり眠れる環境をつくることも大切です。
③ 授乳の負担が軽減される
特に乳首の痛みや母乳トラブルがある場合、夜間だけでも哺乳瓶に切り替えることで身体を休められるのはありがたいこと。混
合育児ならではの「柔軟性」を活かせる場面です。
夜だけミルクのデメリットと注意点
① 母乳量が減る可能性がある
夜間授乳は、母乳の分泌を促す大事なタイミングです。特に深夜(0時〜4時ごろ)は「プロラクチン」という母乳を作るホルモンの分泌が多くなる時間帯。
そのため、この時間帯に授乳をしないと、刺激不足から母乳の分泌が減ってしまうことがあります。
対策としては、夜にミルクをあげたとしても、ママが搾乳で乳房を刺激しておくと母乳量を維持しやすくなります。
② 哺乳瓶に慣れて母乳を拒否する可能性
ミルクに慣れてくると、赤ちゃんが「哺乳瓶の方が楽」と感じてしまい、母乳を吸うのを嫌がるケースもあります。
特に乳首が柔らかく、飲みにくさを感じている赤ちゃんに起こりがちです。
このリスクを減らすためには、母乳実感タイプの哺乳瓶やスローな流量の乳首を使うことがポイントです。
③ 飲みすぎに注意
夜だけミルクのつもりが、「赤ちゃんが寝てくれないから」とつい多めにあげてしまうケースもあります。
ミルクを足す場合も、1回あたり60〜100ml程度が目安。
飲ませすぎると、吐き戻しや腹痛を引き起こすこともあるため、あくまで補助的にと考えましょう。
月齢や体重によって多少異なりますが、おおよその目安は以下の通りです。
|
月齢 |
夜のミルク目安量 |
|---|---|
|
0〜1ヶ月 |
40〜60ml |
|
1〜2ヶ月 |
60〜80ml |
|
3〜4ヶ月 |
80〜100ml |
※母乳を先に飲んだ後に足す場合は、上記量の半分〜7割程度でも十分なことが多いです。
こんな時は夜だけミルクを試してみても◎
-
母乳育児を続けたいが、夜間授乳がつらくなってきた
-
体力の回復やストレス軽減が必要なとき
-
赤ちゃんが母乳だけでは寝つきが悪いと感じるとき
無理して完母を目指すより、母乳とミルクのバランスを自分に合う形に調整することが、育児を楽しく続けるコツです。
母乳だけで寝てしまう赤ちゃん…ミルクを足すべき?チェックするのはこの3つ!
「母乳を飲んでいる途中で寝てしまって、全然ミルクまでたどりつかない」
「おっぱいだけで寝ちゃったけど、これって足りてるの?」
混合育児をしているママたちから、よく聞かれる悩みのひとつです。母乳の量が見えないからこそ、「本当に満足しているのか」「足りていないのでは」と不安になりますよね。
ここでは、母乳だけで寝てしまう赤ちゃんへの対応方法や、ミルクを足すべき判断基準についてわかりやすく解説します。
母乳だけで寝る=満腹とは限らない
赤ちゃんが母乳を飲みながらウトウトして寝てしまうと、「満足して眠ったのかな?」と思いがちですが、実はまだ飲み足りないのに寝てしまっているだけというケースも多いです。
特に新生児期〜生後2ヶ月ごろまでは、赤ちゃんの吸う力も弱く、疲れてすぐに眠ってしまうことがあります。
そうすると、母乳の摂取量が不十分なまま寝てしまい、すぐに起きて泣く→また授乳、の繰り返しになることも。
すぐ寝る赤ちゃんにありがちなパターン
飲み始めて5分以内にウトウト 一見満足そうだけどすぐに起きて泣く 授乳後のおしっこの回数が少ない 授乳間隔が1時間以内で頻繁
これらは、「寝ている=満腹」とは言い切れないサインです。
母乳だけで寝たときにチェックしたいこと
赤ちゃんが母乳だけで寝てしまったときは、次のようなチェックをしてみましょう。
母乳は飲み始めの方は水っぽく、後半になるにつれて脂肪分が多くなります(これを「後乳」といいます)。短時間しか吸えていない場合、満足感が得られていないことがあります。
口を動かしていても、実は「浅飲み」でほとんど出ていないこともあります。
赤ちゃんののどが動いているか、ゴクッという音がしているかがポイントです。
おっぱいの後にすぐに泣き出す、手を口に持っていく、体を反らせるなどの様子があれば、まだお腹が空いているサインかもしれません。
ミルクを足すか迷ったら「様子を見て足す」が正解
赤ちゃんが母乳で寝てしまっても、毎回ミルクを足す必要はありません。
赤ちゃんの体重増加が順調で、おしっこが1日6〜8回以上出ていて、機嫌もいいなら、そのまま母乳だけでも問題ないことが多いです。
ただし、以下のような場合は、少量だけミルクを足して様子を見るのがおすすめです。
-
授乳後すぐに泣いて起きるのが続く
-
体重の増加がゆるやか、または減っている
-
おしっこの回数が少ない
-
授乳に30分以上かかってしまい、ママが疲れている
このようなときは、母乳のあとに40〜60mlだけミルクを足すことで赤ちゃんが満足し、落ち着いて眠ることができます。
赤ちゃんが母乳だけで寝てしまうのが続くと、「もっと出るようにしたいのに、吸われる時間が減ってしまう…」と悩むママも多いです。
そんなときは以下の方法で、母乳分泌を維持・増加させることができます。
寝てしまったあとに搾乳で刺激する 母乳の前に少し乳房マッサージをして出やすくしておく 赤ちゃんが起きているタイミングを見計らって授乳 頻回授乳(2〜3時間おき)を意識する
「ミルク=負け」ではない
混合育児をしていると、「母乳で寝てしまったけど足りていないかも」と不安になり、「ミルクを足すのは母乳が足りていない証拠」と思い込んでしまうことがあります。
でも、ミルクを足すことは、赤ちゃんの健康を第一に考えているからこその行動です。
完母にこだわりすぎず、赤ちゃんの様子と自分の体力を見ながら、柔軟に対応することが大切です。
混合育児でミルクのあげすぎを防ぐ、4つのポイント!
混合育児では、母乳とミルクのバランスをとりながら赤ちゃんを育てていきますが、その中で意外と多いのが「ミルクのあげすぎ」問題。
「なんとなく泣いているから」「飲み残すと心配だから」といった理由でミルクを多く与えてしまうと、赤ちゃんの体に負担がかかったり、母乳の分泌が減ってしまうこともあります。
ここでは、ミルクのあげすぎによる影響や防ぐための工夫について詳しく解説します。
混合育児では、母乳の量が目に見えないため、「足りているのか不安…」という気持ちからミルクを多めに用意しがちです。
赤ちゃんが泣いていると、「もっとお腹が空いているのかも?」と判断してしまい、本当は必要以上の量を飲ませてしまうことがあるのです。
また、「飲み切るまであげないといけない」という思い込みも、あげすぎにつながる要因のひとつです。
ミルクのあげすぎによる影響とは?
① 消化不良や吐き戻し
ミルクは母乳よりも消化に時間がかかるため、あげすぎると胃に負担がかかり、吐き戻しや腹痛の原因になります。
② 過度な体重増加
赤ちゃんの成長は個人差がありますが、急激に体重が増えると将来の肥満傾向につながる可能性があるとも言われています。
特に1ヶ月で体重が2kg以上増加している場合は、医師に相談するのが安心です。
③ 母乳量の減少
ミルクを飲ませる回数が多くなると、母乳を吸う回数が減ってしまい、結果として母乳の分泌量が減っていくことがあります。
これは「需要と供給のバランス」が崩れてしまうためです。
以下のような様子が見られる場合は、ミルクのあげすぎを疑ってみる必要があります。
-
飲んだ後によく吐き戻す
-
授乳の間隔が1〜2時間未満
-
授乳後も苦しそうに泣く・お腹が張っている
-
おしっこの量が極端に多く、色も濃い
-
成長曲線を大きく超えて体重が増えている
赤ちゃんは「満腹でも飲む」ことがあります。特に哺乳瓶は少ない力で簡単に飲めてしまうため、「吸っている=お腹が空いている」とは限らないのです。
月齢や赤ちゃんの体重によってミルクの目安は変わりますが、あくまでも目安であり、実際にはその日の体調や機嫌にも左右されます。
以下は月齢別の目安量ですが、毎回この量を飲まなくても心配いりません。
|
月齢 |
ミルクの1回量(目安) |
|---|---|
|
0〜1ヶ月 |
40〜80ml |
|
1〜2ヶ月 |
60〜100ml |
|
3〜4ヶ月 |
80〜120ml |
母乳をしっかり飲んでいる場合は、この量の7割〜半量程度で足りることもあります。
1. 母乳を先に飲ませる
ミルクを足す前に、必ず母乳を与えることを習慣化しましょう。
先に母乳を吸わせることで、母乳の分泌を維持しながら、ミルクの量を必要最低限に抑えることができます。
2. 赤ちゃんの飲むペースを観察する
哺乳瓶を傾けて流れやすくすると、赤ちゃんは飲み続けてしまうことがあります。
途中で一度止める・様子を見ることで、飲みすぎを防ぐことができます。
3. 哺乳瓶の乳首の流量を調整する
流れが早すぎる乳首は、赤ちゃんが「飲み疲れる前に満腹になる」ため、本来の満足感が得られにくいことも。
年齢に応じた乳首を使用しましょう。
4. 授乳記録をつける
日々の授乳の量や時間を簡単に記録しておくと、「今日はあげすぎたかも」といった気づきが得やすくなります。アプリや手帳を使って無理のない範囲で記録するのがおすすめです。
最後に:ミルクは「赤ちゃんのための安心材料」
混合育児では、つい「ミルクは必要悪」や「できるだけ使わない方がいいもの」と思ってしまいがちです。
でも、ミルクは赤ちゃんに必要な栄養をしっかり届ける手段。
大切なのは、「母乳とミルク、どちらが良いか」ではなく、「赤ちゃんにとってちょうど良い量で満足してもらえているか」という視点です。
ママ自身の体力や生活リズムを守りながら、赤ちゃんにとってベストな形を見つけていきましょう。
母乳とミルクで育った子に違いはある?ポイントは育て方!
「母乳の方がいいって言われるけど、ミルクで育てたら何か違うの?」
「混合育児だと将来に影響があるのでは?」
こうした不安を抱えているママやパパは少なくありません。
特に「完母が理想」と言われがちな世間の風潮の中で、ミルクや混合育児を選ぶことに罪悪感を感じてしまう人もいるでしょう。
しかし、結論から言えば、母乳でもミルクでも、愛情をもって育てられた赤ちゃんは元気に育ちます。
ここでは、母乳とミルクで育った子の違いについての事実と、気にしすぎないための心構えをご紹介します。
育て方によって「赤ちゃんに違いが出るのでは?」と気になりますが、実際のところ、大きな違いが生まれるケースはほとんどありません。
ただし、それぞれに特徴やメリットがあるため、どちらにも良さがあるという視点で見ていくことが大切です。
【母乳育児の特徴とメリット】
-
免疫力を高める成分が含まれている
母乳には、IgA(免疫グロブリンA)など、赤ちゃんの免疫をサポートする成分が豊富に含まれています。そのため、感染症やアレルギー予防に一定の効果があるとされています。
-
スキンシップが自然と増える
授乳時にママと赤ちゃんが密着することで、安心感や愛着形成が促されます。
-
消化がよく、便通が整いやすい
母乳は赤ちゃんの体に合わせて作られるため、消化吸収がしやすく、便がやわらかくなる傾向があります。
【ミルク育児の特徴とメリット】
-
授乳量が目に見えてわかる
赤ちゃんが何ml飲んだかが明確なので、特に新生児期の成長管理がしやすいです。
-
パパや祖父母も授乳に参加できる
ママだけに負担が集中せず、家族全員で育児ができるメリットがあります。
-
時間や場所を選ばずに授乳できる
外出先や夜間の授乳にも対応しやすく、スケジュールが組みやすくなります。
実際に育った子にどんな違いがあるの?
では、母乳だけで育った子とミルクで育った子に、実際どんな違いがあるのでしょうか?
▶ 発達や知能に差はない
多くの研究で、「母乳育児が知能に良い影響を与える」といった報告もありますが、家庭環境や育児のかかわり方による影響の方が大きいとされています。
つまり、母乳かミルクかよりも、「親がどう接しているか」「どれだけ話しかけ、愛情をかけているか」が子どもの成長に大きく関わっているのです。
▶ 成長曲線も個人差が大きい
「ミルクの方が太りやすい」「母乳の子はスリムに育つ」といった印象を持つ人もいますが、これは赤ちゃんそれぞれの体質や代謝の違いによるものが大半です。授乳方法によって成長に偏りが出ることはほとんどありません。
混合育児は「いいとこどり」の育児スタイル
混合育児をしていると、「中途半端では?」「どっちつかずで赤ちゃんに悪いのでは?」と感じてしまう方もいるかもしれません。
でも、実際には母乳の免疫効果と、ミルクの栄養安定性の両方を活かせる育児法なのです。
混合育児を選ぶ理由も人それぞれ。たとえば…
-
母乳の出が安定しない
-
ママの体調に合わせたい
-
育児の負担を軽減したい
-
夜はパパに任せたい
どれも立派な理由ですし、赤ちゃんにとって一番良い方法を考えている証拠です。
育て方に「正解」はない
大切なのは、「何を与えたか」よりも、「どう育てたか」「どんな関わりをしてきたか」です。
赤ちゃんは、母乳かミルクかよりも、「お腹が満たされて安心して抱っこされること」「声をかけてもらうこと」で、心も体もすくすく育ちます。
そして、赤ちゃんの成長には無数の要素が影響しています。
授乳だけで子どもの未来が決まるわけではありません。愛情を持って関わることが何よりの栄養なのです。
混合育児を続けるために大切なこと
混合育児は、母乳とミルクの良いところを取り入れながら、赤ちゃんとママにとって“無理のない育児”を目指す方法です。けれど、「どのくらいミルクを足せばいいの?」「母乳が減ってきた気がする…」と、日々不安を抱えながら過ごしている方も多いのではないでしょうか。
それでも、ここまで見てきたように、混合育児には明確なルールや“正解”はありません。
大切なのは、「赤ちゃんが元気に育ち、ママも無理なく続けられる形を見つけていくこと」です。
混合育児を続けるためのポイント
① 「母乳ファースト」を意識して
母乳の分泌を維持したいときは、できるだけ授乳のスタートを母乳からにするのが基本です。もし赤ちゃんが満足できなければ、必要に応じてミルクを補うという流れにすることで、母乳の刺激を保ちやすくなります。
② ミルクの量は赤ちゃんの様子で調整
「毎回◯ml飲ませなければいけない」という固定観念にとらわれず、赤ちゃんの満足度や体重の増加ペース、おしっこの回数などを見ながら、ミルクの量を柔軟に調整していきましょう。
③ ママの心と体を守る選択を
混合育児は、母乳だけでは体がつらいとき、睡眠を確保したいとき、家族にサポートをお願いしたいときの心強い選択肢です。「ミルクに頼るのは甘え」と思わず、ママの心と体の健康を保つことも、赤ちゃんにとって大切なケアのひとつです。
最後に:完母じゃなくても、立派な育児
「母乳が減ってきたかも」「ミルクばかりになってきた」と不安になることがあっても、それはあなたが赤ちゃんを大切に想っている証拠。混合育児は、決して妥協や不完全な方法ではありません。
むしろ、ママと赤ちゃんの状況に寄り添った、やさしく柔軟な育児スタイルです。
完母でも、完ミでも、混合でも、どれも「赤ちゃんを愛して育てる」ための手段にすぎません。
周りと比べる必要はありません。あなたと赤ちゃんにとって“ちょうどいい”バランスを、安心して見つけていってくださいね。

(画像引用:モグモ公式サイト)
「今日のごはん、どうしよう…」
仕事から帰ってきて、保育園から子どもを迎えて、買い物して、夕飯を作って…毎日そんな繰り返しに疲れていませんか?
そんな忙しいママにおすすめなのが、幼児食宅配サービス mogumo(モグモ)。
1歳半〜6歳の子ども向けに、管理栄養士が考えた無添加・冷凍のおかずをお届けしてくれるんです。
✔ レンジでチンするだけ、調理はほぼゼロ!
✔ 栄養バランスもバッチリで偏食対策にも◎
✔ 忙しい夕食時に“あと1品”としても使える
「子どもがパクパク食べてくれる」だけで、ママの心もぐっと軽くなりますよ。
毎日の食事作りを少しラクにして、子どもと笑顔で過ごす時間を増やしてみませんか?
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ をタップ
をタップ