「気づいたら23時…今日も寝かしつけに1時間以上かかった…」
そんな毎晩を繰り返していませんか?
2歳を過ぎると体力もついて、日中しっかり遊んでもなかなか寝ない。
昼寝の影響?テレビ?イヤイヤ期?
親としては「夜更かしで発達に影響が出るのでは…」と不安になりますよね。
寝かしつけの時間がどんどん後ろにズレて、イライラして怒ってしまったり、
泣きわめく子をつい放置してしまって自己嫌悪に陥ることも…。
この記事では、
- 2歳の理想的な寝る時間とその理由
- 就寝が遅いことで起きやすい影響
- 23時以降の就寝が続く原因と対処法
- 怒り・イライラ・放置との向き合い方
- 今日から始められる寝かしつけのコツ
など、同じ悩みを抱えるママパパに寄り添いながら、わかりやすく解説していきます。
「うちの子だけじゃないんだ」と思える体験談やアドバイスも盛りだくさん。
まずは一歩ずつ、無理のないペースで生活リズムを整えていきましょう。
【総額7,660円OFFクーポン】【特典付き】
初回限定キャンペーンでお得にGETできる!
(画像引用:モグモ公式サイト)
「子どもが小さいうちは、仕事も家事も育児も全部フル回転。気づけば自分の時間はゼロ…」
「健康的なご飯を準備してあげたいけど、うまく時間を作れない…」
そんなママの一番の悩みは“毎日のごはん作り”ではないでしょうか。そんな時におすすめなのが『モグモ』です。
モグモは1歳半〜6歳向けの幼児食宅配サービスで、無添加で栄養バランスに優れた冷凍ごはんが届くため、冷凍庫にストックしておけばいつでも使えるので安心です。
- 保育園帰りで子どもが「お腹すいた!」と言っても、レンジで数分チンするだけ
- 献立に悩む時間がなくなる
- 子どもが食べやすい味付け・サイズだから、食べムラが減る
「今日は疲れてごはんを作りたくない…」「子供にも栄養バランスが整った食事を摂らせたい」そんなときに助けてくれるんです。
家族の食卓を無理なく支えながら、ママに“心のゆとり”を取り戻してくれるはずです。今なら全額返金保証付きで安心して試せるので、気軽に始めてみてくださいね!
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ![]()
2歳の理想的な寝る時間は何時?
2歳頃になると、昼寝の時間が短くなったり、夜の寝かしつけに時間がかかったりと、睡眠リズムの変化に戸惑うママ・パパも多い時期です。
「うちの子、寝るのが23時すぎ…遅すぎるのでは?」と感じることはありませんか?
ここでは、2歳児にとっての“理想的な寝る時間”について、科学的な根拠や専門家の意見を交えながら詳しく解説します。
一般的に、小児科医や睡眠専門家が推奨している2歳児の理想的な就寝時間は「夜8時〜9時(20時〜21時)」の間とされています。
これは、2歳という年齢が心と体の発達が著しい時期であり、十分な睡眠時間が必要だからです。
アメリカ国立睡眠財団(National Sleep Foundation)のガイドラインによると、1〜2歳の子どもには1日あたり11〜14時間の睡眠が必要とされています。
日中に1〜2時間の昼寝をしていたとしても、夜には9〜12時間はしっかり眠ることが望ましいのです。
たとえば、2歳の子が23時に就寝し、朝7時に起きるとしましょう。
この場合の睡眠時間は8時間ですが、これは理想より3〜4時間も少ない計算になります。
2歳児は大人よりも脳が活発に成長しているため、睡眠不足が続くと以下のような影響が心配されます。
-
昼間の集中力・機嫌の悪化
-
情緒の不安定さ
-
成長ホルモンの分泌不足
-
夜泣きや中途覚醒が増える
-
食欲や生活リズムの乱れ
「少し寝るのが遅いくらい平気」と思いがちですが、慢性的な睡眠不足は、発達や健康面にジワジワと影響を及ぼす可能性があるのです。
人の体には「サーカディアンリズム(概日リズム)」と呼ばれる体内時計があり、日中の活動と夜の休息を自然にコントロールしています。
夜になると、「メラトニン」という睡眠を促すホルモンが脳から分泌され、体を休息モードに導いてくれます。
このメラトニンの分泌が始まるのが19〜21時ごろであり、分泌のタイミングでスムーズに眠りに入るためには、この時間に“おやすみの準備”を始めておくことが重要です。
逆に、夜遅くまで明るい部屋でテレビやスマホを見ていたり、遊んでいたりするとメラトニンの分泌が抑制されてしまい、眠りの質が低下する原因になります。
共働き家庭や、上の子のスケジュールに合わせざるを得ないなど、家庭の事情で早い時間に寝かしつけるのが難しい場合もあるでしょう。
そのような場合でも、「就寝リズムを整える」ことを意識していくことで、23時就寝でも多少の改善が見込めます。
以下のようなポイントを取り入れるとよいでしょう:
-
毎日同じ時間に布団に入るようにする
-
寝る前1時間はスマホ・テレビをやめる
-
部屋の照明を徐々に暗くして“夜”を演出する
-
ぬいぐるみ・絵本・音楽など“寝るための合図”をルーティン化する
たとえ寝る時間が23時でも、「夜の過ごし方」「眠る前の刺激」を整えるだけで睡眠の質は大きく変わります。
2歳の寝る時間が23時になることは、今の育児環境では決して珍しくありません。
「遅すぎる」「ダメな親かも」と自分を責める必要はありませんが、
理想は20〜21時の就寝であり、そこを少しでも意識することが子どもの発達と親のゆとりにつながります。
無理に完璧を目指さず、まずは“寝る準備を始める時間”を意識してみることから始めてみてくださいね。
23時以降に寝るのは遅すぎる?その影響とは
「2歳なのに、毎晩寝るのは23時すぎ」「寝かしつけても元気いっぱいで全然寝ない」
そんな状況が続くと、「このままで大丈夫かな…」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
実際、子どもの就寝時間が遅くなることは、発達・健康・情緒面にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。ここでは、23時以降の就寝がもたらす具体的な影響について詳しく見ていきましょう。
子どもの成長に欠かせない「成長ホルモン」は、眠り始めてからの深いノンレム睡眠中に多く分泌されるとされています。
このホルモンは、骨や筋肉の発達を促すだけでなく、脳の発達や免疫力の強化にも重要な役割を果たしています。
通常、22時〜翌2時の間が「ゴールデンタイム」と呼ばれる成長ホルモン分泌のピーク時間です。
この時間帯に深く眠れていないと、成長ホルモンが十分に分泌されず、身長や体の発育が遅れやすくなる可能性もあるのです。
2歳は言葉や感情の発達が急速に進む時期。睡眠は、その日に得た情報や体験を整理し、記憶として定着させる時間でもあります。
この重要な睡眠時間が不足すると、
-
語彙力の伸びが鈍くなる
-
情緒のコントロールが難しくなる
-
集中力が続かない
-
落ち着きがなくなる(多動傾向)
といった症状が見られることがあります。
もちろん一概には言えませんが、「昼間ぐずりが多くなった」「何をしても機嫌が悪い」といった変化がある場合、慢性的な寝不足が原因になっている可能性もあるのです。
最近では「2歳 寝ない 発達障害」というキーワードで検索するママ・パパも増えています。
確かに、発達障害の傾向を持つ子どもは、睡眠リズムの乱れや入眠の困難さが見られるケースもあります。
しかし、就寝時間が遅くなっている原因が生活リズムの乱れや習慣によるものであることも非常に多く、
「寝ない=発達障害」とは決して言い切れません。
むしろ、寝不足からくる落ち着きのなさや感情の爆発が、発達に問題があるように見えてしまっているケースも存在します。
不安な場合は、早めに小児科や保健師に相談しつつ、まずは睡眠環境の見直しをしてみることが大切です。
実は、子どもの就寝が遅くなることで影響を受けるのは“子どもだけ”ではありません。
ママ・パパのメンタルにも大きな負担となっています。
特に多いのがこんな声です:
-
「寝かしつけに1時間以上かかって、イライラして怒ってしまう」
-
「自分の時間がなくてストレスが限界」
-
「つい放置してしまって、後から自己嫌悪になる」
夜の23時以降まで寝ない子どもに付き合うことは、親にとっても体力的・精神的に大きな負担になります。
さらにそのイライラが子どもに伝わってしまい、ますます眠れなくなる…という悪循環にも陥りがちです。
23時すぎに寝ると、当然ながら起床時間も遅くなります。
朝起きるのが9時・10時になれば、昼寝も遅くなり、結果的に夜の寝る時間も遅れる…という悪循環のループに。
このループが習慣化してしまうと、保育園や幼稚園の入園時、生活リズムを整えるのが非常に困難になってしまうケースもあります。
また、将来的に睡眠の質が下がったまま成長し、「寝つきが悪い」「朝が弱い」などの問題が長く続く可能性もあるのです。
ここまで、23時以降の就寝がもたらすリスクについて解説してきましたが、
「もう遅く寝る習慣がついてしまったから手遅れかも…」と不安になる必要はありません。
むしろ、少しずつでも就寝時間を前倒しする工夫を取り入れていくだけで、子どもの睡眠は大きく変わっていきます。
-
寝かしつけのルーティンを決める
-
寝室の明かりや音を見直す
-
夕方以降の過ごし方を変えてみる
といったポイントを押さえることで、23時就寝を22時台、21時台へと段階的にシフトしていくことが可能です。
23時すぎの就寝が続くと、子どもの発達や情緒面への影響だけでなく、親の心身の負担も増加していきます。
ただし、すぐに理想のリズムに戻す必要はありません。
焦らず、“夜は眠る時間”という感覚を育てていくことから始めてみましょう。
次の見出しでは、「なぜ2歳の子が夜なかなか寝ないのか?」その原因を深掘りしていきます。
2歳がなかなか寝ないのはなぜ?原因を探る
「もう布団に入って1時間…全然寝る気配がない」
「寝室に行くと“まだ寝たくない!”と泣き出してしまう」
2歳前後になると、子どもがなかなか寝ないことに悩む家庭はとても多いです。
遅寝の習慣がついてしまう前に、まずは「なぜ寝ないのか?」という原因をしっかり見極めることが大切です。
ここでは、2歳児がなかなか寝ない主な理由を7つの視点から詳しく解説していきます。
2歳児はまだ昼寝が必要な時期ですが、昼寝の時間帯や長さによって夜の睡眠に影響が出ることがあります。
よくあるパターン:
-
昼寝が15時以降になってしまい、夜眠れなくなる
-
2時間以上の長い昼寝で夜に眠気がこない
-
保育園でしっかり寝すぎて夜元気すぎる
📝対策のヒント:
昼寝は13時〜15時の間に1〜1.5時間以内を目安にすると、夜の眠気を妨げにくくなります。
就寝前にスマホ・テレビ・タブレットなどを見せていませんか?
これらの画面から発せられるブルーライトは、脳を覚醒させてしまうため、眠気を感じにくくなります。
特に就寝の1時間前に視覚刺激の強いアニメやゲームを見ていると、眠るモードに切り替わるのが難しくなるのです。
📝対策のヒント:
夜は照明を暗めにし、スマホ・テレビは就寝の1時間前には消すことが理想的です。
体をしっかり動かしていないと、エネルギーが余って夜になっても元気いっぱいに。
「雨で一日中家にいた」「お昼寝だけしっかりした」日は、寝つきが悪くなることがよくあります。
📝対策のヒント:
毎日30分〜1時間程度の外遊びやお散歩の時間を取り入れると、夜ぐっすり眠りやすくなります。
「まだ遊びたいのに!」「パパともっと一緒にいたい!」
2歳児は“今が楽しい”という気持ちが強いため、寝ることを「楽しさを奪われる時間」と捉えてしまうことがあります。
また、怒られて寝室に連れて行かれた経験などがあると、「寝る=怒られる時間」と認識してしまい、拒否反応が出ることも…。
📝対策のヒント:
「寝る時間=安心・心地よい時間」と感じられるように、入眠儀式(絵本・子守唄・スキンシップ)をルーティン化するのがおすすめです。
2歳ごろは言葉が急に増え始める時期。
その影響で、頭の中が刺激でいっぱいになり、興奮して眠れなくなることもあります。
また、「ママ見て」「お話ししよう」と話しかけてくるのは、言語能力が伸びてきた証拠でもあり、成長の一環です。
📝対策のヒント:
就寝前は静かな語りかけや絵本の読み聞かせなどで、気持ちをクールダウンさせる時間をつくることが大切です。
「早く寝て!」「なんで寝ないの⁉」とイライラしながら寝かしつけをしていると、その親の焦りや怒りの感情が子どもに伝染して、余計に寝なくなることがあります。
子どもは非常に敏感で、表情・声のトーン・空気の緊張感から、親の感情を敏感にキャッチしています。
📝対策のヒント:
たとえ寝かしつけが長引いても、“落ち着いた声”で優しく接するだけで、入眠率は大きく変わります。
2歳ごろは「ママと離れるのが不安」「ひとりで寝るのが怖い」と感じる分離不安のピーク時期でもあります。
「寝室に行ったとたんに泣く」「寝る前に不機嫌になる」場合は、安心感が足りていないサインかもしれません。
📝対策のヒント:
「ママは隣にいるよ」「一緒に寝ようね」と安心できる言葉かけをしながら、そっと背中をさすったり、手を握ったりするだけでも落ち着きやすくなります。
2歳の子どもが寝ないのには、単純な「わがまま」ではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。
まずは、
-
昼寝
-
刺激(スマホ・遊び)
-
活動量
-
親の接し方
-
子どもの心理状態
などの日々の生活の中で、何が原因になっているのかを観察することがとても大切です。
原因がわかれば、改善の糸口も見えてきます。
発達障害と関係がある?判断の注意点
「2歳なのに夜0時になっても寝ない…」
「寝かしつけてもすぐ起きる」「毎日睡眠時間が短い」
そんな状況が続くと、ふと頭をよぎるのが──
「もしかしてうちの子、発達障害なのでは…?」という不安です。
ここでは、2歳児の「寝ない」行動と発達障害との関係、また判断の注意点や誤解しやすいポイントについて丁寧に解説します。
まず最初に伝えたいのは、
「寝ないからといって、すぐに発達障害を疑う必要はない」
ということです。
2歳はまだ、言葉の発達・感情表現・生活リズムなど、個人差が非常に大きい時期です。
「寝ない」「落ち着きがない」「癇癪を起こす」などの行動は、発達段階でよくある一時的な現象であることも多いのです。
実際に、2歳前後の子どもを持つ家庭では、
-
寝かしつけに1時間以上かかる
-
夜中に何度も起きる
-
昼寝と夜のリズムがぐちゃぐちゃ
などの悩みを抱える方が多数います。
SNSや知恵袋には次のような声も:
「うちの子も23時まで寝ない毎日でした」
「寝ぐずりがひどくて2時間泣きっぱなし」
「夜中1時に突然元気になってしまう」
これらのケースは、発達障害ではなく“睡眠習慣の乱れ”や“環境的な要因”が原因であることがほとんどです。
とはいえ、なかには「眠れない」という症状の背景に、発達の特性があるケースもあります。
睡眠だけでなく、複数の行動や反応が気になる場合には注意が必要です。
以下のような様子が重なって見られる場合、専門機関への相談をおすすめします:
|
気になるサイン |
内容例 |
|---|---|
|
言葉の発達が著しく遅れている |
2語文が出ない、名前を呼んでも振り向かない |
|
こだわりが極端に強い |
同じ道順・同じおもちゃじゃないとパニックになる |
|
音や光などに過敏 |
掃除機の音、明るいライトに過剰反応する |
|
落ち着きがなく常に動き回っている |
座って遊べない、走り回る |
|
目を合わせない、指差しがない |
コミュニケーションが極端に乏しい |
📝ポイント:
「寝ない」だけでなく、発語・行動・感覚の反応など、他の特性との“複合性”を見極めることが大切です。
「発達障害だったらどうしよう…」と悩んでいても、ネット検索だけでは答えが出ないことがほとんどです。
だからこそ、
-
かかりつけの小児科医
-
地域の保健センター
-
発達支援センター
など、専門の視点を持つ機関に相談することを強くおすすめします。
早期に相談することで、
-
子どもに合った接し方
-
家庭でできる支援
-
必要であれば専門機関の紹介
など、具体的なサポートを受けられることもあります。
実は、「発達障害ではないけれど、ちょっと育てにくい」と感じる子どもでも、地域の子育て支援サービスを利用できるケースは多くあります。
例えば、
-
ことばの教室
-
保育士による訪問相談
-
子育てサロン
-
親子教室
などを利用することで、子どもとの関わり方や成長の見守り方を学ぶことができます。
「発達障害かどうか」にこだわるのではなく、
「今、親子で過ごしやすくなる方法は何か?」という視点で動くことがとても大切です。
2歳の「寝ない」という悩みは、非常に多くの家庭が抱える共通のテーマです。
睡眠だけを見て「発達障害かも…」と不安になる必要はありません。
でも、気になることがあれば、早めに相談・確認することは決して無駄にはなりません。
「眠らないのは困るけれど、それ以上に大切なのは“この子らしさ”を見守ること」
― そう思えるような関わり方を、少しずつ探していけたら理想ですね。
歳がなかなか寝ない…0時まで起きている子どもの実例と親の声
「23時を過ぎても全く眠くならない」
「布団に入れてもベッドでジャンプ」
「ついに寝たのが0時…私が限界」
2歳の子どもがなかなか寝ず、夜0時を過ぎてやっと就寝するという悩みは、実は多くの家庭で共通しています。
この記事では、そんなリアルな声や実例をもとに、“我が家だけじゃない”という安心感と、そこから見える改善のヒントをお伝えします。
🗣️ケース①:23時半就寝が日常に
「保育園から帰ってくるのが18時。そこから夕飯、お風呂、絵本…で、寝室に行くのが21時。でもそこからが長い。全然寝なくて、最終的に寝るのが23時半…。親が疲れて寝落ちすることも。」
ポイント: 帰宅が遅いワーママ家庭では、夜の流れが押されてしまい、就寝時間が自然と後ろ倒しになる傾向があります。
🗣️ケース②:昼寝と夜寝が逆転気味
「昼寝が17時くらいから2時間くらい…。そのせいで、夜寝るのが0時近くになる。でも昼寝をカットすると夕方に機嫌が悪くなるので、調整が難しい。」
ポイント: 昼寝のタイミングや長さが、夜の睡眠に大きく影響する典型例。夕方の昼寝は要注意。
🗣️ケース③:寝かしつけてからの“謎の覚醒”
「20時半に寝たと思ったら、23時にパッチリ起きてきてそこから元気に遊びだす。親が先に眠くなるパターン…。部屋を暗くしても効果なし。」
ポイント: 入眠後すぐの覚醒(中途覚醒)は、昼間の刺激や興奮状態が残っている場合に起こりやすいです。
🗣️ケース④:自己嫌悪とイライラのループ
「夜中まで起きていると、こちらも疲れていてイライラ…。つい怒ってしまって、後から自己嫌悪。こんな毎日で、親として失格じゃないかと落ち込む。」
ポイント: 寝かしつけが長引くことで、親のメンタルにも深刻な影響が及ぶことがあるという現実的な悩み。
子育てメディアやSNS上のアンケート結果でも、
「2歳の就寝時間が23時以降になることがある」と答えた家庭は**約30〜40%**にも上ります。
たとえば:
-
20時台に寝る…約40%
-
21〜22時台…約30%
-
23時以降…約20〜30%
つまり、0時就寝のような“遅寝”は決してレアではないのです。
「うちだけじゃない」と知ることで、少し肩の力を抜いて対応できるようになるかもしれません。
X(旧Twitter)やInstagramでも、#寝ない子 #寝かしつけ地獄 といったハッシュタグには共感の声が多数。
「夜の寝かしつけは親子の戦い」
「布団に入ってから2時間…。心折れそう」
「毎晩寝室で深呼吸してる」
といった、笑えないけど笑ってしまう“あるある”投稿がたくさん見つかります。
自分だけがダメなわけじゃない、みんな悩んでる。
そう感じられるだけで、少し気持ちが軽くなるという声も多いです。
遅寝が習慣化している家庭のケースには、いくつかの共通点があります。
|
共通点 |
対応策のヒント |
|---|---|
|
昼寝が遅い or 長い |
昼寝を13〜15時の間に、時間も90分以内に調整 |
|
寝る前にスマホやテレビ |
寝る1時間前は画面をオフ。絵本や音楽に切り替える |
|
帰宅が遅い・生活が慌ただしい |
朝〜夜のルーティンをできるだけ固定化する |
|
親がイライラしている |
深呼吸・交代制・スキンシップなどで気持ちを整える |
すぐに変えられない事情があっても、“できることから1つずつ整える”ことが大切です。
確かに0時まで寝ない状況は、子どもの健康や親の心にも影響を与えます。
でも、それはあなたが「ちゃんと向き合っている証拠」でもあります。
「完璧じゃなくていい」
「昨日よりほんの少し早く寝られた、それでOK」
そんな気持ちで、まずは今日の寝かしつけを乗り越えていきましょう。
次の見出しでは、怒ってしまったり、放置してしまったときの親の心のケアと対処法について掘り下げていきます。

(画像引用:モグモ公式サイト)
共働きで毎日バタバタのわが家。夕飯作りはどうしても「時短」「手軽」重視になりがちで、栄養バランスに不安を感じていました。
そんなときに知ったのが【mogumo】。
管理栄養士監修・無添加で安心できる上、冷凍庫から出してレンジで温めるだけ。
最初は「子どもが食べてくれるかな?」と半信半疑でしたが、思った以上に完食してくれて驚きました。
野菜も入っていて栄養も取れるし、罪悪感もゼロ。
ママの“心のゆとり”を取り戻してくれるサービスだと思います。
>>mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ
寝ない子にイライラして怒ってしまう…どうすれば?
「もう早く寝てよ!」「なんでまた起きてくるの⁉」
寝ない2歳児に対して、つい強い口調になってしまったり、怒鳴ってしまったり…。
そして寝かしつけたあとに、自分を責めてしまう──そんな経験、ありませんか?
この記事を読んでくださっているあなたが感じているその「イライラ」と「自己嫌悪」は、決して一人だけのものではありません。ここでは、2歳児の寝かしつけで感じる親のストレスと、その向き合い方について掘り下げていきます。
まず大前提として、
寝ない子どもにイライラしてしまうのは「おかしいこと」ではなく、自然なことです。
人は疲れていたり、余裕がなかったり、同じことが何度も繰り返されたりすると、当然ストレスがたまります。
2歳児の寝かしつけはまさにその連続。
-
時間をかけても寝ない
-
寝室から何度も出てくる
-
寝かしつけ中にお茶・おむつ・抱っこ…の要求が止まらない
…こんな日々が続けば、感情が爆発してしまっても仕方がありません。
寝ない子に怒ってしまう背景には、次のような気持ちが隠れています。
-
「自分の時間がまったくない…」
-
「明日も仕事なのに、寝てくれないと困る」
-
「このままだと発達に悪影響があるのでは」
-
「育て方が間違ってるのかも…」
つまり、怒り=心の悲鳴。
怒ってしまった自分を責める前に、「それだけ一生懸命子育てしている」という証であることを思い出してほしいのです。
「寝てくれなくて、つい声を荒げてしまった…その直後に寝顔を見て号泣しました」
「優しく接したいのに、もう心に余裕がなさすぎて無理でした」
「怒鳴ってしまった翌朝、ぎゅっと抱きしめて謝るのが日課になってしまってます…」
──このような声が多数寄せられています。
「みんなも同じように悩んでる」と思うだけで、少しホッとするかもしれません。
怒りそうになったとき、もしくは怒ってしまったあとの「心の切り替え方」をいくつかご紹介します。
① 一度その場を離れて深呼吸
どうしても感情が爆発しそうなときは、一時退室して心を整えるのもアリ。5秒だけでも目を閉じて深呼吸するだけで、怒りのエネルギーをリセットできます。
② 交代する・頼る
ワンオペで寝かしつけている場合、パートナーと交代制にするのも効果的。「今日はママ、明日はパパ」と分担すれば負担も減ります。
③ 寝かしつけの時間を「ゆるくとらえる」
「21時までに寝かせなきゃ!」という思い込みが強すぎると、焦りが生まれます。“寝かせる”ではなく“眠る準備を一緒にする時間”と捉えるだけでも心に余裕が生まれます。
④ 感情を書き出してみる
怒りが続いてしまうときは、紙やスマホに思っていることを書き出してみるのもおすすめ。「こんなに頑張ってたんだな」と自分を客観視できるようになります。
⑤ 子どもが寝たあとに「自分をねぎらう時間」をつくる
お茶を飲む・ドラマを見る・アロマを焚くなど、自分の心を癒す時間を確保することで、明日へのエネルギーになります。
怒ったあとに「怖い思いをさせてしまったかも…」と後悔する方も多いはず。
でも、そんなときこそ「ごめんね」「ママも疲れちゃったの」と素直に伝えることが大切です。
子どもにとって「完璧な親」である必要はありません。
「怒っても、あとでちゃんと愛情を伝えてくれる」
という体験が、子どもの心の安定につながります。
2歳児の寝かしつけは、親の精神力が試される大仕事。
イライラしてしまう日があっても、怒ってしまった日があっても、
あなたは“子どもと向き合っている素晴らしい親”です。
完璧じゃなくていい。
できなかった日があっても、「また明日、優しく抱きしめよう」
そう思えれば、きっと大丈夫です。
放置してもいいの?泣かせておくのはアリ?
「もう限界…泣かせておいても大丈夫なのかな?」
「抱っこも拒否されるし、何をしても泣き止まない。放っておいてみたけど罪悪感…」
寝ない2歳児への対応で疲れ切って、「もういっそ放置してもいいのでは?」と思ってしまうこと、ありますよね。
この記事では、「放置する」ことの意味とリスク、そして“泣かせっぱなし”との違いについて、専門家の視点も交えながら解説していきます。
結論から言うと、
状況によっては“少し放っておく”のは必要な対応であり、必ずしも“悪いこと”ではありません。
親だって人間です。
どうしても耐えられない時や、感情的になりそうな時、無理に対応し続けるよりも、“あえて一度離れて心を整える”という選択は、むしろ健全な行動です。
ただし、「完全に無視する」「怒りのまま放置する」「声もかけない」など、子どもが“見捨てられた”と感じる関わり方は避ける必要があります。
よく混同されがちですが、
|
タイプ |
内容 |
子どもへの影響 |
|---|---|---|
|
❌泣かせっぱなし(無関心・無視) |
声もかけず、完全に放置し続ける |
愛着不安・不信感・情緒不安定の原因になる |
|
⭕見守り型の放置(タイムアウト) |
子どもから少し距離をとり、落ち着いたら寄り添う |
子どもも親もクールダウンできる、信頼は維持 |
「泣かせてしまった」と罪悪感を抱くよりも、
“どう対応したか”“その後どう寄り添えたか”が大切なのです。
育児書や専門家のアドバイスでも、「一時的な見守り=タイムアウト」は有効な方法とされています。
アメリカ小児科学会(AAP)でも、2歳前後の子どもへの対応として、
-
感情が爆発してどうしようもないときは「クールダウンタイム」を
-
落ち着いたあとに「受け入れと説明」を
と提案しています。
特に、2歳児はまだ自分の感情をうまく言葉で伝えられず、泣く・叫ぶ・拒否するという形で表現します。
その嵐のような感情に巻き込まれ続けると、親自身が消耗してしまうのです。
では、罪悪感なく“安全な見守り”をするには、どうすれば良いのでしょうか?以下にいくつかのポイントを紹介します。
①「ママ(パパ)はここにいるよ」と伝える
完全に無視するのではなく、「近くにいるよ」「落ち着いたらおいでね」と声をかけるだけでも、子どもは安心します。
② 距離をとる=逃げるではない
同じ部屋にいても、あえて目線をそらしたり、壁のほうを向くだけでも、感情の切り替えが可能になります。
③ 放っておいたあと、しっかり抱きしめる
子どもが泣き疲れたり、落ち着いてきたら、ぎゅっと抱きしめて「寂しかったね」と言葉で受け止めることで、関係はむしろ深まります。
「毎晩抱っこしても寝ず、泣き叫ばれて限界に…。勇気を出して一度、静かに見守る方法に切り替えたら、数日で少しずつ落ち着きました」
「“泣かせてはいけない”と自分を追い込んでいました。でも、自分が壊れそうだった。離れて深呼吸しただけで、イライラが落ち着きました」
──こうした声からも、「親が無理しすぎないこと」が子どもとの信頼関係を守るカギだとわかります。
子どもが泣いてしまうのは、「怖い」「不安」「悔しい」「悲しい」など、言葉にできない気持ちを表す手段です。
その涙をすべて受け止めなきゃいけない──という思いが、親を苦しめてしまうこともあります。
でも本当は、
「泣いてもいい」「泣いても愛されている」と伝えることのほうが、ずっと大事なんです。
「もう限界…」そう感じたときに、少し距離を取って見守ることは、愛情の放棄ではありません。
むしろ、感情が爆発する前に一歩引ける親の姿勢こそ、子どもにとって安心の土台になります。
泣かせてしまった日があっても、抱きしめ直せば、何度でもやり直せます。
今日からできる!2歳児の寝かしつけのコツ7選
「寝かしつけが毎日の大仕事になっている…」
「どうしてこんなに時間がかかるの?」
そんなお悩みを抱えるママ・パパのために、今日から取り入れられる実践的な寝かしつけのコツ7つをお届けします。
ポイントは、“早く寝かせよう”ではなく、“眠りやすい環境と流れを整える”こと。
完璧じゃなくても大丈夫。できることから1つずつ試していきましょう!
子どもにとっては、「いつも通り」が安心のサイン。
寝る前の行動を“決まった順番”にすることで、自然と体が“眠る準備”を始めます。
たとえばこんな流れ:
夕食 → お風呂 → 歯磨き → トイレ → 絵本 → おやすみ
📝ポイント:
寝る時間を固定するよりも、「この順番が来たら寝るんだ」と覚えてもらうことが重要です。
寝室の照明は、できるだけ暖色系の間接照明に切り替えると、眠りやすくなります。
強い白い光(蛍光灯など)は脳を覚醒させるため、入眠を妨げてしまいます。
📝おすすめアイテム:
-
足元ライトや調光ランプ
-
フットライト
-
やさしいナイトライト(星空タイプや動物型が人気)
スマホやタブレット、テレビの光には「ブルーライト」が含まれており、メラトニン(眠りのホルモン)分泌を妨げると言われています。
📝実践法:
-
絵本に切り替える
-
音楽(オルゴール)や読み聞かせアプリの音声だけを使う
-
画面の代わりに影絵や紙芝居もおすすめ
毎晩の“これをしたら寝る”という「おやすみスイッチ」を取り入れると、子どもが自然と眠るモードに切り替えやすくなります。
例えば:
-
特定のぬいぐるみを渡す
-
「おやすみなさい」と部屋の電気を消す合図
-
一緒に「おやすみの歌」を歌う
📝ポイント:
どんな形でもいいので“いつも同じ”を大切に。それが安心感につながります。
2歳はまだ“ひとりで眠る”ことが不安な時期。
手をつなぐ・背中をさする・頭をなでるなどのスキンシップを取り入れることで、安心して眠りにつきやすくなります。
📝よくある工夫:
-
「トントン」で一定のリズムを刻む
-
指先だけ握って“手はつながってるよ”と伝える
-
寝息に合わせてママも呼吸をゆっくりにする
子どもは親のテンポ・声のトーン・呼吸に非常に敏感です。
寝かしつけの時間は、意識的にゆっくりしゃべり、ゆっくり動くことで、子どもの緊張を解いていく効果があります。
「さぁ、ねんねしようか〜…」
「今日はいっぱい遊んだねぇ〜…」
📝ポイント:
“寝なさい!”より、“気持ちいいな…”という空気作りを。
どうしても寝ない・イライラしてしまうときは、一度寝室から出てリセットするのも有効です。
-
トイレに行く
-
水を一杯飲む
-
隣の部屋で深呼吸する
数分離れたあとに、落ち着いて再び関わるだけで、親も子も気持ちが切り替わります。
子どもの性格や気質によって、効果的な方法は異なります。
|
タイプ |
向いている方法 |
|---|---|
|
さびしがり屋タイプ |
スキンシップ、絵本、添い寝 |
|
活発・多動タイプ |
寝る前の光や刺激の遮断、静かな音楽 |
|
こだわりタイプ |
入眠儀式(毎晩同じ順番)、お気に入りグッズ活用 |
📝ポイント:
1つずつ試しながら、「うちの子に合うスタイル」を見つけていきましょう。
2歳の寝かしつけは、手間も時間もかかるものです。
でも、日々の小さな積み重ねが“眠る力”を育て、やがてひとりで眠れるようになる第一歩になります。
「寝ない」ではなく、
「まだ眠る準備が整っていないだけ」
そう考えると、少し気持ちがラクになりませんか?
よくあるQ&Aまとめ(よくある不安・疑問)
2歳の寝かしつけに関する悩みは、家庭によってさまざま。
ここでは、実際によく寄せられる不安や疑問をQ&A形式でわかりやすく解説していきます。
「うちも同じことで悩んでた!」という声が多い内容ばかりですので、ぜひご覧ください。
A. 理想の就寝時間は20〜21時ですが、23時就寝が続いても焦らなくて大丈夫です。
ただし、慢性的に睡眠時間が足りていない場合(夜8時間以下など)は、発達や情緒面に影響が出る可能性があります。
「早く寝かせる」のではなく、「眠りやすい環境に整える」ことから始めてみましょう。
A. 単に寝ないだけでは発達障害とは判断できません。
確かに、発達障害のある子に睡眠リズムの乱れが見られるケースもありますが、2歳前後は生活習慣・性格・日中の刺激によっても眠りにくくなる時期です。
心配な場合は、保健師や小児科医に相談してみるのが安心です。
A. 睡眠時間(約11時間)が確保できていれば、基本的には問題ありません。
ただし、今後保育園・幼稚園への入園や、家族の生活サイクルとのズレが課題になる場合もあります。
できれば少しずつ就寝・起床時間を前倒しする習慣づくりを意識していきましょう。
A. それだけ真剣に向き合っている証拠です。自分を責めすぎないでください。
多くの親が「寝かしつけで感情が爆発してしまった」経験を持っています。
大切なのは、そのあとに「怖かったね」「ごめんね」ときちんと寄り添い直すこと。
完璧な親になる必要はありません。「また明日やり直そう」で大丈夫です。
A. 必ずしも悪いことではありません。“安心できる見守り”が大切です。
「もう無理…」と感じたときに、安全を確保したうえで少し距離をとることは、子どもにとっても親にとっても必要な時間です。
ただし、完全に無視したり怒りのまま放置するのではなく、落ち着いたら声かけやスキンシップで安心を与えることを忘れずに。
A. 昼寝を減らすと夜早く寝るケースもありますが、夕方以降にぐずる可能性も。
2歳児はまだ昼寝が必要な時期です。
昼寝の時間帯(13〜15時)や長さ(1時間程度)を調整することで、夜の寝つきが改善することがよくあります。
完全になくす前に、調整する方法を試してみましょう。
A. 遊びすぎ・興奮状態・脳が疲れすぎている可能性があります。
2歳児は興奮すると逆に眠れなくなることがあります。
日中に強い刺激(おでかけ・人混み・動画など)が多い日は、脳が休まらず、「疲れているのに寝られない」状態になることも。
→ 寝る前の静かな時間(照明・音・声・スキンシップ)を意識しましょう。
A. 1時間以上かかる家庭はとても多いです。
特に、イヤイヤ期まっさかりの2歳は、“まだ寝たくない”という意志表示が強く出る時期。
入眠までの時間をストレスに感じすぎず、“一緒に過ごすリラックスタイム”と捉えると少しラクになるかもしれません。
A. よくあることですし、悪いことではありません!
ママ・パパが寝たあと、子どもが自然と眠るパターンも多いです。
むしろ、親が落ち着いた呼吸や姿勢で横にいることで、安心感を伝える効果もあります。
A. 個人差がありますが、3歳ごろから少しずつ“ひとり寝”への移行が始まります。
最初は「先にママが出て行っても泣かなくなった」「お気に入りのぬいぐるみで寝られるようになった」など、小さな変化から始まります。
今はまだ「安心をチャージする時期」。ひとりで眠れる力は、ゆっくりでも確実に育っています。
寝かしつけの悩みは、どれも一朝一夕には解決できないものばかり。
でも、「不安に思うことは、自分だけじゃない」と気づくことで、気持ちがふっと軽くなることもあります。
子どもと一緒に、少しずつ進んでいきましょう。
大切なのは完璧よりも、毎日の積み重ね
2歳の寝かしつけは、親にとって毎晩が“挑戦”の連続です。
理想は20時台の就寝と分かっていても、実際は「23時を過ぎても寝ない」「0時まで泣かれて放置してしまった」なんて日もある。
自分の時間は取れず、イライラして怒ってしまい、あとで自己嫌悪…。
そんなママ・パパの心の葛藤を、この記事ではたっぷりと共有してきました。
でも、ひとつ覚えておいてほしいのは、
「うまくいかない日があっても、子どもはちゃんと愛されていると感じている」
ということです。
23時就寝でも、0時就寝でも、
それは「親が手を抜いたから」ではなく、「毎日一生懸命やっている中での結果」です。
誰だって理想通りにいかない日があります。
でも、安心できる環境・関係性・リズムを少しずつ整えていけば、子どもはちゃんと“眠れる力”を身につけていきます。
寝る前の絵本、スキンシップ、ママやパパの声、
そのすべてが子どもにとっては「安心のスイッチ」です。
うまくいかなくても、怒ってしまっても、最終的にぎゅっと抱きしめて「おやすみ」と言えるなら、
それは子どもにとって一番の幸せな記憶になります。
「完璧な寝かしつけ」は必要ありません。
むしろ大切なのは、
-
スマホの代わりに5分だけ絵本を読む
-
寝る前に部屋の照明を落とす
-
子どもと一緒に深呼吸してみる
-
イライラしたらいったん離れて戻る
といった、“ほんの小さな積み重ね”です。
昨日よりちょっと落ち着いて過ごせた。
先週より少し早く寝られた。
それだけで、親も子も十分に成長しています。

(画像引用:モグモ公式サイト)
「今日のごはん、どうしよう…」
仕事から帰ってきて、保育園から子どもを迎えて、買い物して、夕飯を作って…毎日そんな繰り返しに疲れていませんか?
そんな忙しいママにおすすめなのが、幼児食宅配サービス mogumo(モグモ)。
1歳半〜6歳の子ども向けに、管理栄養士が考えた無添加・冷凍のおかずをお届けしてくれるんです。
✔ レンジでチンするだけ、調理はほぼゼロ!
✔ 栄養バランスもバッチリで偏食対策にも◎
✔ 忙しい夕食時に“あと1品”としても使える
「子どもがパクパク食べてくれる」だけで、ママの心もぐっと軽くなりますよ。
毎日の食事作りを少しラクにして、子どもと笑顔で過ごす時間を増やしてみませんか?
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ をタップ
をタップ




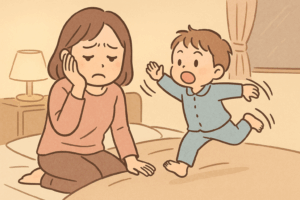
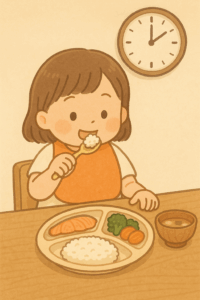




コメント