赤ちゃんの成長を願って、一生懸命お世話をしているママやパパ。
でも混合育児をしていると、「ミルクを足しすぎてないかな?」「母乳とミルクのバランスってどうしたらいいの?」と不安になること、ありますよね。
特に母乳量が安定していない時期や、赤ちゃんが泣き止まない時など、「とりあえずミルクをあげておこう」と思ってしまうことも。
でもそのたびに「これって飲ませすぎ?」とモヤモヤしてしまう…。
そんな混合育児中のママたちが気をつけたいポイントや、安心できる目安について、わかりやすくご紹介します。
【総額7,660円OFFクーポン】【特典付き】
初回限定キャンペーンでお得にGETできる!
(画像引用:モグモ公式サイト)
「子どもが小さいうちは、仕事も家事も育児も全部フル回転。気づけば自分の時間はゼロ…」
「健康的なご飯を準備してあげたいけど、うまく時間を作れない…」
そんなママの一番の悩みは“毎日のごはん作り”ではないでしょうか。そんな時におすすめなのが『モグモ』です。
モグモは1歳半〜6歳向けの幼児食宅配サービスで、無添加で栄養バランスに優れた冷凍ごはんが届くため、冷凍庫にストックしておけばいつでも使えるので安心です。
- 保育園帰りで子どもが「お腹すいた!」と言っても、レンジで数分チンするだけ
- 献立に悩む時間がなくなる
- 子どもが食べやすい味付け・サイズだから、食べムラが減る
「今日は疲れてごはんを作りたくない…」「子供にも栄養バランスが整った食事を摂らせたい」そんなときに助けてくれるんです。
家族の食卓を無理なく支えながら、ママに“心のゆとり”を取り戻してくれるはずです。今なら全額返金保証付きで安心して試せるので、気軽に始めてみてくださいね!
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ![]()
混合育児でミルクのあげすぎが心配!体重の増え方を確認してチェック
赤ちゃんの「お腹すいたよ」のサインを見逃さないように気を配っていても、混合育児では「本当に足りてるのかな?」という不安がつきもの。
母乳がどのくらい出ているのか目に見えない分、ついつい「足りないかも…」と心配になって、ミルクを多めにあげてしまうこともありますよね。
けれど、ミルクのあげすぎには注意が必要です。
赤ちゃんの胃に負担をかけたり、体重の増えすぎにつながることもあるからです。
では、混合育児でミルクのあげすぎを防ぐには、どんな点に気をつければいいのでしょうか?
まず大切なのは、「赤ちゃんの飲み方や様子を観察すること」です。
たとえば、赤ちゃんが母乳を飲んだ後にまだ不機嫌だからといって、すぐにミルクを足すのではなく、まずは他の理由を探ってみましょう。
おむつが汚れていないか、眠いのにうまく寝付けないのではないか、抱っこしてほしいのかも…そんなサインを見逃さずに見てあげることで、必要以上にミルクを与えるのを防ぐことができます。
また、ミルクを足すタイミングや量に「目安」を持つことも大切です。
母乳のあとに毎回フル量のミルクをあげていると、どうしても過剰になりがち。
たとえば、生後1〜2ヶ月頃であれば、母乳をしっかり飲んだ後ならミルクは40〜80ml程度からスタートして、赤ちゃんの満足度に応じて加減するなど、柔軟な対応をしていくと良いでしょう。
赤ちゃんが飲んでいる途中でウトウトしはじめたり、哺乳瓶を口から離すようなら、満腹のサインかもしれません。
無理に飲ませずに、赤ちゃんのペースを尊重しましょう。
それから、体重の増え方も一つの判断材料になります。
赤ちゃんの健診時に「成長曲線の範囲内に入っているか」をチェックし、急激な体重増加が見られるようであれば、ミルクの量を見直す必要があるかもしれません。
必要であれば、小児科や助産師さんに相談するのも安心です。
プロの視点でアドバイスをもらえると、過度な心配をせずに育児ができます。
さらに、混合育児では「ミルクを足す=悪いこと」ではないという視点も大切です。
大事なのは、赤ちゃんが心地よく成長しているかどうか。
そしてママが心身ともに無理をしていないか、という点です。
「母乳が足りてないかも」とプレッシャーを感じるたびにミルクを足し、その結果「飲ませすぎてしまったかも」と自己嫌悪に陥る…そんな悪循環にならないように、自分の気持ちにも優しくしてあげてください。
混合育児は「ちょうどよいバランス」を見つけるのが難しいもの。
でも、赤ちゃんの様子をよく見て、少しずつミルクの量やタイミングを調整していけば、きっとあなたと赤ちゃんに合ったペースが見つかります。
育児に正解はありません。
「今日は飲ませすぎちゃったかな」と感じた日があっても、それはママが赤ちゃんのことを一生懸命考えている証拠。
日々のトライ&エラーを重ねながら、自信を持って進んでいきましょう。
混合育児の場合、新生児のミルクの量はどれくらい?
新生児期の育児は、喜びと同時に不安の連続ですよね。
特に混合育児を選んだママにとって、「どれくらいミルクを足せばいいの?」「母乳の量は足りてるのかな?」と毎日のように悩むことも多いのではないでしょうか。
母乳とミルクの両方を使う混合育児は、赤ちゃんの栄養を確保しながら、ママの体や気持ちにも無理をさせすぎず、柔軟に対応できるメリットがあります。
ただし、母乳の量が目に見えないため、ミルクの量に迷いがち。
ここでは新生児期(生後0〜1ヶ月)の赤ちゃんにおける、混合育児でのミルク量の目安や注意点について詳しく紹介します。
まず基本的な目安として、新生児が1日に必要とするミルクの量は、体重1kgあたり約120〜150mlとされています。
たとえば体重3kgの赤ちゃんであれば、1日に必要な量は360〜450ml程度。
ただしこれは、母乳+ミルクの合計量です。
混合育児の場合は、母乳をあげた後に赤ちゃんが満足していない様子(泣き止まない、口をパクパクするなど)が見られる時に、必要に応じてミルクを足すという方法が一般的です。
たとえば…
-
母乳後に赤ちゃんがまだ欲しそうなら、20〜40ml程度からミルクを足す
-
1回量としては最大でも60ml前後までにして、赤ちゃんの様子を見ながら調整
-
授乳間隔は基本的に2〜3時間おき、1日8回前後
というのがひとつの目安になります。
「足りないかも…」と心配して、毎回フル量のミルクを足してしまうと、飲ませすぎになってしまうこともあります。
飲ませすぎは赤ちゃんの胃腸に負担をかけ、吐き戻しや体重の増加ペースが早くなりすぎる原因になることも。
だからこそ、ミルクを足す時は「必要に応じて、少しずつ」が鉄則。
母乳を飲んだ後に赤ちゃんが満足していそうなら、あえてミルクは足さなくてもOKです。
ママ自身が「母乳が出ていないかも…」と不安になっても、実際は赤ちゃんにとって十分足りていることもあります。
ミルク量の判断に迷ったときは、赤ちゃんの様子を見ることが何よりのヒントになります。たとえば…
-
飲み終わったあとに機嫌がいい
-
眠そうにしている
-
おっぱいや哺乳瓶を口から離す
-
1日6〜8回程度のおしっこが出ている
このような状態なら、ミルクを無理に足す必要はありません。
生後1週間〜1ヶ月までの間でも、赤ちゃんは日々成長します。たとえば…
-
生後1週間:ミルクは1回量40〜60mlが目安
-
生後2〜3週間:母乳が安定してくる時期。ミルクの量を減らしていくママも
-
生後1ヶ月:赤ちゃんの胃も少しずつ大きくなり、1回量は60〜100mlになることも
このように時期によって調整が必要ですし、「いつまでもこの量でOK」という決まりはありません。
どうしても不安が拭えないときは、産院の助産師さんや地域の保健師、小児科の先生に相談しましょう。
「赤ちゃんの体重の増え方が気になる」「夜中に何回も授乳してしまってつらい」といったことも、専門家に相談することでぐっと安心できるはずです。
混合育児での新生児のミルクの量は、「母乳+ミルクのバランスを、赤ちゃんの様子に合わせて柔軟に」が大切。
最初は手探りでも、毎日の中で少しずつ「うちの子のちょうどいい量」が見えてきます。
赤ちゃんとママにとって心地よい育児ペースを見つけていけるよう、焦らず、自信を持って進んでいきましょう。
混合育児の場合、生後1ヶ月の母乳とミルクの量は?
「母乳だけで足りているのかな?」「ミルクをどれくらい足せばいいんだろう…」
混合育児をしていると、生後1ヶ月を迎えても不安が尽きませんよね。
母乳は赤ちゃんにとって最良の栄養とわかっていても、量が目に見えないからこそ「本当に足りているのか」がわからず、ついミルクを多めにしてしまう…そんな経験は、混合育児中のママの多くが感じていることです。
では、生後1ヶ月の赤ちゃんにとって適切な母乳とミルクの量とはどれくらいなのでしょうか?
ポイントは、“赤ちゃんのペース”と“ママの体の状態”の両方を大切にすることです。
生後1ヶ月になると、赤ちゃんの吸う力が少しずつ強くなり、授乳のリズムも安定しはじめる時期です。
母乳は消化が良いため、2~3時間おきに欲しがるのは自然なこと。
1日8〜12回の頻回授乳でも問題ありません。
むしろ、この時期の頻回授乳は母乳量の安定にもつながるので、赤ちゃんが欲しがるサインを見逃さずに対応することが大切です。
赤ちゃんが飲み終わったあとに満足そうにしていたり、1日6〜8回以上のおしっこが出ているようなら、母乳はしっかり足りていると考えてOKです。
混合育児では、母乳のあとに足りなさそうなときだけミルクを足すスタイルが基本です。
生後1ヶ月頃の赤ちゃんにミルクを足す場合、1回の量は40〜80ml程度が目安です。
ただしこれは“最大量”ではなく、赤ちゃんがどのくらい母乳を飲んでいるかによって調整する必要があります。
たとえば…
-
母乳をしっかり吸っていそう:ミルクは20〜40ml程度
-
母乳の分泌が少なめ、赤ちゃんの飲みが浅い:60〜80ml程度まで
というように、赤ちゃんの満足度やママの母乳分泌量によって柔軟に対応することがポイントです。
この時期の赤ちゃんは、1日あたり母乳+ミルクの合計で約600〜800ml程度の栄養を摂取します。
授乳の間隔は2〜3時間おきで、1日7〜8回程度が一般的です。
ミルクだけで育てている場合は、1回あたり100ml前後与えることもありますが、混合育児では母乳の量を含めてトータルで考える必要があります。
「泣いている=お腹がすいている」と思いがちですが、実は眠たい・暑い・寂しいなど、赤ちゃんにはさまざまな理由で泣くことがあります。
母乳を飲んだあとでも泣き止まないからといって、すぐにミルクを足すのではなく、抱っこやおむつ替えなどで様子を見てから判断することも大切です。
また、赤ちゃんが哺乳瓶を押しのける、飲んでいる途中で寝てしまう、吐き戻しが多いなどのサインがあれば、それは飲みすぎのサインかもしれません。
無理に飲ませるのではなく、赤ちゃんの満足度を観察しながら調整しましょう。
混合育児のスタイルは家庭ごとにさまざまです。たとえば…
-
日中は母乳中心、夜はミルクをしっかり足してママの休息時間を確保する
-
搾乳した母乳を哺乳瓶で与えることで量の目安を把握する
-
母乳が軌道に乗ってきたら、ミルクを徐々に減らしていく
など、試行錯誤しながら「わが家のやり方」を見つけていくことが、混合育児をうまく続けるコツです。
生後1ヶ月の赤ちゃんにおける混合育児では、「母乳+ミルクのバランスを、赤ちゃんの様子を見ながら柔軟に」が大原則。
母乳を優先しつつ、不足を感じたときにミルクを少し足すスタイルが基本です。
最初から完璧にできるママなんていません。
赤ちゃんの体重の増え方や機嫌、おしっこの回数などをチェックしながら、あなたと赤ちゃんにとって最適な育児スタイルを少しずつ見つけていきましょう。
【関連記事】生後2ヶ月のミルクの量は?完ミの場合は?
【関連記事】生後3ヶ月のミルクの量は?完ミの場合は?
母乳と混合ミルクの割合はどれがいい?
赤ちゃんを育てる中で、「母乳とミルクのバランスってどうすればいいの?」という悩みは、混合育児をしている多くのママが直面する壁です。
最初は「母乳が少ないからミルクも使おう」と始めた混合育児。
けれど、いつの間にか「ミルクをあげすぎてる?」「母乳が減っちゃってる?」とバランスに迷うことが増えていきます。
では実際、母乳とミルクの割合はどれが正解なのでしょうか?
まず最初に知っておいてほしいのは、「この割合がベスト」という絶対的な正解はないということです。
なぜなら、ママの母乳の出方、赤ちゃんの飲み具合、家庭の生活リズム、ママの体調や気持ち…それぞれの条件が違うからです。
大切なのは、「赤ちゃんが満足して元気に育ち、ママも無理せず続けられること」。そのために、母乳とミルクの割合は家庭ごとのオーダーメイドでOKなのです。
① 母乳メイン+補助的にミルク
このスタイルは「できるだけ母乳をあげたい」と考えるママに多く、母乳を飲ませたあと、赤ちゃんが足りなさそうなときにだけミルクを足す方法。赤ちゃんの飲み具合に応じてミルクの量が変わるので、柔軟に対応できるのが特徴です。
② 母乳とミルクを半々で交互に
1日の授乳のうち、例えば「昼は母乳、夜はミルク」というように、時間帯によって分けるケースです。ミルクで夜の睡眠時間を少し確保することができるため、ママの体を休めるのにも役立ちます。
③ ミルクメイン+気分で母乳
「母乳はあまり出ないけど、吸わせることでスキンシップをしたい」というママに多いスタイル。基本はミルクで栄養をまかない、気が向いた時に母乳を吸わせて、赤ちゃんとの触れ合いの時間を楽しみます。
どのスタイルも間違いではありません。大切なのは、ママ自身が安心して続けられるかどうかです。
では、今の自分のやり方がちょうどいいのか?見直したい時にチェックしておきたいポイントを紹介します。
-
赤ちゃんの体重が順調に増えているか
-
1日のおしっこの回数が6回以上あるか
-
授乳後に赤ちゃんが満足している様子か
-
ミルクをあげたあとに吐き戻しが多くないか
-
ママの疲労感が強すぎないか
これらを見ながら、ミルクの量を増やしたり減らしたり、母乳の回数を増やしてみたりと、少しずつ調整していくのが理想です。
もし「もっと母乳を増やしたい」と考えている場合は、以下のポイントを意識してみてください。
-
赤ちゃんに頻繁に吸ってもらう(1日8回以上)
-
水分をしっかり摂る(母乳は水分からできています)
-
夜間授乳を取り入れる(特に深夜〜早朝は母乳分泌が促されやすい)
-
ママ自身がリラックスできる時間を確保する
母乳の分泌はホルモンの働きによるものなので、ストレスや疲労がたまっていると減ってしまうことも。
無理をせず、気持ちにゆとりを持てるように、家族の協力も大切にしていきましょう。
混合育児というと、どこか「完全母乳でも完全ミルクでもない中途半端」と感じてしまうママも少なくありません。
でも、実は混合こそ赤ちゃんとママの生活に合わせた“柔軟で賢い選択肢”なんです。
母乳にこだわりすぎてママが疲れてしまったり、反対にミルクばかりで自己嫌悪に陥ったり…そんな必要はありません。
混合育児は「赤ちゃんとママのどちらもが心地よく過ごせる育児法」。その日の体調や気分によって調整できるのが、最大の魅力です。
母乳とミルクの割合に“正解”はありません。
大切なのは、「赤ちゃんが元気に育ち、ママが無理なく育児を続けられること」。
あなたと赤ちゃんだけの、心地よいバランスを少しずつ見つけていきましょう。
混合育児は、自由で柔軟。
だからこそ、不安な日があっても大丈夫。あなたは今、ちゃんと赤ちゃんを思って頑張っていますよ。
新生児の混合ミルクで3時間持たない。原因は?
「授乳から1時間半〜2時間しか経ってないのに、もう泣き出した…」
「ミルクも母乳もあげたのに、また欲しがってる?」
混合育児中の新生児期、とにかく“授乳の間隔が持たない”ことに悩んでいるママはとても多いです。
育児本やミルク缶の表示には「3時間おきが目安」と書かれているのに、現実はまるで違う…。
そんな違和感にモヤモヤしている方へ、「なぜ3時間持たないのか?」その原因と対処法を、わかりやすくお伝えします。
まず知っておきたいのは、新生児の胃はビー玉くらいの大きさしかないということ。
1回にたくさんの量を飲むことは難しく、すぐにお腹がすいてしまうのはごく自然なことなんです。
特に母乳は消化が早いため、ミルクを補っていても母乳の割合が多い場合は、授乳間隔が短くなりやすい傾向があります。
「まだ時間が空いてないのに泣いたからおかしい?」と焦る必要はありません。
赤ちゃんが泣くと「お腹がすいたのかな?」と思いがちですが、実は赤ちゃんが泣く理由はとても多様です。
たとえば…
-
おむつが濡れている
-
寒い/暑いなどの環境の不快感
-
寂しくて抱っこしてほしい
-
眠いのにうまく寝られない
-
なんとなく不安
このように、「空腹以外の理由」で泣いていることも多いのです。
毎回ミルクをあげていると、必要以上に飲ませてしまう=胃に負担がかかる・吐き戻しが多くなるなどの原因になってしまうこともあります。
生後2〜3週間ごろまでは、まだ母乳の分泌が安定していないママも多いです。
赤ちゃんの吸う力も弱くて効率が悪く、実際にはあまり母乳が飲めていないというケースもよくあります。
そのため、母乳を飲んだあとに赤ちゃんが泣く=飲み足りなかった可能性はあります。
この場合、母乳のあとにミルクを少量(20〜40ml)補うことで赤ちゃんが落ち着く場合もあります。
ただし、毎回たくさんの量を足すと母乳の分泌が減ってしまうこともあるため、様子を見ながら少しずつの量で調整していくのが大切です。
生後2〜3週間前後には「成長スパート(cluster feeding)」と呼ばれる時期があり、赤ちゃんが急に頻繁に授乳を求めるようになります。
この時期は、赤ちゃんの体が急成長している証拠で、「とにかく飲みたい!」モードになることがあります。
母乳の量を増やすためにもこの頻回授乳は大切で、一時的な現象です。
「なんで今日はこんなに飲むの!?」と思うことがあっても、数日で落ち着くことがほとんどです。
もしミルクを足していても3時間持たないようであれば、単純にミルク量が足りていない可能性もあります。
たとえば、母乳がほとんど出ておらず、ミルクの量も少なめの場合、赤ちゃんはすぐに空腹を感じます。
生後0〜1ヶ月の赤ちゃんであれば、ミルク量の目安は1回80〜100ml程度(母乳をほとんど飲んでいない場合)。
ただし、毎回しっかり母乳を飲んでいるなら、ミルクはその補助として20〜60ml程度から始めるのが一般的です。
赤ちゃんの体重増加や排尿回数を見ながら、適切な量を見直してみましょう。
新生児期の混合育児は、「時間通りにならない」「泣き止まない」ことが日常茶飯事。
でもそれは、赤ちゃんが元気に生きている証です。
「3時間空かない=ダメなこと」と思わなくて大丈夫。
赤ちゃんの個性、成長のタイミング、ママの体の状態…いろんな要素が重なってのこと。
少しずつ、赤ちゃんとのペースができてきます。
どうしても不安な場合は、助産師さんや小児科に相談してみてください。
専門家の一言が、気持ちをぐっと楽にしてくれるはずです。

(画像引用:モグモ公式サイト)
「今日のごはん、どうしよう…」
仕事から帰ってきて、保育園から子どもを迎えて、買い物して、夕飯を作って…毎日そんな繰り返しに疲れていませんか?
そんな忙しいママにおすすめなのが、幼児食宅配サービス mogumo(モグモ)。
1歳半〜6歳の子ども向けに、管理栄養士が考えた無添加・冷凍のおかずをお届けしてくれるんです。
✔ レンジでチンするだけ、調理はほぼゼロ!
✔ 栄養バランスもバッチリで偏食対策にも◎
✔ 忙しい夕食時に“あと1品”としても使える
「子どもがパクパク食べてくれる」だけで、ママの心もぐっと軽くなりますよ。
毎日の食事作りを少しラクにして、子どもと笑顔で過ごす時間を増やしてみませんか?
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ をタップ
をタップ






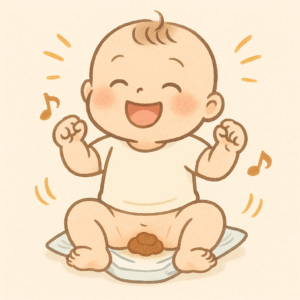



コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 混合育児でミルクのあげすぎが心配!どこを気をつければいい? […]