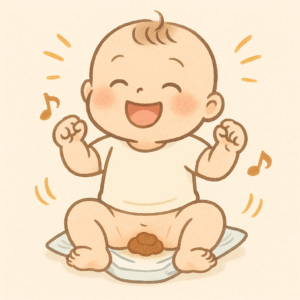「母乳だけで寝ちゃったけど、本当に足りてるのかな…?」
混合育児をしていると、母乳のあとに赤ちゃんがスヤスヤ眠ってしまうことがよくあります。
ですがその姿にほっとする反面、「ミルクを足さなくても大丈夫?」「もしかして飲み足りてないのでは?」と不安になるママやパパも少なくありません。
さらに、母乳とミルクをうまく使い分けているつもりでも、「母乳の量が減ってきたかも」「ミルクを飲んでくれない」など、育児の中で次々と新たな悩みが出てきますよね。
この記事では、混合育児で「母乳だけで寝てしまう赤ちゃん」への対応を中心に、ミルクを足す目安、母乳量をキープする方法、夜だけミルクを取り入れるやり方まで、よくある疑問や不安に寄り添いながらわかりやすく解説します。
「自分のやり方で大丈夫かな…」と悩むすべてのママ・パパに、安心と自信を届けられる内容です。
【総額7,660円OFFクーポン】【特典付き】
初回限定キャンペーンでお得にGETできる!
(画像引用:モグモ公式サイト)
「子どもが小さいうちは、仕事も家事も育児も全部フル回転。気づけば自分の時間はゼロ…」
「健康的なご飯を準備してあげたいけど、うまく時間を作れない…」
そんなママの一番の悩みは“毎日のごはん作り”ではないでしょうか。そんな時におすすめなのが『モグモ』です。
モグモは1歳半〜6歳向けの幼児食宅配サービスで、無添加で栄養バランスに優れた冷凍ごはんが届くため、冷凍庫にストックしておけばいつでも使えるので安心です。
- 保育園帰りで子どもが「お腹すいた!」と言っても、レンジで数分チンするだけ
- 献立に悩む時間がなくなる
- 子どもが食べやすい味付け・サイズだから、食べムラが減る
「今日は疲れてごはんを作りたくない…」「子供にも栄養バランスが整った食事を摂らせたい」そんなときに助けてくれるんです。
家族の食卓を無理なく支えながら、ママに“心のゆとり”を取り戻してくれるはずです。今なら全額返金保証付きで安心して試せるので、気軽に始めてみてくださいね!
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ![]()
母乳だけで寝る赤ちゃん…本当に足りてる?見極めるポイント!
寝落ち=満腹とは限らない
赤ちゃんが母乳を飲んだあとにすぐ寝てしまうのは、安心している証拠でもあります。しかしそれが「満腹で満足して寝た」のか、「まだ飲みたかったけど体力がなくて寝た」のか、見分けるのは難しいところ。
特に新生児は吸う力が弱く、短時間で疲れてしまうことも。そのため、実際には十分な量を飲めていないケースもあります。母乳だけで寝てしまったからといって、毎回安心してよいとは限りません。
赤ちゃんが「母乳だけで足りているかどうか」は、以下のポイントを総合的に見て判断しましょう。
① 体重が順調に増えているか?
月齢に応じて、赤ちゃんの体重が少しずつ増えていれば、母乳が足りている可能性が高いです。1日25〜30g程度、1週間で150〜210g程度の増加が目安です。
② うんちやおしっこの量
おしっこは1日5〜6回以上出ていれば問題ありません。うんちが柔らかくて黄色〜黄緑色であれば、消化がうまくいっている証拠です。
逆に、おしっこの回数が極端に少ない・濃い色が続くときは、水分不足のサインかもしれません。
③ 授乳後の機嫌や睡眠の様子
授乳後にご機嫌で、しばらく落ち着いて眠れているようなら、母乳で満足している可能性があります。
逆に、寝てもすぐ起きて泣く、ぐずりが続くなどの場合は、もう少し飲みたいサインかも。
母乳だけで寝てしまっても、以下のようなサインがある場合は飲み足りていないことが考えられます。
-
授乳間隔が1時間以内など極端に短い
-
吸う時間が明らかに短い(5分以下など)
-
飲んだあとも口を動かしたり、おっぱいを探す仕草をする
-
体重が思うように増えない
こうした場合は、ミルクを少量足す、または次の授乳を早めるなどの対応が必要かもしれません。
ママの母乳が出ていて、赤ちゃんがそれをしっかり飲めていれば「母乳だけで寝てしまう=足りている」というケースももちろんあります。
混合育児では、毎回ミルクを足さなければいけないわけではなく、母乳量や赤ちゃんの飲む力に応じて柔軟に判断してOKです。
特に夜間は「母乳だけで寝てくれるならありがたい」というママも多く、赤ちゃんの体調や発達に問題がなければ、そのスタイルを続けても問題ありません。
母乳のあとにミルクを飲まない…これって普通?理由と対処法を紹介!
混合育児を始めたばかりのママやパパが戸惑いやすいのが、「母乳を飲んだあとにミルクを飲んでくれない」という赤ちゃんの行動です。
特に新生児期や生後1〜2ヶ月の赤ちゃんは、吸う力や飲むペースに個人差が大きく、「母乳→ミルク」が毎回うまくいくとは限りません。
ここでは、ミルクを飲まない理由とその対処法を解説します。
「母乳のあとにミルクを飲んでくれない…どうして?」と心配になるかもしれませんが、これはよくあるケースです。特に以下のような理由が考えられます。
1. お腹がいっぱいで飲めない
最もよくある理由が「母乳だけで満腹になっている」こと。母乳の出が良かったり、赤ちゃんがしっかり吸えていたりすると、ミルクを足す必要がないくらい満たされている可能性があります。
2. 母乳のあとに眠くなってしまう
母乳を飲んだことで満足し、赤ちゃんがそのまま眠ってしまうケースも多いです。とくに新生児期は飲むだけで体力を使い切ってしまうので、飲み足りなくても寝てしまうことも。
3. 哺乳瓶に慣れていない・哺乳瓶拒否
「母乳は飲むのに、哺乳瓶だと拒否する」という赤ちゃんもいます。母乳と哺乳瓶の吸い方は感覚が違うため、慣れるまでに時間がかかる場合もあります。
結論から言うと、毎回ミルクを無理に足す必要はありません。
混合育児では「母乳+ミルク=完璧」ではなく、その時々の赤ちゃんの様子に応じて調整するのが正解です。
母乳だけで満足しているようなら、それを尊重して大丈夫です。
ただし、以下のような様子が見られる場合は注意が必要です。
-
授乳後すぐに泣く、ぐずる
-
授乳間隔が1〜2時間以内と極端に短い
-
おしっこやうんちの回数が少ない
-
体重があまり増えていない
これらが当てはまる場合は、ミルクを足す必要があるかもしれません。心配であれば、地域の助産師さんや小児科に相談してみましょう。
赤ちゃんが母乳のあとにミルクを飲んでくれないときは、無理に飲ませるのではなく、以下のような工夫を試してみましょう。
・哺乳瓶を変えてみる
乳首の形や硬さが合わないと赤ちゃんは嫌がることがあります。数種類試して、飲みやすいものを見つけましょう。
・ミルクを少量にして様子を見る
最初からフルの量を用意するのではなく、20〜30ml程度からスタートして、飲むかどうか確認するのもひとつの方法です。
・時間を少し空けてみる
母乳のあとすぐではなく、30分〜1時間ほどしてから再チャレンジすると、赤ちゃんの機嫌が変わって飲んでくれることも。
混合育児は、あくまで赤ちゃんとママのペースに合わせて調整していくスタイルです。
「母乳のあとにミルクを飲まない」こと自体が悪いわけではありません。
母乳だけで満足している日もあれば、たくさんミルクを欲しがる日もあります。
大切なのは「赤ちゃんの機嫌・体重・排泄の状態」をよく観察して、総合的に判断すること。焦らず、赤ちゃんと向き合いながら進めていきましょう。
ミルクと母乳を交互にあげていたら母乳量が減った?原因と対策について。
混合育児をしていると、「ミルクと母乳をバランスよくあげているつもりなのに、最近母乳の出が減ってきた気がする…」という悩みに直面する方が多くいます。
特に、ミルクと母乳を交互にあげるスタイルを続けていると、気がつけば母乳をあげる回数が減り、結果として母乳量そのものが減ってしまうことも。
ここでは、なぜミルクと交互に授乳すると母乳量が減りやすいのか?その原因と対策について詳しく解説します。
母乳の量は、赤ちゃんに吸われる回数や時間によって自然に調整されます。
つまり「よく吸われればよく出る」「吸われなければ減る」という、需要と供給の仕組みで成り立っているのです。
そのため、ミルクをあげる回数が増えたり、母乳を吸うタイミングが減ってしまうと、体が「もうそんなに母乳は必要ないんだな」と判断して、母乳の分泌量を減らしてしまいます。
交互にあげるというスタイルは、一見バランスよく思えるかもしれませんが、注意すべき点もあります。
【例】1日6回の授乳を想定した場合
-
交互にすると母乳が3回、ミルクが3回
-
結果的に、1日の授乳刺激が半分になる
-
体が「母乳は1日3回でいい」と判断 → 母乳量が減少
とくに新生児期〜生後2ヶ月ごろの時期は、母乳の生産がまだ安定していないこともあり、ちょっとした変化で母乳量に影響が出やすくなります。
母乳量をキープするには、ミルクとのバランスを工夫することが大切です。以下の方法を参考にしてみてください。
1. 母乳→ミルクの「順番」にこだわる
授乳のたびに、まずは母乳をしっかり吸ってもらうことを優先し、そのあとで足りない分だけミルクを補うようにします。これにより、母乳への刺激が確保され、分泌が促されます。
2. 母乳のあとに搾乳を取り入れる
赤ちゃんが吸ったあとでも5〜10分ほど軽く搾乳をすることで、「まだ必要なんだ」と体に信号を送ることができ、母乳の分泌量アップにつながります。
3. 夜間授乳を活かす
夜間は母乳ホルモン(プロラクチン)の分泌が活発になる時間帯です。夜間に1回でも母乳授乳を入れることで、日中よりも効率的に母乳量をキープしやすくなります。
4. 哺乳瓶を使う回数を見直す
母乳を吸ってもらう機会が減ってしまうと、乳首への刺激が少なくなり、母乳量が落ちる原因に。哺乳瓶と母乳のバランスを再確認してみましょう。
母乳が減ってきたかも?と思ったら、次のようなサインをチェックしましょう。
-
吸わせたあとの張りや刺激感が以前より少ない
-
搾乳しても以前より量が減った
-
赤ちゃんの体重増加がゆるやかになっている
-
授乳後にぐずることが多くなった
このような場合は、助産師さんや小児科医に相談するのも一つの方法です。
母乳量が一時的に減ったように感じても、刺激をしっかり与えれば再び増やすことは可能です。
大切なのは「焦らず、少しずつ自分たちのペースで調整すること」。
混合育児には、赤ちゃんとママにとっての柔軟さがある分、正解は一つではありません。
「ミルクと交互にあげているけど、母乳も続けたい」という想いがあるなら、その気持ちを大切にしながら、できる範囲で母乳への刺激を増やしていきましょう。
夜だけミルクにする方法とそのメリット・注意点
「夜だけミルクに切り替えたい」
「夜ぐっすり寝てほしい」
「日中は母乳を大切にしたい」
そんな想いから、「夜だけミルク」を取り入れるママ・パパが増えています。
混合育児の中でも比較的取り入れやすいスタイルですが、始める前に正しいやり方と注意点を知っておくことが大切です。
「夜だけミルク」とは、その名の通り夜間の授乳だけをミルクに切り替える方法です。
日中は母乳中心にしながら、夜の授乳タイミング(寝る前・深夜1回など)にミルクを使うことで、赤ちゃんの睡眠が深くなったり、ママの体力が温存できるというメリットがあります。
① 寝る前のタイミングでミルクを用意
お風呂→授乳→就寝という流れの中で、寝る直前の授乳をミルクに切り替えます。満腹感が得られるため、睡眠が長くなることも。
② 日中は母乳をメインに
昼間の授乳はこれまで通り母乳にすることで、母乳量の維持がしやすくなります。夜だけミルクにすることで母乳への影響を最小限にとどめます。
③ 夜中の授乳タイミングでもミルクを活用
夜中に1〜2回起きる赤ちゃんの場合は、深夜の授乳もミルクで対応すると、パパと交代しながら育児ができ、ママの負担軽減にもつながります。
1. 赤ちゃんが長く寝てくれることがある
ミルクは母乳よりも消化に時間がかかるため、満腹感が持続しやすく、結果的に睡眠時間が長くなることが多いです。夜間の頻回起きに悩むママには特におすすめの方法です。
2. ママの睡眠・体力回復につながる
母乳だけだと、夜間授乳が頻繁で睡眠不足になりがち。ミルクに切り替えることで、数時間まとまった睡眠がとれるようになるママも多くいます。
3. パパが授乳に参加できる
ミルクなら哺乳瓶で誰でも授乳できるため、夜間だけパパが担当という家庭も。育児の分担が進み、ママの心身の負担が軽くなるケースも多いです。
メリットの多い「夜だけミルク」ですが、以下の点には注意が必要です。
母乳量が減るリスクがある
夜間の授乳は母乳ホルモン(プロラクチン)分泌のピークです。
この時間帯に吸われないと、母乳が減る可能性があるため、日中の授乳や搾乳で刺激を補うことが大切です。
乳腺炎のリスク
母乳を飲ませる回数が減ることで、乳腺炎になりやすくなることも。夜間ミルクに切り替えた日は、軽く搾乳して張りを解消しておくと安心です。
授乳リズムが崩れることも
夜間ミルクに慣れすぎると、赤ちゃんが「おっぱいより哺乳瓶が好き」になってしまうことがあります。哺乳瓶の吸いやすさに慣れてしまい、母乳拒否につながることもあるため注意が必要です。
-
初めは週に2〜3回からスタートして、赤ちゃんの様子を見ながら調整
-
母乳量を維持したいときは、日中の授乳間隔を短めにする
-
ミルクの量は寝る前に120〜160ml程度から。赤ちゃんの飲み具合で調整OK
-
赤ちゃんの体重が順調に増えていれば、過度にミルク量にこだわらなくて大丈夫
夜だけミルクは、混合育児をしているママ・パパにとって、生活のリズムを整える大きな味方になります。
ただし、母乳量をキープしたい方は、日中の授乳や搾乳でしっかりカバーするのがポイントです。
「少しでも長く寝てほしい」「夜ぐらいは身体を休めたい」──その気持ちは、何よりも大切です。あなたと赤ちゃんにとって、無理のないペースで取り入れていきましょう。

(画像引用:モグモ公式サイト)
共働きで毎日バタバタのわが家。夕飯作りはどうしても「時短」「手軽」重視になりがちで、栄養バランスに不安を感じていました。
そんなときに知ったのが【mogumo】。
管理栄養士監修・無添加で安心できる上、冷凍庫から出してレンジで温めるだけ。
最初は「子どもが食べてくれるかな?」と半信半疑でしたが、思った以上に完食してくれて驚きました。
野菜も入っていて栄養も取れるし、罪悪感もゼロ。
ママの“心のゆとり”を取り戻してくれるサービスだと思います。
>>mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ
ミルクをあげすぎていないか心配なときは?4つのチェックポイント!
混合育児をしていると、「母乳で足りているか不安でついミルクを多めに…」「泣いたらとりあえずミルクをあげてしまう…」という場面、よくありますよね。
しかし、知らず知らずのうちにミルクをあげすぎてしまっていることも。
赤ちゃんにとって最適な量ってどれくらい?本当に足りていないの?と不安になるママ・パパも少なくありません。
ここでは、ミルクのあげすぎのサインや、適正量の見極め方について詳しく解説します。
「ミルクのあげすぎ」とは、赤ちゃんの消化・吸収能力を超えて与えてしまうことを指します。たとえ赤ちゃんが飲んだとしても、体に負担がかかっていたり、飲み過ぎて不快感を抱いていることもあります。
特に混合育児では「母乳の量がわかりにくい=不安だからつい多めに足す」という傾向があるため、ミルクの量に注意が必要です。
以下のような様子が見られる場合、ミルクをあげすぎている可能性があります。
1. 吐き戻しが頻繁
飲んだあとに大量に吐いてしまう、口からポタポタ垂れるようにミルクが出る場合は、胃に入りきらず戻しているサインです。
2. お腹が張って苦しそう
お腹がカチカチに張っていたり、ガスが溜まっていて機嫌が悪くなることがあります。これはミルクの消化に負担がかかっている可能性があります。
3. 急激な体重増加
1週間に300g以上増えている場合は、少しペースが早すぎるかもしれません。もちろん個人差はありますが、健診などで指摘されることもあります。
4. よく寝るけど、飲んだあとはぐったり
ミルクで満腹になると赤ちゃんはよく寝ますが、飲んだ直後に疲れたような表情や元気がないときは、飲み過ぎによる不快感がある場合も。
ミルクを足す量の目安は、母乳の出具合や赤ちゃんの飲みっぷりによっても異なりますが、以下はあくまで参考値です。
|
月齢 |
ミルクの目安量(1回あたり) |
授乳回数の目安 |
|---|---|---|
|
新生児(生後0〜1ヶ月) |
40〜80ml(母乳のあと) |
8〜10回/日 |
|
生後1〜2ヶ月 |
80〜120ml |
7〜8回/日 |
|
生後3〜4ヶ月 |
120〜160ml |
6〜7回/日 |
※この量は「母乳をあげたあとに足す場合」の量。母乳量が多ければ、さらに少なくてもOK。
① 授乳記録をつける
「母乳の時間」「ミルクの量」「飲んだ時間」を記録しておくと、全体のバランスが把握しやすくなります。育児アプリや手帳を活用すると便利です。
② 泣いた=ミルクとは限らない
赤ちゃんが泣く理由は空腹だけではありません。眠い・暑い・不安・おむつなど、さまざまな理由があります。すぐにミルクに頼らず、他の原因も探ってみましょう。
③ 飲みきらなくても無理にあげない
残したからといって無理に最後まで飲ませる必要はありません。赤ちゃんが自分で「もういらない」と判断しているサインです。
④ 医師や助産師に相談する
体重の増え方が気になる、授乳の仕方に不安があるという場合は、健診時や母乳外来などで専門家に相談しましょう。
「うちの子、飲みすぎてるかも…」と不安に思うことは、赤ちゃんを大切に思っている証拠です。ただし、心配しすぎるとママ・パパの気持ちが追い詰められてしまうことも。
赤ちゃんの体重や機嫌、排泄の状態を日々観察しながら、「よく飲んで、よく眠って、よく出している」なら、それがその子に合った量かもしれません。
混合育児において、ミルクの量に悩むのはごく自然なことです。
「飲ませすぎてないかな?」「足りてないかな?」と不安になったら、一度立ち止まって、赤ちゃんの様子をゆっくり見てみましょう。
ミルクは赤ちゃんの栄養を支える大切な存在ですが、量だけにとらわれず、赤ちゃんの反応を見ながら調整していくことが一番の近道です。
母乳寄りの混合育児の理想的なスケジュールを紹介!
「できるだけ母乳中心で育てたいけれど、足りない時だけミルクを足したい」
そんな思いから、母乳寄りの混合育児を選ぶママ・パパも多くいます。でも、「いつ、どのタイミングでミルクを足せばいいの?」「スケジュールが毎回バラバラで不安…」と感じている方も少なくありません。
ここでは、母乳寄りの混合育児におすすめの1日のスケジュールと、柔軟に調整するためのコツをお伝えします。
「母乳寄りの混合」とは、基本的に母乳をメインに与え、足りないときだけミルクを補う育児スタイルです。
完全母乳にこだわりすぎず、でもできるだけ母乳で育てたいというママにとって、心と体の負担を軽くしながら続けられるバランスの良い方法です。
以下はあくまで一例ですが、参考になるスケジュールです。
|
時間帯 |
授乳内容 |
|---|---|
|
6:00 |
母乳のみ(目覚めのタイミング) |
|
9:00 |
母乳のみ(しっかり吸わせる) |
|
12:00 |
母乳+ミルク(ミルクを40〜60ml足す) |
|
15:00 |
母乳のみ(抱っこやお昼寝前) |
|
18:00 |
母乳+ミルク(寝る前に足す) |
|
21:00 |
母乳のみ(就寝前) |
|
深夜2:00 |
母乳またはミルク(ママの体力や赤ちゃんの様子で調整) |
- 日中は母乳中心にして、お昼や夕方に1回だけミルクを足すスタイル
- 夜間は赤ちゃんの様子とママの体力に応じてミルクにするのもOK
新生児期(〜1ヶ月)
まだ母乳の分泌が安定していないため、1日2〜3回程度のミルク補足がおすすめ。しっかり吸ってもらうことが母乳を育てる第一歩です。
生後1〜2ヶ月
母乳が軌道に乗ってきたら、日中は母乳のみにして、夕方〜夜に1回だけミルクを足すなど、ミルクを減らしていけるように調整します。
生後3ヶ月以降
赤ちゃんの飲む力も強くなり、母乳量が安定していれば、ミルクは1日1回以下または不要になることも。
ただし、体重増加や機嫌を見ながら無理なく進めましょう。
① 固定しすぎず「赤ちゃん主導」で
赤ちゃんの成長や日ごとの体調によって、欲しがる量やタイミングは変わります。あくまでスケジュールは目安として、柔軟に対応することが大切です。
② 母乳の前に「スキンシップタイム」
母乳量を増やすためには、授乳前に赤ちゃんとのスキンシップや軽いマッサージを取り入れるのもおすすめ。リラックスすることで、吸いつきも良くなります。
③ ミルクの補足量は「最低限」に
「念のため」「泣いたから」と足しすぎると、母乳を飲む量が減り、結果的に母乳の分泌も減ってしまいます。体重や機嫌を見て、最小限で補うことを意識しましょう。
-
ママが体調不良・疲労困憊のとき
-
外出先での授乳が難しいとき
-
母乳の出が一時的に減っていると感じたとき
-
赤ちゃんが泣き止まず、お腹が空いているような様子のとき
母乳寄りの混合でも、ミルクに頼っていい場面はたくさんあります。
頑張りすぎず、赤ちゃんとママが笑顔で過ごせることを優先しましょう。
母乳寄りの混合育児では、「きっちりスケジュール通りにやること」よりも、赤ちゃんのサインに合わせて、母乳とミルクのバランスをその都度調整することが大切です。
母乳を大切にしながらも、必要なときはミルクに助けてもらってOK。無理のないリズムで、親子にとって最適なスタイルを見つけていきましょう。
ミルクの量がわからない!判断のコツと目安
混合育児をしていると、毎回つきまとうのが「ミルクってどれくらい足せばいいの?」という悩み。
母乳の量は目に見えない分、「足りてるの?」「足りないの?」という判断が難しく、ミルクの量にも迷いや不安がつきまといますよね。
ここでは、ミルクの量を見極めるための目安と判断のコツを、月齢別にわかりやすく紹介します。
混合育児の難しさは、母乳とミルクのバランスが不明確なことにあります。
母乳だけなら「吸わせるだけ」、ミルクだけなら「分量通り」で済みますが、混合になると「どのくらい飲めているのか」がわからないため、必要以上に足してしまったり、逆に足りなかったりしやすくなるのです。
|
月齢 |
ミルクの目安量(1回あたり) |
回数目安(1日) |
|---|---|---|
|
新生児(〜1ヶ月) |
20〜60ml |
母乳のあとに毎回少量ずつ |
|
生後1〜2ヶ月 |
40〜80ml |
1日2〜3回程度(母乳中心) |
|
生後3〜4ヶ月 |
60〜120ml |
必要時のみ(1〜2回) |
|
生後5〜6ヶ月 |
80〜150ml |
離乳食と併用しながら調整 |
※母乳の出具合や赤ちゃんの飲む力によって調整してください。
① 授乳後の赤ちゃんの様子を観察する
-
機嫌がよく、満足そうにしていれば足りているサイン
-
授乳後も泣く・口をパクパクする・哺乳瓶を探すような動きがあれば、追加が必要かも
② おしっこ・うんちの回数をチェック
-
おしっこは1日5〜6回以上が目安。量が少ない・色が濃いときは水分不足の可能性も
-
うんちの色が黄〜黄緑、回数が安定していれば消化できているサイン
③ 体重の増加スピードを記録する
-
1日あたり約25〜30g、1週間で150〜210gの増加があれば◎
-
増加がゆるやかで、機嫌も悪い・おしっこの回数が少ない場合は見直しが必要
「足りないかも」と思うとつい多めに作りたくなりますが、必要以上に足してしまうと母乳の飲む量が減り、結果的に母乳量が減ってしまうこともあります。
以下のような対策を意識してみましょう。
最初は少なめに用意する
様子を見ながら、飲み切ったら10〜20mlずつ追加。最初からフル量作る必要はありません。
母乳をしっかり吸わせてからミルクを足す
授乳の最初は必ず母乳→そのあとでミルクを足すのが基本。先にミルクを飲んでしまうと、母乳への興味が薄れやすくなります。
哺乳量や回数を記録して見える化する
育児日記アプリやノートを使って「母乳何分」「ミルク○ml」などを記録すると、自分なりのバランスや変化が見えてくるようになります。
-
「赤ちゃんが泣いた=足りてない」 → 泣く理由はお腹以外にもあります(眠い・暑い・寂しいなど)
-
「飲んだ量=安心材料」 → 飲みすぎても吐き戻したり、お腹が張ることも
-
「同じ月齢の子より少ない=心配」 → 赤ちゃんの体格・成長ペースには個人差があるので比べすぎないで
ミルクの量に正確な答えはありません。大切なのは、赤ちゃんの様子をよく見て、その子に合った育て方を見つけていくことです。
「今のこの子には、どのくらい必要かな?」
その気持ちを持って接していれば、少しずつ判断力も自信もついてきます。
完璧でなくて大丈夫。ミルクの量がわからなくて迷うあなたは、それだけ赤ちゃんを大切に思っている証です。
3時間もたない!混合育児での授乳間隔の悩み
「さっきミルクを飲んだばかりなのに、もう泣いてる…」
「3時間持たないって、飲ませすぎ?それとも足りない?」
混合育児では、「ミルクを足したのに授乳間隔が短い」と感じることがよくあります。特に新生児期〜生後2〜3ヶ月は赤ちゃんのリズムが安定しないため、授乳間隔に対して不安や疑問を持つママ・パパがとても多いのです。
よく耳にする「授乳は3時間おき」という言葉。これはあくまで平均的な目安であり、すべての赤ちゃんに当てはまるわけではありません。
実際には…
-
1〜2時間で泣いて授乳を求める子も普通
-
飲む量が少なかったり、眠りが浅いと、間隔が短くなる傾向あり
-
特に母乳寄りの混合育児では、母乳の消化が早いため間隔が短くなりやすい
赤ちゃんによっては、「3時間もたない」のがむしろ自然なこともあるのです。
① 飲み足りていない
母乳やミルクの量がその子にとって少ないと、満腹になれず短時間で空腹になります。
特に母乳はミルクより消化が早いため、母乳だけのときは2時間以内にまた泣くことも珍しくありません。
② 寝ながら飲んでいて満腹になっていない
「寝落ち授乳」で実は十分飲めていなかった…ということも。
短時間の授乳+ウトウト状態だと、胃が満たされていない可能性があります。
③ 泣く理由が空腹以外のことも
授乳後すぐに泣く=お腹がすいた、と決めつけがちですが、
-
抱っこしてほしい
-
オムツが不快
-
暑い・寒い
といった理由で泣いていることも。まずは落ち着いて赤ちゃんの様子を見ましょう。
様子を見て少量だけミルクを足す
明らかに空腹そうで泣き止まない場合は、10〜30ml程度の少量ミルクを足してみるのもOK。無理に3時間あけなくても、必要な時に必要な分だけ補えば大丈夫です。
授乳前のスキンシップ・目覚ましテクを活用
寝落ちしやすい赤ちゃんには、授乳前に肌のぬくもりを感じさせたり、頬を優しくさするなどの**「目覚まし刺激」**でしっかり起こしてから飲ませると、飲む量が増えて間隔も延びやすくなります。
昼間はこまめに授乳、夜はまとまって寝るリズムを意識
昼間は頻回でもOK。そのぶん夜にまとめて寝てくれるリズムがつくよう意識して、生活サイクルを整えるきっかけにしましょう。
3時間もたない=何かがおかしい…と思い込んでしまいがちですが、これは赤ちゃんが自分のリズムで生きている証でもあります。
とくに混合育児では、母乳とミルクのバランスが日によって変わるため、間隔がバラつくのはごく自然なこと。
ママ・パパが不安になると、赤ちゃんにもその気持ちは伝わってしまうもの。リラックスして、「今日のこの子のペース」に合わせていきましょう。
授乳間隔は3時間が理想…と思い込むと、赤ちゃんの個性を見失ってしまいがちです。
-
よく飲んで
-
よく出して
-
よく寝て
-
よく笑っている
この4つが揃っていれば、「3時間持たない」なんて心配はいりません。
赤ちゃんの個性を受け入れて、“型にはまらない育児”を楽しんでいきましょう。

(画像引用:モグモ公式サイト)
「今日のごはん、どうしよう…」
仕事から帰ってきて、保育園から子どもを迎えて、買い物して、夕飯を作って…毎日そんな繰り返しに疲れていませんか?
そんな忙しいママにおすすめなのが、幼児食宅配サービス mogumo(モグモ)。
1歳半〜6歳の子ども向けに、管理栄養士が考えた無添加・冷凍のおかずをお届けしてくれるんです。
✔ レンジでチンするだけ、調理はほぼゼロ!
✔ 栄養バランスもバッチリで偏食対策にも◎
✔ 忙しい夕食時に“あと1品”としても使える
「子どもがパクパク食べてくれる」だけで、ママの心もぐっと軽くなりますよ。
毎日の食事作りを少しラクにして、子どもと笑顔で過ごす時間を増やしてみませんか?
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ をタップ
をタップ