2歳の寝かしつけって、なんでこんなに大変なんだろう——。
布団に入れても動き回る、おしゃべりが止まらない、泣き叫ぶ、やっと落ち着いたかと思えばまた起き上がる…。
「もう寝てってば!」とつい怒ってしまい、自己嫌悪で涙が出る夜もあるのではないでしょうか。
2歳は、自我が育ち始め「まだ寝たくない!」という気持ちが強くなる時期。体力もついてきて、なかなか寝てくれない子も増えてきます。
でも、毎日続く寝かしつけのイライラや疲れに悩むのは、決してあなただけではありません。
この記事では、「2歳が寝ない・動き回る・泣く」といった寝かしつけのよくある悩みに寄り添いながら、
怒ってしまった時の心のケアや、“神アイテム”と呼ばれる寝かしつけグッズ、生活リズムの整え方まで詳しく解説します。
今日も寝かしつけがうまくいかなかった…そんな夜に、少しでもあなたの心が軽くなるヒントが見つかりますように。
【総額7,660円OFFクーポン】【特典付き】
初回限定キャンペーンでお得にGETできる!
(画像引用:モグモ公式サイト)
「子どもが小さいうちは、仕事も家事も育児も全部フル回転。気づけば自分の時間はゼロ…」
「健康的なご飯を準備してあげたいけど、うまく時間を作れない…」
そんなママの一番の悩みは“毎日のごはん作り”ではないでしょうか。そんな時におすすめなのが『モグモ』です。
モグモは1歳半〜6歳向けの幼児食宅配サービスで、無添加で栄養バランスに優れた冷凍ごはんが届くため、冷凍庫にストックしておけばいつでも使えるので安心です。
- 保育園帰りで子どもが「お腹すいた!」と言っても、レンジで数分チンするだけ
- 献立に悩む時間がなくなる
- 子どもが食べやすい味付け・サイズだから、食べムラが減る
「今日は疲れてごはんを作りたくない…」「子供にも栄養バランスが整った食事を摂らせたい」そんなときに助けてくれるんです。
家族の食卓を無理なく支えながら、ママに“心のゆとり”を取り戻してくれるはずです。今なら全額返金保証付きで安心して試せるので、気軽に始めてみてくださいね!
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ![]()
2歳の寝かしつけが大変な理由とは?それは自我の芽生え
「寝かしつけの時間が1時間以上かかる」「布団に入れても動き回って全然寝ない」
そんな2歳の寝かしつけに悩む声は、実はとても多いものです。
この時期の子どもが「なかなか寝ない」「寝かしつけに時間がかかる」のには、いくつかの理由があります。
2歳頃になると、子どもは“自分の意志”をしっかり持ち始めます。
大人が「そろそろ寝ようね」と声をかけても、子ども自身が「今は寝たくない!」と思えば、寝室に行くこと自体を拒否することも珍しくありません。
この「イヤイヤ期」の特徴的な行動が寝かしつけにも影響し、
「おもちゃで遊びたい」「もっとママといたい」「絵本を読んで」など、さまざまな要求が出てきます。
この時期の寝かしつけがスムーズにいかないのは、単なるわがままではなく、発達の一環とも言えるのです。
2歳頃になると日中の活動量がぐっと増え、体力もしっかりしてきます。
その分、以前よりも眠たくなるまでの時間が長くなり、寝る時間になってもまだエネルギーが残っていることもあります。
特に、昼寝の時間や長さによっては、夜なかなか寝つけずに布団の中でゴロゴロしたり、部屋の中を歩き回ったりするケースも少なくありません。
「2歳 寝ない 動き回る」という状況は、多くの家庭で見られる“あるある”なのです。
日中にテレビやタブレットを長時間見ていたり、外出先でたくさんの人や音に触れたりした日は、子どもの脳が興奮状態にあることがあります。
そういった日は、眠くても神経が高ぶってなかなか眠れない状態に。
大人でも、楽しいイベントがあった日はなかなか寝つけないことがありますよね。子どもも同じです。
就寝・起床の時間が毎日バラバラだったり、昼寝の時間が遅すぎたりすると、体内リズムが整わずに夜の寝つきが悪くなる傾向があります。
また、夕食の時間が遅すぎたり、就寝前にスマホやテレビを見せてしまったりすることも、睡眠に悪影響を与えます。
「2歳 寝かしつけ 時間 かかる」と感じている場合は、一度生活リズムを見直してみるのもおすすめです。
「早く寝かせなきゃ…」「明日も仕事なのに…」
そんな親の焦りやイライラは、実は敏感な2歳の子どもにしっかり伝わっています。
子どもは“安心”がないと眠りにつきにくいもの。
親がピリピリしていると、子どももどこか落ち着かず、寝かしつけが長引いてしまうこともあるのです。
2歳の子どもがなかなか寝ない、動き回る、寝かしつけに時間がかかる——それは“ダメなこと”でも“ママやパパのせい”でもありません。
むしろ、それは子どもの成長の一過程。
だからこそ、完璧に寝かしつけようと気負わずに、うまくいかない日も「そういう日もあるよね」と思える心の余裕を持てるといいですね。
2歳の子が「寝ない・動き回る」あるある行動集
2歳児の寝かしつけに苦戦しているママやパパにとって、「うちの子だけじゃないのかな?」という不安はよくあるもの。
でも安心してください。2歳の子どもが寝ない・動き回るのはとてもよくあることです。
ここでは多くのご家庭で見られる“あるある行動”を紹介します。
「もう寝る時間だよ」と言っても、布団の上で飛び跳ねたり、部屋の隅に行ってぬいぐるみを取りに行ったり…。
まるでエネルギーが有り余っているかのように部屋中を動き回る2歳児は珍しくありません。
親としては「なぜこのタイミングでそんなに元気?」とツッコミたくなる瞬間ですが、子どもにとっては遊びも睡眠の一部のようなもの。
しっかり動いて安心できる環境にならないと、寝るモードに入れないのかもしれません。
寝かしつけの時間になると急におしゃべりスイッチが入る子もいます。
「今日◯◯したの!」「ママ、◯◯って知ってる?」など、語彙が増えてきた2歳児ならではの“話しかけ攻撃”に、毎晩付き合っている親も多いはず。
これは、親と1対1でゆっくり過ごせる貴重な時間だからこそ出てくる行動。
「もっとかまってほしい」「今日のことを話したい」という気持ちの表れでもあります。
「寝る前に1冊だけね」と言ったはずが、次から次へと絵本を持ってくる…。
お気に入りのぬいぐるみやブロックを布団に並べ始める…。
これは“まだ寝たくない”というサインかもしれません。
また、寝る=楽しいことの終わりという意識があると、何かで時間を引き延ばそうとする行動につながることがあります。
布団に入ったと思ったら「お布団列車で〜す!」とごっこ遊びが始まる子も。
ママやパパを巻き込んで、お話の世界を展開し始める様子に「今じゃないでしょ…」と内心ため息が出ることもありますよね。
このような行動も、想像力が育ち始めている証拠です。
眠いけど眠りたくない…そんな葛藤を抱えながら、親にくっついたり触ったりする子もいます。
中には、顔をなでたり、髪をクルクルいじったり、足でトントン蹴ってきたりする子も。
スキンシップで安心したい気持ちと、眠気の攻防戦が垣間見えるこの時期ならではの行動と言えます。
いざ電気を消した瞬間に、「おなかすいた」「のどかわいた」「おしっこ…」と“寝かしつけ阻止”のリクエストが次々と飛び出すのもあるあるです。
これは本当に必要なこともあれば、「寝たくない」という理由で口にしていることも。
見極めが難しいですが、毎回応じていると逆に習慣化する可能性もあるので注意が必要です。
「2歳 寝ない 動き回る」という悩みは、本当に多くのご家庭で見られる共通のものです。
このような“あるある行動”が出るのは、決して育て方のせいではなく、子どもの発達や心理が関係している自然な現象。
怒ってしまう自分が嫌…2歳の寝かしつけでイライラした時の対処法
「もう何回言ったら寝てくれるの!?」「動かないでって言ってるでしょ!」
つい声を荒げてしまった後、「また怒っちゃった…」と自己嫌悪に陥るママ・パパは少なくありません。
特に、寝かしつけに時間がかかると、親も疲れている分、感情のコントロールが難しくなるものです。
まず伝えたいのは——怒ってしまうのはあなただけじゃないということ。
ここでは、2歳児の寝かしつけでイライラした時の考え方や具体的な対処法を紹介します。
寝かしつけにイライラするのは、それだけ一生懸命に子育てに向き合っている証拠でもあります。
疲れがたまっていたり、明日の予定が気になって焦っていたり、他にも不安やストレスを抱えていたり…。
怒ってしまう背景には、親自身のコンディションも大きく関係しています。
「怒ったこと」ではなく、「怒るまで我慢していた自分」をまずは認めてあげましょう。
完璧な親である必要はありません。むしろ、子どもと一緒に感情と向き合う経験も、成長の一部になるのです。
大声で怒鳴ってしまうと、子どもは何に対して怒られたのかよりも、「ママ・パパが怖かった」という感情だけが残ってしまうことがあります。
寝る前にそのような体験をすると、安心して眠ることが難しくなってしまうことも。
だからこそ、怒る前に一度深呼吸。
少しでも冷静さを取り戻すことで、伝えたいことを落ち着いて話す余裕が生まれます。
どうしても「寝かせなきゃ!」と強く思うと、親子の間に“対立構造”が生まれます。
子どもはその空気を敏感に察知し、さらに寝ない…という負のループに。
ここで発想を少し変えて、「今日は一緒に横になるだけでOK」とハードルを下げてみましょう。
横になって目を閉じるだけでも、子どもの体は休まります。
完璧に寝かせようとせず、“心地よい時間を共有する”と捉えることで、親の心も軽くなるはずです。
毎日完璧に寝かしつけようとすると、必ずどこかで疲れが爆発してしまいます。
そこでおすすめなのが、「今日は寝かしつけをがんばる日」「今日は少し手を抜く日」とメリハリをつけること。
手を抜く日は、絵本を省略したり、いつもより寝る時間を少しだけ遅らせたり、自動で音楽が流れるアイテムに頼ってみるのも手です。
寝かしつけにも“オフの日”があっていいのです。
もし寝かしつけ中に怒ってしまっても、あとで子どもに「さっきはごめんね。ママも疲れてたんだ」と伝えることはとても大切です。
2歳児はまだ言葉の理解が不完全でも、親の声のトーンや表情で“謝ってくれている”ことはしっかり伝わります。
このやりとりを重ねていくことで、子どもも「感情は伝えていい」「あとから仲直りできる」という信頼関係を学んでいきます。
イライラが限界に達しそうなときは、思いきって一旦その場を離れるのもおすすめです。
子どもが安全な場所にいることを確認した上で、トイレにこもる・廊下で深呼吸するなど、気持ちを切り替える時間を持ちましょう。
自分の心を守ることは、子育てにおいてとても大切なセルフケアです。
「怒らないようにしなきゃ」と自分を追い詰めすぎると、それもまたストレスになります。
大切なのは、「毎日100点」ではなく、「今日は60点でも、また明日がある」と思える気持ちのゆとり。
完璧じゃなくていい。
怒る日も、笑える日もある。それが、子育てです。
「寝たくない!」と泣く・叫ぶ子への対応法
寝る時間になっても「まだ寝ない!」「イヤー!!」と大声で泣き叫び、全力で寝かしつけを拒否する2歳児。
布団に入れようとすると暴れる、抱っこしても泣き止まない…。
そんな「寝たくない」と訴える子どもに、どう対応すれば良いのでしょうか?
まず知っておきたいのは、2歳児の「泣き叫ぶ行動」は、甘やかしているからでも、わがままでもありません。
まだ言葉だけで自分の気持ちを表現しきれない2歳の子どもにとって、泣く・叫ぶという手段は大切な感情の出口です。
「眠いけど寝たくない」「ママと離れたくない」「日中のストレスを解放したい」など、いろんな思いが詰まっていることもあります。
そのため、まずは「この子なりにがんばっているんだな」と受け止めてあげる姿勢が大切です。
泣き叫んでいるときに「もう寝る時間でしょ!」「うるさい!」と叱ってしまうと、子どもはさらに興奮してしまい逆効果になってしまいます。
そんなときは、まず感情に寄り添う言葉がけをしてみましょう。
たとえば——
- 「まだ遊びたいよね、楽しかったもんね」
- 「今日はいっぱいがんばったね。寂しかったのかな?」
- 「ママもそばにいるから大丈夫だよ」
このような共感の言葉をかけることで、子どもは安心し、少しずつ気持ちを落ち着けることができます。
「寝る」ことを強制されると、反発したくなるのは子どもも同じ。
そんなときは、「寝るか寝ないか」ではなく、“寝る準備をどう進めるか”の選択肢を与えると、気持ちの切り替えがうまくいくことがあります。
例:
- 「お布団まで、ママと手をつなぐ?それともジャンプして行く?」
- 「電気消すの、○○ちゃんがやる?ママがやる?」
“自分で選んだ”という感覚があるだけで、子どもの行動は不思議と変わることがあります。
なかなか泣き止まず、親も疲れてきてしまうこともありますよね。
でも、泣いている最中に「寝なさい!」と言っても、子どもは耳を貸してくれません。
まずは抱っこして落ち着かせる/背中をトントンする/お気に入りのぬいぐるみを抱かせるなど、安心できる手段を試してみましょう。
そして、子どもの呼吸がゆっくりになってきたタイミングで、絵本を読む・音楽を流すなど、眠りに向かうルーティンを始めてみてください。
子どもによっては、保育園や家での小さなストレスが夜に爆発することもあります。
特に昼間ガマンしたことや、イヤなことを伝えられずにいた子は、夜になって「泣く」という形で感情を出すことがあります。
夜泣きや夜の癇癪は、「子どもなりの感情のデトックス」と捉えると、親も少し心が軽くなります。
2歳の「寝たくない!」は、成長の証。
泣き叫ぶのも、自分の意思を伝える練習のひとつです。
泣くこと自体を止める必要はありません。
ただ、泣いているときに「怒られない」「見放されない」「ママやパパはそばにいてくれる」と思える安心感が、
その子の心をゆっくりと落ち着かせていきます。

(画像引用:モグモ公式サイト)
共働きで毎日バタバタのわが家。夕飯作りはどうしても「時短」「手軽」重視になりがちで、栄養バランスに不安を感じていました。
そんなときに知ったのが【mogumo】。
管理栄養士監修・無添加で安心できる上、冷凍庫から出してレンジで温めるだけ。
最初は「子どもが食べてくれるかな?」と半信半疑でしたが、思った以上に完食してくれて驚きました。
野菜も入っていて栄養も取れるし、罪悪感もゼロ。
ママの“心のゆとり”を取り戻してくれるサービスだと思います。
>>mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ
「放置」ではなく「見守る」!寝ない2歳児との付き合い方
寝かしつけに毎晩1時間以上…
あの手この手を尽くしても寝ないわが子に、ふと頭をよぎるのが「もう放っておいてもいいのでは…?」という考え。
「2歳 寝ない 放置」で検索するママ・パパも少なくありません。
でも、「放置しても大丈夫?」「罪悪感が残らない?」と迷う気持ちもありますよね。
ここでは、寝かしつけにおける“放置”の考え方と、適切な距離の取り方について解説します。
まず知っておいていただきたいのは、子どもから完全に目を離す“放置”と、そっとそばで見守る“自立の促し”はまったく別のものということ。
完全に無視をしたり、暗い部屋に一人きりにするような「見捨てた感覚」を子どもに与えるのは避けるべきですが、
子どもがひとりで横になって眠る練習をするために少し距離を取る“見守り”スタイルは、むしろ自立の一歩として有効です。
2歳頃から少しずつ「自分で眠る力」が育ってくる子もいます。
眠くなった時に、ママやパパが横にいなくても安心して眠れる力を身につけるためには、本人が寝るペースをつかむことも大切です。
「先に寝室に入れて、少しの時間様子を見る」
「寝るまではリビングで待っていて、声だけかける」
というスタイルに切り替えることで、スムーズに寝つけるようになる子もいます。
“見守り放置”をする場合は、子どもが1人で過ごしても危険がない環境を整えることが大前提です。
- ベッドや布団の周囲に転落のリスクはないか
- 誤飲につながる小物は近くにないか
- 抱き枕やぬいぐるみで顔が埋もれないか
- 寝室に危険な家具や尖った角がないか
子どもが自由に動き回る2歳だからこそ、安心して「少し離れる」ためには安全面の確認を丁寧に行いましょう。
泣いてしまった場合に、すぐに対応すると“泣けば来てくれる”と覚えてしまうかも…と心配になる方もいるかもしれません。
そんなときは、「1分→3分→5分」と少しずつ間隔を空けながら声をかけに行く“フェードアウト方式”を取り入れるとよいでしょう。
「まだ寝たくないんだよね。でもママはそばにいるよ」
「ちょっとだけ待っててね。○○ちゃんはできる子だもんね」
などの安心を与える声かけをしながら、少しずつ“親がそばにいなくても眠れる”感覚を育てていきます。
放っておくなんて、冷たい親だ…と自分を責める必要はありません。
むしろ、寝かしつけがうまくいかない中で「一度離れてみる」「子どもに任せてみる」と決断することは、親にとっても子どもにとっても大事な選択肢です。
親が疲れ切ってイライラしてしまうより、少し離れてお互いに落ち着いた方が、ずっと健全な関係でいられます。
寝かしつけは、ただ子どもを寝かせる時間ではありません。
親子の関係や信頼を築く時間でもあります。
でも、毎晩イライラしたり、泣き声に疲弊してしまうようでは、誰にとっても幸せな時間にはなりませんよね。
だからこそ、「そっと距離を取る」「時には先に寝る」「見守ることも愛情のひとつ」と捉えて、
お互いがラクになれるスタイルを探っていきましょう。
2歳の寝かしつけがラクになる“神アイテム”10選
「何をしても寝ない…」「動き回るし、泣くし、毎晩くたくた…」
そんなママ・パパの声に応えるように、寝かしつけに役立つ“神アイテム”がいろいろ登場しています。
ここでは、SNSや口コミでも話題の「寝かしつけをラクにするアイテム」を10点ご紹介します。
ただし、どのアイテムも**「魔法」ではありません**。子どもとの相性を見ながら、無理なく取り入れてみましょう。
部屋の天井や壁に星や動物の映像を映し出すアイテム。
暗い部屋が怖い子どもでも安心し、視覚的な刺激で自然と眠気が誘われます。
おやすみ前のルーティンとして「星を見ながらゴロンしようね」と誘導するのも効果的。
胎内音に近いとされる“ホワイトノイズ”を流すことで、赤ちゃん時代の安心感を思い出させてくれるアイテム。
外の物音や兄弟の声が気になる環境でも、安定した音が集中を促し眠りに入りやすくなります。
「おやすみ、ロジャー」や「おやすみ、エレン」など、読むだけで眠気を誘う構成の絵本も人気。
声のトーンやリズムに工夫があり、親子ともにリラックスしながら眠りに近づけるのが魅力です。
香りの力でリラックス効果を高めるアイテム。
ラベンダーやカモミールなどの香りは副交感神経を優位にして、自然な眠気を促すと言われています。
※使用時は「赤ちゃん・子ども向け」の表記を必ず確認してください。
クラシックやオルゴールなどの音楽を流せるプレイヤーも、寝かしつけに便利。
「この音楽が流れたら寝る時間」という習慣をつけることで、寝室モードへの切り替えがスムーズになります。
お気に入りのぬいぐるみや肌ざわりのよいブランケットは、子どもにとって「安心の象徴」。
触れることで落ち着き、入眠しやすくなります。保育園で使用しているアイテムと同じものを使うのも◎。
寝返りが激しく、布団を蹴飛ばしてしまう2歳児にぴったり。
体温調節がしやすく、寝冷えの心配がなくなることで、親も安心して見守れます。
どうしても寝かしつけ中に動き回ってしまう子には、寝室の安全確保用ゲートがあると便利。
物理的にスペースを区切ることで、遊びモードを遮断しやすくなります。
「ママとおそろいだから着たい!」という気持ちを活かして、寝るモードに楽しく誘導。
「パジャマを着たらお布団へ行こうね」と、遊び感覚でルーティン化できます。
就寝30分前から徐々に照明を暗くしてくれる照明機能付きのランプ。
自然と体が“眠る準備”に入れるようサポートします。ブルーライトをカットする暖色系がおすすめです。
今回紹介したアイテムは、すべての子に効果があるわけではありません。
でも、「このぬいぐるみを握ったら落ち着く」「この音楽を聴くと眠くなる」といった“うちの子専用スイッチ”を見つけられれば、
寝かしつけの負担は確実に軽くなります。
また、アイテムに頼ることは「手抜き」ではなく、「育児を工夫するチカラ」です。
2歳児の寝かしつけがスムーズになる生活リズム作り
寝かしつけに悩んでいる家庭の多くが、実は「寝る前だけ工夫してもなかなか寝ない…」という壁にぶつかっています。
それもそのはず。2歳児の眠りは、1日の過ごし方や生活の流れに大きく影響されるからです。
この章では、寝かしつけがスムーズになるための生活リズムの整え方について詳しく解説します。
毎日バラバラの時間に寝起きしていると、体内時計がうまく整わず、夜の眠気がやってこない原因に。
理想的なのは、朝7時ごろに起きて夜9時前には寝る生活。
「起きる時間」と「寝る時間」を固定するだけでも、子どもの体はそのリズムを覚えていきます。
2歳児はまだ昼寝が必要な時期ですが、15時以降の昼寝や、2時間以上の長時間睡眠は夜の寝かしつけの妨げになります。
理想的な昼寝の目安:
- 時間帯:12時半〜14時ごろまで
- 長さ:1〜1.5時間程度
日中に体をしっかり使って遊ばせつつ、昼寝も“適度に”とれるようなスケジュールを意識してみましょう。
夕食が遅くなったり、脂っこいもの・甘いお菓子が多かったりすると、寝つきが悪くなるケースがあります。
特に寝る直前の間食はNG。消化に時間がかかり、体が「眠るモード」に入りにくくなります。
夕食は18〜19時台までに済ませるのが理想。温かい味噌汁やおじやなど、消化の良いメニューを選ぶと◎です。
2歳児は「繰り返し」や「パターン」に安心感を覚える時期です。
そのため、就寝前の流れを毎晩できるだけ同じようにすることで、「これをしたら寝る時間だ」と自然に認識するようになります。
おすすめの寝る前ルーティン例:
- お風呂(18:30ごろ)
- 夕食(19:00ごろ)
- おもちゃを片付ける
- 絵本を1〜2冊読む
- トイレ or おむつ替え
- 電気を消す+子守唄や音楽
- 就寝(20:30〜21:00)
この“順番”が崩れると、子どもも不安になり、寝つきに影響が出ることがあります。
就寝前に明るい画面を見ていると、脳が覚醒してしまい寝つきが悪くなります。
特にスマホやタブレットのブルーライトは要注意。
最低でも就寝の1時間前には画面をオフにして、間接照明でゆったりとした雰囲気を作りましょう。
2歳の子どもにとって、生活リズムが安定していることは“安心の土台”になります。
その安心感が、夜の入眠にもつながっていくのです。
「昼間の過ごし方なんて関係ない」と思ってしまいがちですが、寝かしつけがうまくいかないときほど、
1日の流れや環境づくりを見直してみることが近道になります。
子どもが自分で眠るようになるためにできること
2歳頃になると、「いつかは一人で寝てくれるようになってほしい」と思うママ・パパも多いはず。
しかし実際は、寝かしつけに毎晩1時間以上、添い寝・抱っこ・トントンが欠かせない…というご家庭も多いのではないでしょうか?
この見出しでは、「子どもが自分で眠る力」を育てるために親ができることを具体的に紹介していきます。
まず大前提として知っておきたいのが、「寝かしつけを卒業させる方法」に正解はないということ。
睡眠は、しつけや言葉で教えるものではなく、時間と経験の中で“育っていく力”です。
だからこそ、焦らずに、子どものペースに合わせて少しずつステップアップしていくことが大切です。
“自分で眠る”には、その前段階として、「寝る準備を自分で進められる」ことが大きな鍵になります。
たとえば:
- パジャマを自分で着てみる
- 絵本を自分で選ぶ
- 電気を自分で消す
このような寝るまでの流れを“自分でコントロールできた”という成功体験が、「自分で眠れるかも」という気持ちにつながっていきます。
2歳児にとって、親がそばにいるという安心感が睡眠の土台になります。
完全に一人で寝かせることよりも、まずは「安心して眠れる環境」を整えることが大切です。
たとえば、最初は:
- 添い寝しながら寝かせる
- 一緒にゴロンとして、途中で少しずつ距離をあけていく
- 部屋を出る時に「また後で見に来るね」と伝えて安心させる
少しずつステップを踏むことで、子どもは「ママやパパが見守ってくれている」と感じながら眠りにつくことができます。
眠くなってから寝室へ行く…ではなく、決まった時間に布団に入る習慣をつけることもポイントです。
眠気は波のように訪れ、タイミングを逃すと逆に寝つきが悪くなることもあります。
毎日同じ時間に布団へ行くことで、「ここで眠る」という身体のリズムを整えることができます。
たとえ親がそばにいて寝たとしても、「自分で布団に入った」「電気を消せた」などの小さな行動をしっかり褒めることが大切です。
- 「すごいね!自分でゴロンできたね」
- 「昨日より早く寝られたね!」
と声をかけることで、子どもは“できた自信”を積み重ねていきます。
この積み重ねが、自立した睡眠への一歩になります。
子どもが自分で寝られるようになることは、成長の証でもありますが、
そのプロセスでしか得られない「親子で寄り添って眠る時間」も、今だけの大切な宝物です。
「もう添い寝したくない」と思う夜もあれば、
「いつかこの時間がなくなるのか…」と切なくなる夜もあるかもしれません。
大切なのは、「今の寝かしつけスタイルが正しいかどうか」ではなく、親も子どもも心地よく過ごせること。
それぞれのご家庭に合った“眠りの形”を、ゆっくり見つけていきましょう。
寝かしつけは「親子で育っていく時間」
2歳の寝かしつけは、本当に大変。
動き回る、泣き叫ぶ、全然寝ない…。
そんな毎日に疲れ果てて、「もう限界」と感じてしまうこともあるかもしれません。
でも、それは決してあなただけではありません。
寝かしつけに悩むご家庭はとても多く、それぞれが試行錯誤を重ねています。
今回ご紹介したように、寝ない理由には子どもなりの発達の背景があり、
怒ってしまう気持ちにも、毎日がんばる親の愛情が詰まっています。
「泣いてもいいよ」「うまくいかない日もあるよ」
そんなふうに、お互いに少し肩の力を抜いて、
“がんばりすぎない寝かしつけ”を目指してみませんか?
寝かしつけは、ただ眠らせるだけの作業ではなく、
親子の心がつながる貴重な時間でもあります。
今日も、昨日よりほんの少しラクになれるように。
この先の毎晩が、ほんの少し穏やかになりますように。

(画像引用:モグモ公式サイト)
「今日のごはん、どうしよう…」
仕事から帰ってきて、保育園から子どもを迎えて、買い物して、夕飯を作って…毎日そんな繰り返しに疲れていませんか?
そんな忙しいママにおすすめなのが、幼児食宅配サービス mogumo(モグモ)。
1歳半〜6歳の子ども向けに、管理栄養士が考えた無添加・冷凍のおかずをお届けしてくれるんです。
✔ レンジでチンするだけ、調理はほぼゼロ!
✔ 栄養バランスもバッチリで偏食対策にも◎
✔ 忙しい夕食時に“あと1品”としても使える
「子どもがパクパク食べてくれる」だけで、ママの心もぐっと軽くなりますよ。
毎日の食事作りを少しラクにして、子どもと笑顔で過ごす時間を増やしてみませんか?
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ をタップ
をタップ




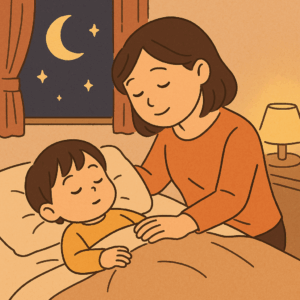
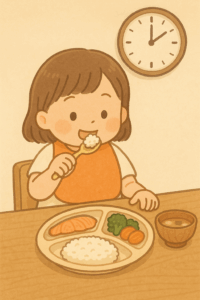




コメント