生後1ヶ月の赤ちゃんは、まだ母乳やミルクの飲む量や間隔が安定しない時期です。
母乳だけで足りているのか、ミルクをどれくらい足せばいいのか、不安や疑問を抱えるママ・パパは多いのではないでしょうか。
特に「混合育児」をしていると、母乳の後に足すミルク量やタイミングが分からず、「飲み過ぎていないかな?」「少なすぎていないかな?」と悩みやすいものです。
本記事では、生後1ヶ月のミルクを足す量の目安を、混合授乳と完全ミルク(完ミ)のケースに分けて詳しく解説します。
さらに、60ml・80ml・100mlなど具体的な追加量の考え方や、飲み過ぎサイン・適切な授乳スケジュール例もご紹介。
量の調整に迷ったときの判断ポイントや、体重増加をチェックする方法もまとめています。
この記事を読むことで、「うちの子は足りている?」「どれくらい足せばいい?」というモヤモヤが解消され、安心して授乳計画を立てられるようになります。
【総額7,660円OFFクーポン】【特典付き】
初回限定キャンペーンでお得にGETできる!
(画像引用:モグモ公式サイト)
「子どもが小さいうちは、仕事も家事も育児も全部フル回転。気づけば自分の時間はゼロ…」
「健康的なご飯を準備してあげたいけど、うまく時間を作れない…」
そんなママの一番の悩みは“毎日のごはん作り”ではないでしょうか。そんな時におすすめなのが『モグモ』です。
モグモは1歳半〜6歳向けの幼児食宅配サービスで、無添加で栄養バランスに優れた冷凍ごはんが届くため、冷凍庫にストックしておけばいつでも使えるので安心です。
- 保育園帰りで子どもが「お腹すいた!」と言っても、レンジで数分チンするだけ
- 献立に悩む時間がなくなる
- 子どもが食べやすい味付け・サイズだから、食べムラが減る
「今日は疲れてごはんを作りたくない…」「子供にも栄養バランスが整った食事を摂らせたい」そんなときに助けてくれるんです。
家族の食卓を無理なく支えながら、ママに“心のゆとり”を取り戻してくれるはずです。今なら全額返金保証付きで安心して試せるので、気軽に始めてみてくださいね!
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ![]()
生後1ヶ月の赤ちゃんにミルクを足す必要があるケース
生後1ヶ月は、母乳の分泌が安定し始める時期ではありますが、すべてのママが十分な量を出せるとは限りません。
赤ちゃんの体格や飲む力、ママの体調や生活リズムによって、母乳だけでは足りない場合もあります。
ここでは、ミルクを足すことを検討すべき代表的なケースをご紹介します。
生後1ヶ月の赤ちゃんは、1日あたり25〜30g程度の体重増加が理想的とされています(週に約150〜210g)。
母乳やミルクをしっかり飲めている場合、このペースで体重が増えていきます。
しかし、定期的な体重測定で増加が少ない、または増えていない場合は、必要な栄養が足りていないサインです。
母乳が十分出ていない可能性があり、この場合はミルクを足すことが推奨されます。
母乳を与えた直後にもかかわらず、すぐに泣き出したり、口をパクパクさせたりする場合は、満腹感が得られていない可能性があります。
特に授乳直後から指しゃぶりやおしゃぶりを強く吸う様子があるときは、お腹が空いているサインかもしれません。
ただし、眠い・抱っこしてほしい・おむつが気持ち悪いなど、空腹以外の理由で泣くことも多いので、原因を一つずつ確認してからミルク追加を検討しましょう。
新生児期は2〜3時間ごとの授乳が目安ですが、母乳後1時間もたたずに頻繁に泣く場合は、授乳で十分な量を飲めていないことが考えられます。
母乳の分泌量が少ないか、赤ちゃんの吸う力が弱くて必要量を取れていないことが理由です。
こうした場合、日中だけミルクを足したり、夜間授乳時に多めに足してあげることで、赤ちゃんもぐっすり眠れるようになることがあります。
出産から1ヶ月以内は、母乳の分泌が安定するまでに時間がかかることがあります。
母乳の量が少ない・片方の胸からしか出ない・搾乳してもほとんど出ないなどの場合、ミルクを補助的に使うことで赤ちゃんの栄養不足を防げます。
産後の体調不良や睡眠不足、ストレスも母乳の出に影響します。
無理に母乳だけにこだわらず、必要に応じてミルクを取り入れることは決して悪いことではありません。
出産後の1ヶ月健診や訪問指導で、医師や助産師から「体重増加がゆるやか」「もう少しミルクを足してみましょう」と言われた場合は、その指示に従うことが大切です。
専門家は赤ちゃんの発育状況や健康状態を総合的に見て判断しているため、自己判断で量を減らすのは危険です。
-
便やおしっこの回数が極端に少ない(おしっこは1日6回以上が目安)
-
授乳中によく眠ってしまい、十分に飲めていない
-
泣き方が弱々しく、活動量が少ない
これらは赤ちゃんが必要な栄養を取れていない可能性があり、早めの対処が必要です。
生後1ヶ月は、赤ちゃんの成長に必要な栄養をしっかり確保することが最優先です。
母乳だけにこだわらず、必要であればミルクを上手に足すことで、赤ちゃんもママも安心して過ごせます。
次の章では、混合育児と完全ミルクの場合の具体的なミルク量の目安について詳しく解説していきます。
生後1ヶ月のミルク量の目安(完全ミルク・混合別)
生後1ヶ月は、母乳やミルクの必要量が徐々に安定してくる時期です。
とはいえ、完全ミルク(完ミ)と混合授乳ではミルクの量やあげ方が異なります。
ここでは、それぞれの授乳スタイルに合わせた目安量と考え方を解説します。
完全ミルクは、すべての栄養をミルクから摂取するため、必要量が比較的明確です。
メーカーや個人差で多少異なりますが、生後1ヶ月の一般的な目安は次の通りです。
-
1回量:100〜120ml
-
回数:1日7〜8回(授乳間隔3時間程度)
-
1日合計量:700〜960ml程度
ミルク缶に記載されている量はあくまで目安ですが、体重や飲みっぷりによって前後しても問題ありません。
例えば、よく飲む赤ちゃんなら1回130ml程度でも大丈夫ですが、飲み過ぎによる吐き戻しや便秘がないか観察しましょう。
完ミでの量調整のポイント
-
体重×150mlを目安に1日の総量を計算
例:4kgの赤ちゃん → 4,000g × 150ml = 600ml(1日)
※ただし、生後1ヶ月はまだ飲みムラがあるため、必ずしも計算通りにしなくてもOK
-
授乳間隔が短くなりすぎる場合は、1回量を少し増やして間隔を整える
-
夜間授乳を長めに空けたい場合は、寝る前の授乳で多め(+10〜20ml)に与える方法も有効
混合授乳は、母乳を与えた後に不足分をミルクで補うスタイルです。
この場合、母乳の出る量や赤ちゃんの飲む力によってミルクの追加量が変わります。
一般的な混合授乳の目安は以下の通りです。
-
母乳後の追加量:40〜80ml
-
回数:1日6〜8回
-
1日合計量:300〜600ml程度(母乳の量によって変動)
混合授乳の量調整の考え方
混合授乳では「混合 ミルクの量 わからない」と悩む方がとても多いです。
母乳は哺乳瓶のように飲んだ量を目で確認できないため、赤ちゃんの様子や体重増加を手がかりに判断します。
-
満腹サイン
飲み終わった後に口を閉じる、乳首を押し返す、ウトウトする
-
足りないサイン
授乳後すぐに泣く、手を口に持っていく、頻繁に欲しがる
-
体重が週150g以上増えていれば、今の追加量で十分と考えて良い
|
項目 |
完全ミルク |
混合授乳 |
|---|---|---|
|
栄養摂取 |
全てミルク |
母乳+ミルク |
|
1回の量 |
100〜120ml |
40〜80ml(母乳後) |
|
量の決め方 |
体重や月齢から計算 |
赤ちゃんの飲み具合と体重増加で調整 |
|
メリット |
量が計算しやすい、預けやすい |
母乳の免疫成分も摂れる |
|
注意点 |
飲み過ぎに注意 |
量の判断が難しい |
-
ミルクはあくまで「補う」もので、母乳の出が良ければ無理に多く足さなくてもOK
-
量が多すぎると吐き戻しや便秘の原因になる
-
少なすぎると体重増加不良や発育遅延につながる可能性がある
-
初めは少なめから始め、様子を見ながら増やすのが安全
生後1ヶ月のミルク量は、完全ミルクなら1回100〜120ml、混合授乳なら母乳後40〜80mlが目安です。
ただし、これはあくまで一般的な基準であり、赤ちゃんによって必要量は異なります。
次の章では、より具体的に60ml・80ml・100ml別の追加量の使い分けを解説します。
生後1ヶ月のミルク足す量の具体例(60ml・80ml・100ml)
生後1ヶ月で混合授乳をしていると、母乳後に足すミルク量を60ml・80ml・100mlのどれにすべきか迷う方は多いです。
ここでは、それぞれの量を選ぶ目安やメリット・注意点を具体的に解説します。
「生後1ヶ月 混合 ミルク60」は、比較的少なめの追加量です。
適しているケース
-
母乳の出が比較的良い
-
体重増加が順調で、授乳間隔も保てている
-
赤ちゃんが小柄で胃の容量がまだ小さい
メリット
-
飲み過ぎによる吐き戻しや消化負担を防ぎやすい
-
母乳を多く飲む習慣を保てる
注意点
-
少なすぎると授乳間隔が短くなりやすい
-
母乳の量が急に減った場合、栄養不足に気づきにくい
「生後1ヶ月 混合 ミルク80」は、多くの赤ちゃんに合いやすい「標準的な追加量」です。
適しているケース
-
母乳の出は普通〜やや少なめ
-
授乳後3時間ほど間隔が空く
-
体重増加がややゆるやかで、少し補強したい
メリット
-
満腹感が得られやすく、授乳間隔が安定しやすい
-
夜間授乳の回数を減らせることもある
注意点
-
体重増加が急な場合は飲み過ぎの可能性あり
-
赤ちゃんの様子を見ながら、1回あたりの量を微調整する必要がある
「生後1ヶ月 混合 ミルク100」は、追加量としては多めの設定です。
適しているケース
-
母乳の量がかなり少ない、またはほぼ出ていない
-
赤ちゃんが大きめで飲む力が強い
-
完全ミルクに近い混合授乳スタイル
メリット
-
栄養不足をしっかり防げる
-
授乳間隔が安定しやすく、ママの休憩時間が取れる
注意点
-
消化に負担がかかりやすく、吐き戻しの原因になることも
-
母乳を飲む量が減り、分泌がさらに減ってしまう可能性あり
どの量を選ぶかは、赤ちゃんの個性と授乳スタイルに合わせるのが大切です。
以下のポイントを参考にしてください。
-
体重増加の確認
週150g以上増えていれば現状維持でOK
-
授乳間隔
2〜3時間持てば十分
-
赤ちゃんの様子
飲み終わった後に満足そうか、吐き戻しが多くないか
ミルク量は一度に大きく増減させず、10〜20ml単位で調整すると安全です。
急な増量は消化不良や便秘の原因になり、急な減量は栄養不足につながる可能性があります。
-
60ml → 母乳がよく出る&小柄な赤ちゃん向け
-
80ml → 標準的な追加量、多くのケースに合いやすい
-
100ml → 母乳がほとんど出ない/大きめの赤ちゃん向け
次の章では、この追加量を踏まえて、飲み過ぎサインの見分け方と防ぐ方法を詳しく解説します。
ミルクの飲み過ぎサインと対処法
生後1ヶ月の赤ちゃんは、まだ満腹中枢の働きが未熟で、お腹がいっぱいになっても反射的に吸ってしまうことがあります。
そのため、ミルクを与えすぎてしまうと「飲み過ぎ」の状態になり、体調や授乳リズムに影響が出ることも。
ここでは、飲み過ぎのサインと、そうなったときの対処法を詳しく解説します。
「生後1ヶ月 ミルク 飲み過ぎ サイン」として代表的なのは以下の通りです。
① 吐き戻しが多い・勢いがある
授乳後すぐや、しばらく経ってから大量に吐く場合は、胃の容量を超えて飲んでいる可能性があります。特に、吐き戻しが噴水のように勢いよく出るときは要注意です。
② お腹がパンパンに張っている
ミルクを多く飲みすぎると、胃や腸にガスやミルクが溜まり、お腹が固く張ります。触ると張っていて、赤ちゃんが苦しそうに足を縮めたり泣いたりします。
③ 便やおしっこの変化
下痢や水っぽいうんちが増える、または便秘になることがあります。ミルクの消化に負担がかかっているサインです。
④ 授乳後も落ち着かない
満腹感があるはずなのに泣き続ける場合は、胃の不快感や張りが原因のこともあります。空腹ではなく「飲み過ぎによる苦しさ」の可能性があります。
飲み過ぎサインが見られた場合は、ミルクの量やあげ方を見直しましょう。
① 1回量を減らす
例えば100ml与えていた場合、80mlに減らして様子を見ます。1回量を減らす代わりに回数を少し増やすことで、必要な栄養は確保しつつ胃への負担を減らせます。
② 授乳中に休憩を入れる
一気に飲ませると満腹中枢が反応する前に飲み過ぎてしまいます。半分ほど飲んだところで休憩を入れ、ゲップをさせてから再開しましょう。
③ 哺乳瓶の乳首サイズを見直す
乳首の穴が大きいとミルクが勢いよく出てしまい、飲むスピードが速くなります。流量が少ないタイプに変えると飲み過ぎを防ぎやすくなります。
④ 授乳間隔を見直す
2時間未満で頻繁に与えると、胃が休まる時間がなくなり、飲み過ぎになりやすいです。
母乳後にミルクを足す場合も、欲しがるたびではなく間隔を一定に保つことが大切です。
-
吐き戻しや下痢による栄養ロス
-
胃や腸の負担増加による消化不良
-
授乳間隔が短くなり、ママの休息時間が減る
-
母乳量の減少(混合育児の場合)
これらは赤ちゃんの成長や生活リズムにも影響します。
飲み過ぎを防ぐことは、赤ちゃんの健康だけでなくママの育児負担軽減にもつながります。
-
吐き戻しに血が混じる
-
噴水状の吐き戻しが頻繁にある
-
体重が急激に増える、または逆に減る
-
機嫌が悪く、授乳後もずっと泣き続ける
これらは単なる飲み過ぎではなく、病気や発達上の問題が隠れている場合があります。早めに小児科を受診しましょう。
生後1ヶ月の赤ちゃんは、必要以上に飲んでしまうことがあるため、吐き戻しやお腹の張りなどの飲み過ぎサインを見逃さないことが大切です。
量の調整や授乳方法の見直しで改善できることが多く、適切な管理によって赤ちゃんも快適に過ごせます。

(画像引用:モグモ公式サイト)
共働きで毎日バタバタのわが家。夕飯作りはどうしても「時短」「手軽」重視になりがちで、栄養バランスに不安を感じていました。
そんなときに知ったのが【mogumo】。
管理栄養士監修・無添加で安心できる上、冷凍庫から出してレンジで温めるだけ。
最初は「子どもが食べてくれるかな?」と半信半疑でしたが、思った以上に完食してくれて驚きました。
野菜も入っていて栄養も取れるし、罪悪感もゼロ。
ママの“心のゆとり”を取り戻してくれるサービスだと思います。
>>mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ
生後1ヶ月 混合授乳のスケジュール例
生後1ヶ月の赤ちゃんは、まだ授乳間隔や生活リズムが安定していない時期です。
特に混合授乳では、母乳とミルクの組み合わせ方によって授乳スケジュールが大きく変わります。
ここでは、生後1ヶ月 混合 スケジュールの具体例と組み立て方を紹介します。
混合授乳には主に次の2つのパターンがあります。
-
母乳の後にミルクを足すパターン
母乳をできるだけ吸わせ、その後不足分をミルクで補う。
→ 母乳の分泌を促しつつ、栄養不足を防げる。
-
母乳とミルクを交互にあげるパターン
1回は母乳のみ、次の回はミルクのみ、と交互に与える。
→ 哺乳瓶や授乳方法の切り替えがスムーズで、ママの休憩時間も確保しやすい。
-
6:00 母乳→ミルク40ml追加
-
9:00 母乳→ミルク60ml追加
-
12:00 母乳→ミルク40ml追加
-
15:00 母乳→ミルク60ml追加
-
18:00 母乳→ミルク40ml追加
日中は比較的短い間隔(約3時間)で授乳し、追加ミルク量は40〜60ml程度を目安に調整します。
-
21:00 母乳→ミルク80〜100ml追加(多め)
-
1:00 ミルク100ml(母乳なし)
-
5:00 母乳→ミルク60ml追加
夜は母乳量が減りやすい上、ママの睡眠を確保するためにミルクを多めに与えるのがおすすめです。
多めに与えることで授乳間隔を長くでき、夜中の授乳回数を減らせます。
-
6:00 母乳のみ
-
9:00 ミルク100ml
-
12:00 母乳のみ
-
15:00 ミルク100ml
-
18:00 母乳のみ
-
21:00 ミルク100ml
-
2:00 母乳またはミルク
この方法は、ミルクの量が計算しやすく、母乳分泌も保ちやすい反面、母乳量が減っている場合は不足しやすい点に注意が必要です。
-
赤ちゃんの飲み具合で柔軟に変更する
固定的にしすぎると、成長や体調の変化に対応できない場合があります。
-
母乳の時間はしっかり確保する
母乳を飲ませる時間が短いと分泌が減少する原因に。
-
夜間授乳の工夫
パパや家族と交代でミルク授乳を行うと、ママの負担軽減になる。
混合授乳のスケジュールは、日中は母乳をメインにしてミルクで補い、夜間はミルク多めで睡眠確保を目指すとバランスが取りやすくなります。
スケジュールはあくまで目安であり、赤ちゃんの成長や母乳量に合わせて柔軟に変更することが大切です。
ミルク追加量がわからないときの判断ポイント
混合育児をしているママ・パパからよく聞かれる悩みが、「混合 ミルクの量 わからない」という声です。
母乳は飲んだ量が数値で見えないため、足すべきミルクの量をどう決めれば良いのか迷ってしまいます。
ここでは、ミルク追加量を判断するための具体的なポイントを解説します。
一番確実なのは、体重増加ペースを確認することです。
-
生後1ヶ月の理想的な体重増加:1日25〜30g(週150〜210g)
-
1週間で150g以上増えていれば、追加量は十分である可能性が高い
チェック方法
-
家庭用ベビースケールで定期的に計測(1週間ごとが目安)
-
1日の増減ではなく、1週間単位での増加傾向を見る
母乳後に追加ミルクを与えるかどうかは、赤ちゃんの反応で見極められます。
足りているサイン
-
授乳後にウトウトする
-
乳首を押し返す
-
表情が落ち着く
足りないサイン
-
授乳後すぐに泣き出す
-
指しゃぶりやおしゃぶりを強く吸う
-
授乳間隔が1時間未満で泣く
生後1ヶ月の赤ちゃんは、おしっこの回数が1日6回以上、うんちは1〜数回が目安です。
おしっこの回数が少ない、うんちが硬い・出ない場合は、栄養や水分が不足しているサインかもしれません。
母乳量が多いか少ないかを知る方法として、搾乳やテスト授乳があります。
-
搾乳:1回で50ml以上取れる場合は比較的多い方
-
テスト授乳:授乳前後で体重を測り、差分で飲んだ量を確認
※これらはあくまで目安であり、毎回行う必要はありません。
初めて量を決めるときは、多めより少なめから始めて様子を見るのがおすすめです。
例えば、「足りないかも?」と思ったら、まず40〜60ml程度足してみて、授乳間隔や赤ちゃんの満足度を観察します。
必要に応じて10〜20mlずつ増やすと安全です。
毎回同じ量にこだわらず、日や時間帯によって変える方法もあります。
-
昼間:母乳メイン+ミルク40〜60ml
-
夜間:睡眠確保のためミルク80〜100ml
このように変えることで、赤ちゃんも満足しやすく、ママの休憩時間も確保しやすくなります。
1ヶ月健診や産後ケア訪問時には、体重や授乳状況を伝え、ミルクの追加量について相談しましょう。
プロは赤ちゃんの成長曲線や発達状態を見て、最適なアドバイスをしてくれます。
-
体重増加、赤ちゃんの様子、おしっこ・うんちの回数が重要な判断基準
-
初めは少なめから始め、必要に応じて増やす
-
日中と夜間で追加量を変えるのも効果的
次は、完全ミルクに切り替える場合の量と注意点について解説していきます。
完全ミルクに切り替える場合の量と注意点
生後1ヶ月の時点で母乳から完全ミルク(完ミ)に切り替える家庭も少なくありません。
理由は、母乳の分泌が少ない、ママの体調や職場復帰の予定、授乳ストレスの軽減などさまざまです。
ここでは、生後1ヶ月 ミルクの量 完ミの目安や切り替えの注意点を解説します。
生後1ヶ月で完ミにする場合の一般的な目安は以下の通りです。
-
1回量:100〜120ml
-
授乳回数:1日7〜8回(授乳間隔3時間程度)
-
1日合計量:700〜960ml程度
この量はあくまで目安であり、赤ちゃんの体重や飲みっぷりに応じて調整します。
計算で求める方法
「体重 × 150ml」が1日の総ミルク量の目安です。
例:4kgの赤ちゃん → 4,000g × 150ml = 600ml/日
※メーカー推奨量と比較して多すぎ・少なすぎにならないよう注意します。
切り替えのステップ
母乳から完ミへ切り替える場合は、急に全てをミルクに置き換えず、段階的に進めるのが安心です。
-
まずは夜間授乳をミルクにする
-
日中の授乳のうち1〜2回をミルクに置き換える
-
赤ちゃんの排泄や体重増加を確認しながら全授乳をミルクに変更
-
量が正確に把握できる
飲んだ量を数値で管理できるので、足りない・飲み過ぎの判断がしやすい。
-
授乳を家族で分担できる
パパや祖父母も授乳可能で、ママの休養時間が確保できる。
-
授乳間隔が安定しやすい
母乳より消化に時間がかかるため、授乳間隔が長くなる傾向がある。
-
母乳の免疫成分が摂れなくなる
病気予防の効果は低くなるため、手洗い・衛生管理をより徹底。
-
便秘になりやすい
水分補給(湯冷まし)や腹部マッサージで予防。
-
コストがかかる
粉ミルクや液体ミルクの購入費用を見込んでおく必要がある。
-
ミルク作りの手間
外出時や夜間授乳では特に準備時間が必要。
完ミの場合は哺乳瓶を使う回数が増えるため、毎回の消毒が欠かせません。
-
煮沸消毒
-
薬液消毒
-
電子レンジスチーム消毒
方法は家庭の環境に合わせて選び、常に清潔を保ちます。
完ミは量をコントロールしやすい反面、赤ちゃんが欲しがるたびに与えてしまうと飲み過ぎになります。
-
授乳間隔を2.5〜3時間あける
-
泣いても空腹以外の理由(抱っこ、オムツ、温度)を確認してから与える
-
授乳中に休憩を挟み、満腹感が伝わる時間を確保
生後1ヶ月での完ミは、1回100〜120ml × 1日7〜8回が目安ですが、体重や成長曲線を見ながら調整します。
急な切り替えではなく段階的に進めることで、赤ちゃんの消化器官にも負担をかけずに移行できます。
この記事のまとめ
生後1ヶ月の赤ちゃんにとって、十分な栄養をとることは成長と健康のために欠かせません。
母乳だけでは足りない場合や、ママの体調・生活リズムに合わせてミルクを足すことは、決して悪いことではありません。
むしろ、赤ちゃんにとってもママにとっても安心できる選択肢のひとつです。
-
ミルクを足す必要があるサイン
体重増加が少ない、授乳後すぐ泣く、授乳間隔が短い、おしっこやうんちの回数が少ない場合はミルク追加を検討。
-
ミルク量の目安
完全ミルクなら1回100〜120ml(1日7〜8回)、混合授乳なら母乳後40〜80mlが目安。
-
具体的な追加量の考え方
60mlは母乳が多い場合、80mlは標準的、100mlは母乳がほとんど出ない場合や大きめの赤ちゃん向け。
-
飲み過ぎサインと対策
吐き戻しやお腹の張り、下痢や便秘があれば量や授乳方法を見直す。
-
混合授乳スケジュール例
日中は母乳メインでミルクを補い、夜間はミルク多めで睡眠確保を目指す。
-
量がわからないときの判断基準
体重増加・授乳後の様子・排泄の回数をチェックし、少なめから試して調整。
-
完ミへの切り替え方
段階的に移行し、衛生管理や飲み過ぎ防止も意識する。
育児書やネットの情報はあくまで「目安」です。
赤ちゃんの個性や成長ペースは一人ひとり違います。
周りと比べる必要はなく、あなたの赤ちゃんに合った方法を見つけることが何より大切です。
もし迷ったり不安に感じたら、1人で抱え込まず、医師や助産師、育児経験者に相談しましょう。
赤ちゃんもママも笑顔で過ごせる授乳スタイルが、あなたの家庭の正解です。

(画像引用:モグモ公式サイト)
「今日のごはん、どうしよう…」
仕事から帰ってきて、保育園から子どもを迎えて、買い物して、夕飯を作って…毎日そんな繰り返しに疲れていませんか?
そんな忙しいママにおすすめなのが、幼児食宅配サービス mogumo(モグモ)。
1歳半〜6歳の子ども向けに、管理栄養士が考えた無添加・冷凍のおかずをお届けしてくれるんです。
✔ レンジでチンするだけ、調理はほぼゼロ!
✔ 栄養バランスもバッチリで偏食対策にも◎
✔ 忙しい夕食時に“あと1品”としても使える
「子どもがパクパク食べてくれる」だけで、ママの心もぐっと軽くなりますよ。
毎日の食事作りを少しラクにして、子どもと笑顔で過ごす時間を増やしてみませんか?
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ をタップ
をタップ




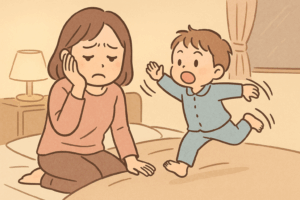
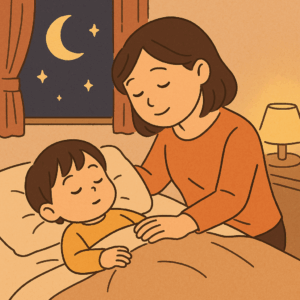
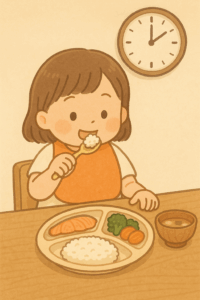



コメント