「さっきミルクを飲んだばかりなのに、また泣いて欲しがる…」「本当に足りてないの?飲み過ぎじゃないの?」——そんなふうに、新生児期の赤ちゃんの様子に戸惑うママやパパは少なくありません。
特に生後0〜2ヶ月ごろは、授乳リズムがまだ安定せず、ミルクを飲んでもすぐに欲しがる、泣き続ける、寝ない…といった状況がよく起こります。
インターネットで検索しても情報がバラバラで、「うちの子だけかも…」と不安になることもあるでしょう。
しかし、実はこうした行動には、赤ちゃん特有の理由がしっかりあります。そして、必要以上に心配しすぎなくても大丈夫なケースも多いのです。
この記事では、「新生児がミルクを飲んでも欲しがる」理由とその背景、ミルクの間隔や量の目安、そして親としてどのように対応すればよいかを、わかりやすく解説していきます。
実際のママたちの体験談や、助産師からのアドバイスも交えながら、赤ちゃんの「泣き」と「欲しがる」のナゾに迫ります。
【総額7,660円OFFクーポン】【特典付き】
初回限定キャンペーンでお得にGETできる!
(画像引用:モグモ公式サイト)
「子どもが小さいうちは、仕事も家事も育児も全部フル回転。気づけば自分の時間はゼロ…」
「健康的なご飯を準備してあげたいけど、うまく時間を作れない…」
そんなママの一番の悩みは“毎日のごはん作り”ではないでしょうか。そんな時におすすめなのが『モグモ』です。
モグモは1歳半〜6歳向けの幼児食宅配サービスで、無添加で栄養バランスに優れた冷凍ごはんが届くため、冷凍庫にストックしておけばいつでも使えるので安心です。
- 保育園帰りで子どもが「お腹すいた!」と言っても、レンジで数分チンするだけ
- 献立に悩む時間がなくなる
- 子どもが食べやすい味付け・サイズだから、食べムラが減る
「今日は疲れてごはんを作りたくない…」「子供にも栄養バランスが整った食事を摂らせたい」そんなときに助けてくれるんです。
家族の食卓を無理なく支えながら、ママに“心のゆとり”を取り戻してくれるはずです。今なら全額返金保証付きで安心して試せるので、気軽に始めてみてくださいね!
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ![]()
新生児がミルクを飲んでも欲しがるのはなぜ?6つの理由!
「ミルクをしっかり飲ませたはずなのに、また欲しがって泣いている…」
新生児期によくあるこの悩みは、実は多くのママやパパが通る道です。赤ちゃんが“飲んだのに欲しがる”とき、そこにはいくつかの理由があります。ただ「足りていない」という単純な話ではなく、赤ちゃんの心と体の発達が大きく関係しているのです。
新生児は、まだ脳の中にある「満腹中枢(おなかいっぱいと感じるセンサー)」が未発達です。
そのため、お腹が満たされていても“飲みたい”という欲求が残ることがあります。
また、胃の容量も小さく、飲める量も限られているため、ちょっとした刺激(例えば抱っこをやめた、空気を飲み込んで苦しいなど)でも泣いてしまい、「もっと飲ませた方がいいのかな」と親は思いがちです。
赤ちゃんにとって“吸う”という行為は、単に「お腹を満たすため」だけでなく、心を落ち着かせるための行動でもあります。
ママのおっぱいを吸うときの感覚や、哺乳瓶の乳首を口に含んでいる感触は、新生児にとって非常に安心できるもの。お腹がいっぱいでも、不安・寂しさ・眠れないときに“吸いたい”という行動をとることがあります。
これは「非栄養的吸啜(ひえいようてききゅうてつ)」と呼ばれ、おしゃぶりや母乳をくわえることで安心を求める自然な行動です。
もちろん、ミルクの量が実際に足りていないケースもあります。特に以下のような兆候が見られる場合は、哺乳量の見直しが必要かもしれません。
-
飲んでもすぐに泣く・不機嫌になる
-
体重の増えが少ない(1日平均25〜30g以下)
-
1日の排尿回数が5回未満
-
毎回の授乳後に激しく泣く or 落ち着かない
新生児のミルクの量は、体重や月齢によって目安がありますが、赤ちゃんによって「必要量」は違います。親の判断だけで決めず、体重の増加ペースや排泄の状態などを総合的に見て調整することが大切です。
意外に多いのが「飲みすぎてしまい、かえってお腹が張って不快→泣く→また飲ませてしまう」という悪循環です。
赤ちゃんはミルクを吐く力が未熟で、飲みすぎても自分で止められない場合があります。たとえば、哺乳瓶の乳首の穴が大きすぎて、一気に飲んでしまっているケースもあります。
このような場合は以下のような兆候が出ることも。
-
ミルクを飲んだ後に頻繁に吐く
-
うなったり反り返ったりして苦しそうにする
-
おならやゲップがたくさん出る
「泣く=空腹」ではないことを覚えておくと、落ち着いて対応できます。
ミルクを飲んだあと、上手にゲップが出ないと、胃に空気がたまりやすくなります。すると、お腹が張って苦しくなり、その不快感で泣いてしまうこともあります。
それを親が「まだ足りてないのかも」と勘違いしてさらにミルクを与えると、ますますお腹が張ってしまう…という悪循環に陥ります。
授乳後はなるべく縦抱きで背中を軽くトントンしてゲップを出してあげるようにしましょう。個人差はありますが、ゲップを上手に出せるようになると、飲んだ後に泣く回数がぐっと減るケースもあります。
生後1週間、3週目、6週目、3ヶ月などのタイミングで、「成長スパート(growth spurt)」と呼ばれる時期があり、急激に食欲が増すことがあります。
こうした時期には、ミルクの間隔が短くなったり、飲んでもすぐに欲しがったりするのは自然なことです。
この時期は赤ちゃんの体も脳も一気に成長しているため、栄養をたくさん必要としています。成長スパートは数日〜1週間ほどで落ち着くことが多いので、あまり神経質にならず、赤ちゃんのサインを見ながら柔軟に対応してあげましょう。
新生児がミルクを飲んでも欲しがるのは、ごく自然な行動の一つです。そこには発達過程の問題、安心を求める行動、または実際の栄養不足など、さまざまな要因が隠れています。
大切なのは、「泣いている=ミルクをあげる」という短絡的な対応ではなく、赤ちゃんの表情・仕草・体重の増え方・排泄状態などを総合的に観察して対応すること。
心配なときは、ひとりで抱え込まずに助産師さんや小児科医に相談してみるのもおすすめです。
新生児がミルクを飲んで2時間・1時間で泣くのは異常ではない!
「さっきミルクを飲んだばかりなのに、1時間後にまた泣く…」
「新生児なのにミルクの間隔が3時間もたない」
こんな状況に悩んでいるママやパパは少なくありません。特に初めての育児では、マニュアル通りにいかない現実に「なにか異常なのでは?」と不安になる方も多いでしょう。
ですが、結論から言うと、新生児がミルクを飲んで1〜2時間で泣くのは、必ずしも異常ではありません。
それにはいくつかの理由があります。
育児書や病院で「3時間おきの授乳を目安にしましょう」と言われることが多いですが、この「3時間」はあくまで目安にすぎません。
赤ちゃんによってお腹の空くスピードや、消化のスピード、満足できる哺乳量などには個人差があります。そのため、
-
ミルクを飲んで2時間で泣く
-
飲んでも1時間でまた欲しがる
-
3時間持たない日が続く
という状況も決してめずらしいことではなく、正常な範囲です。
赤ちゃんが泣く理由は空腹だけではありません。以下のような要因でも泣くことがあります。
✅ 赤ちゃんが泣く主な理由
|
泣く理由 |
具体的な状況 |
|---|---|
|
空腹 |
ミルクが足りない・時間が経った |
|
不快感 |
おむつが濡れている、暑い、寒い |
|
寂しさ |
抱っこしてほしい、ママの匂いを感じたい |
|
眠たい |
眠いのに眠れない、寝ぐずり |
|
胃腸の不快感 |
ゲップが出ていない、便秘気味、お腹が張っている |
新生児は言葉で訴えられないため、どんな不快感も「泣く」で表現します。
ミルクをあげたばかりなのに泣くからといって、すぐに「またミルクを」と考えるのは早計かもしれません。
ミルクをあげるか迷ったときは、赤ちゃんの空腹サインをチェックしてみましょう。
✅ 空腹サインの例
-
口をパクパクさせる
-
指しゃぶりをする
-
舌を出したり口元を舐める
-
顔を左右に動かして何かを探すようなそぶり(ルート反射)
これらのサインが見られるときは、お腹が空いている可能性が高いと判断できます。ただし、これも個人差があり、泣く前に出ることもあれば、出ない赤ちゃんもいます。
「飲んでもすぐ泣く」「1時間ごとに欲しがる」場合、実際に哺乳量が足りていないこともあります。以下のような場合は、ミルクの量の見直しや、頻度の調整を検討しましょう。
✅ 見直しポイント
-
ミルクを飲み干すスピードが速すぎる(勢いよく飲んでいる)
-
飲み終わっても口をパクパクさせている
-
授乳後も不機嫌な様子が続く
-
体重の増え方がゆるやか(1日20g未満)
このような場合は、一度1回あたりの哺乳量を10〜20ml程度増やしてみる、または哺乳の間隔をやや詰めてみるなど、柔軟な対応が大切です。
逆に、「泣いてる=すぐミルク」と繰り返してしまうと、飲ませすぎによってお腹が張って苦しい→泣く→さらにミルクを与えるという悪循環に陥る可能性もあります。
飲ませすぎかどうかは、以下のような症状で判断できます。
✅ 飲ませすぎのサイン
-
授乳後によく吐く(口の端からあふれるように)
-
お腹がパンパンに張っている
-
授乳後すぐに激しく泣き始める
-
うんちが緩くなりすぎている
こうした症状があれば、哺乳量が適切かどうかを再確認しましょう。乳首のサイズが大きすぎて一気に飲んでしまっている場合もあります。
多くのママパパが誤解してしまうのが、「3時間ごとに授乳できていない=自分の育児が間違っているのでは」という不安です。
でも、新生児は本当に十人十色。1時間半ごとに飲みたがる子もいれば、3時間ぐっすり寝てしまう子もいます。間隔が空かないこと自体を“異常”と決めつけないようにしましょう。
育児本やアプリで「この通りじゃない」と悩むより、目の前の赤ちゃんのペースに合わせることが何より大切です。
困ったときはプロに相談を
どうしても判断に迷うときは、助産師さんや小児科の先生に相談してみましょう。体重の増え方や哺乳の様子を見ながら、その子に合ったミルク量・授乳間隔をアドバイスしてもらえるはずです。
新生児がミルクを飲んでから1時間、2時間で泣くことは、決して珍しいことではありません。お腹が空いているだけでなく、不快・不安・眠れないなど、さまざまな理由があります。
「マニュアル通りの育児」にとらわれすぎず、赤ちゃんの様子をよく観察しながら、臨機応変に対応してあげることが大切です。
生後1〜2ヶ月で飲んでも飲んでも欲しがる理由と対策
生後1〜2ヶ月頃の赤ちゃんが「飲んでも飲んでも欲しがる」というのは、多くのママ・パパが直面する育児の悩みです。とくに夜中や授乳後すぐにまた欲しがる様子を見ると、「足りていないのでは?」「異常なの?」と不安になってしまいますよね。
この時期の赤ちゃんがミルクを頻繁に欲しがるのには、いくつかの明確な理由があります。そして、心配しすぎなくても大丈夫なことも多いんです。
生後1〜2ヶ月は、赤ちゃんの「成長スパート(growth spurt)」が起こるタイミングとされています。これは急激に体と脳が発達する時期で、通常よりも多くの栄養を必要とするため、ミルクの量や頻度が一時的に増えるのです。
よくあるタイミングは以下のとおりです:
-
生後3週目ごろ
-
生後6週目ごろ
-
生後2ヶ月ごろ
この期間は、普段よりもミルクを欲しがる頻度が上がり、飲んでも飲んでも足りないように見えることがあります。ただし、これは数日〜1週間程度で落ち着くことがほとんどです。
生後1〜2ヶ月になると、赤ちゃんは少しずつ「ママがいないと寂しい」「抱っこされたい」という感情を持ち始めます。その結果、お腹が空いていなくても、安心するためにミルクを欲しがるようになることがあります。
ミルクを飲む=ママとつながっている時間
という感覚が芽生え始めるこの時期には、母乳でもミルクでも“吸う”こと自体が安心につながっている可能性があるのです。
生後間もない赤ちゃんには「吸啜反射(きゅうてつはんしゃ)」という、生きるために備わった本能的な動きがあります。これは、口に触れたものを吸うという反射行動で、月齢が低いうちはとても強く出ます。
そのため、お腹がいっぱいでも口をくわえたがる・吸いたがるという行動をよく見せるのです。この反射は生後2〜4ヶ月ごろから少しずつ弱まってきます。
赤ちゃんが飲んでもすぐ欲しがるとき、やはり「足りていないのでは?」と不安になりますよね。そんなときは、次のポイントでミルク量が適切かどうかを確認してみましょう。
✅ 哺乳量が足りているか確認するポイント
-
体重が順調に増えている(1日25〜30gが目安)
-
おしっこが1日5〜6回以上出ている
-
うんちが1日1〜2回は出ている(母乳寄りだともっと多くてもOK)
-
機嫌がよく、泣いたあとに落ち着く
これらを満たしていれば、ミルクは足りている可能性が高いです。
反対に、「飲ませすぎ」で赤ちゃんが苦しんで泣いている場合もあります。飲みすぎかどうかは、以下のサインでチェックできます。
✅ 飲みすぎサイン
-
よく吐く(特に授乳直後に噴水のように)
-
げっぷが出にくく、うなって苦しそう
-
体重の増え方が急すぎる(1日40g以上)
-
お腹がパンパンに張っている
こうした様子がある場合は、一度に飲む量を少し減らす or ゆっくり時間をかけて飲ませるなどの調整をしてみてください。
もし「吸いたい」欲求が強くて泣いているようなら、おしゃぶりを使うことも一つの方法です。おしゃぶりには賛否ありますが、赤ちゃんの気持ちを落ち着かせるのに効果的な場合があります。
ただし、おしゃぶりに頼りすぎないようにし、あくまで一時的な安心材料として活用しましょう。
赤ちゃんがミルクを欲しがるのは、“ママに抱っこされて安心したい”という気持ちの表れであることも多いです。そういうときは、ミルクを追加で与えるのではなく、以下のような方法も有効です。
-
抱っこして背中をトントン
-
肌と肌を触れ合わせる(スキンシップ)
-
やさしく話しかける
-
部屋の明かりや音を調整して落ち着ける環境にする
こうした方法で、飲まなくても安心できる体験を増やすことも、赤ちゃんの情緒安定につながります。
哺乳瓶の乳首のサイズが赤ちゃんに合っていない場合、飲むスピードが早すぎて満腹感が追いつかないことがあります。
目安としては、哺乳に10〜15分程度かかるのが適切とされています。あまりに短時間で飲み終わってしまう場合は、乳首のサイズを一段階落としてみるのもおすすめです。
生後1〜2ヶ月の赤ちゃんが「飲んでも飲んでも欲しがる」のは、成長スパートや心の発達、吸いたい欲求など、さまざまな要因が重なっている自然な行動です。
大切なのは、「また欲しがってる=ミルクを足さなきゃ」と考えるだけでなく、赤ちゃんが安心できる方法をいくつか試してみることです。
飲みすぎを防ぎつつ、赤ちゃんの心と体に寄り添ってあげることで、きっと少しずつ落ち着いてくれるはずですよ。

(画像引用:モグモ公式サイト)
共働きで毎日バタバタのわが家。夕飯作りはどうしても「時短」「手軽」重視になりがちで、栄養バランスに不安を感じていました。
そんなときに知ったのが【mogumo】。
管理栄養士監修・無添加で安心できる上、冷凍庫から出してレンジで温めるだけ。
最初は「子どもが食べてくれるかな?」と半信半疑でしたが、思った以上に完食してくれて驚きました。
野菜も入っていて栄養も取れるし、罪悪感もゼロ。
ママの“心のゆとり”を取り戻してくれるサービスだと思います。
>>mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ
母乳でもずっと欲しがって寝ないときの考えられる原因
「母乳をあげてもすぐ泣く」「ずっと吸っていたがる」「寝たと思って布団に置くとまた起きて泣く」――こんな状態が続くと、ママは肉体的にも精神的にも限界を感じてしまいますよね。
特に夜中に何度も起きて「寝ない・泣く・吸いたがる」のループに入ると、「私の母乳が足りていないのでは…?」と自己嫌悪になることもあるかもしれません。
でも安心してください。母乳育児でも赤ちゃんがずっと欲しがるのは、決してママのせいではなく、赤ちゃん側の理由や成長による自然な行動であることがほとんどなのです。
産後間もない時期は、ママの母乳の分泌量が安定するまでに数週間かかることが一般的です。特に生後1ヶ月未満の赤ちゃんは、授乳回数も多く、吸っても満足できない状態が続くことがあります。
また、母乳の出始め(前乳)は水分が多くてサラッとしており、後乳(脂肪分の多い母乳)をしっかり飲まないと満腹感が得られないとも言われています。頻回授乳はその後乳を引き出すためにも必要な過程です。
赤ちゃんは、生理的な空腹だけでなく、「吸いたい」という欲求によっても母乳を求めます。これを「非栄養的吸啜(ひえいようてききゅうてつ)」と呼びます。
ママの胸の匂いやぬくもり、心音に包まれることで安心感を得ようとして、本当はお腹はいっぱいだけど、精神的な安心のために吸いたがるのです。特に夜間はその傾向が強まります。
赤ちゃんは眠たくなると、自力でスッと眠ることができず、**逆に興奮して泣いてしまう「寝ぐずり」**を起こすことがあります。
このとき、ママのおっぱいをくわえることでリラックスし、眠りに落ちようとしているケースが多いです。眠いけれど不安、体がうまく力を抜けない、という状態のときに**「吸う」という行為が自己安定の手段**になるのです。
「おっぱいを飲みながら寝たのに、布団に置くと起きて泣く」という現象、経験があるママも多いのではないでしょうか。
これは赤ちゃんの“環境の変化”に敏感な性質によるものです。ママの腕の中は、温かくて、揺れがあって、安心感に包まれていますが、布団の上は静かでひんやりして、孤独感が強くなりがち。
眠りが浅いタイミングで環境が変わると、目が覚めて「不安!吸いたい!」と感じて泣いてしまうことがあります。
生後3週・6週・2ヶ月などの時期に現れる**成長スパート(急激な発達)**では、赤ちゃんの食欲も急激に増加します。
この時期は、母乳でも「飲んだのにまた欲しがる」「飲んでも寝ない」ということが多くなりますが、一時的なもので数日〜1週間ほどで落ち着くことがほとんどです。
赤ちゃんが頻繁に吸うことでママの母乳の分泌も促されるため、母乳育児においては必要なプロセスでもあります。
赤ちゃんが“吸いたい”気持ちが強い場合は、おしゃぶりの活用もひとつの方法です。
ただし、おしゃぶりは赤ちゃんによって好き嫌いが分かれますし、早期から常用すると母乳育児に影響が出るという指摘もあります。そのため、以下のような代替スキンシップも有効です。
-
ママの胸の上で添い寝(添い乳)
-
おくるみでくるんで安心感を
-
やさしく語りかける、歌う
-
抱っこひもで密着
“おっぱい以外の安心手段”を持たせることは、ママの体力温存にもつながります。
「頻回に泣いて起こされてヘトヘト…」というママには、添い乳という方法が役立つことがあります。
これはママが横になった状態で赤ちゃんにおっぱいをあげる方法で、赤ちゃんが寝たあともママがそのまま休めるのが最大の利点です。
ただし、安全面には注意が必要で、
-
柔らかすぎる布団や枕は避ける
-
赤ちゃんの顔が覆われないようにする
-
ママが寝落ちしすぎないよう環境を整える
などの対策をしながら行うことが大切です。
「母乳だけで寝ない」「ずっと欲しがる」ことで、ママが心身ともに疲弊している場合は、一時的にミルクを併用する混合育児を検討しても良いでしょう。
ミルクは消化に時間がかかるため、睡眠がまとまる傾向があるという特徴があります。夜だけミルクを追加してママが休める時間を確保するのも、赤ちゃんにとっても良い育児です。
母乳でも「ずっと欲しがる」「寝ない」という現象は、赤ちゃんの自然な欲求や成長、安心を求める気持ちからくるものがほとんどです。
決して「母乳の出が悪い」「育て方が悪い」わけではありません。ママ自身が無理をしすぎず、赤ちゃんに合った方法+ママにやさしい育児スタイルを見つけていくことが、赤ちゃんの安心と成長に大きくつながります。
ミルクの適切な間隔・量・泣いたときの対応まとめ
「結局どれくらいの間隔で、どれだけ飲ませればいいの?」「泣いたら毎回ミルクをあげていいの?」と疑問に感じるママやパパも多いでしょう。
ここでは、新生児〜生後2ヶ月ごろまでの赤ちゃんにとって、目安となるミルクの間隔や量、泣いたときの対応方法をまとめてご紹介します。
赤ちゃんの月齢が低いうちは、胃が小さく、1回に飲める量も少ないため、頻回の授乳が必要です。
一般的には以下のような目安が紹介されています。
|
月齢 |
授乳の間隔 |
1回あたりのミルク量 |
|---|---|---|
|
新生児(0〜1ヶ月) |
2〜3時間おき(1日7〜8回) |
80〜120ml程度 |
|
生後1〜2ヶ月 |
3時間おき(1日6〜7回) |
120〜160ml程度 |
ただし、これはあくまで一般的な目安であり、赤ちゃんによって差があります。「うちは2時間もたない…」という場合でも、それがその子のペースであれば問題ありません。
赤ちゃんが泣いたとき、必ずしも「空腹」とは限りません。次のような流れで様子を確認してみましょう。
泣いたときのチェックリスト
-
おむつが汚れていないか?
-
暑すぎ・寒すぎではないか?
-
抱っこやスキンシップで落ち着くか?
-
空腹サインが出ているか?(口をパクパク、手をしゃぶるなど)
これらを確認したうえで、明らかに空腹のサインが見られるときにはミルクを追加してOKです。
泣くたびにミルクを足していると、知らず知らずのうちに「飲ませすぎ」になってしまうことも。以下の点に注意してみましょう。
-
哺乳瓶の乳首サイズを適切に(流量が多すぎると早飲みしてしまう)
-
時間をかけてゆっくり授乳(10〜15分かける)
-
ミルク後の様子を観察(お腹の張り、吐き戻しなど)
もし「吐く」「うなる」「お腹がパンパン」などのサインが見られた場合は、量や間隔の調整を検討しましょう。
-
授乳後すぐに激しく泣く
-
体重の増加が少ない
-
ミルクを飲みすぎて吐くことが多い
-
日中もぐずりが続く
こうした場合は、小児科や助産師に相談してみてください。体重や生活リズムを見ながら、その子に合ったアドバイスをしてもらえます。
ミルクの量や間隔には目安がありますが、**一番の基準は“赤ちゃんの様子”**です。
-
よく飲み、よく眠り、体重が増えていればOK
-
間隔や回数に縛られず、赤ちゃんの個性に合わせて
-
ママやパパが無理せず育児できるスタイルを大切に
「泣いた=ミルク」と反射的に対応するのではなく、赤ちゃんのサインをよく観察して“今、本当に必要なこと”を見極めていくことが、育児においてとても大切です。
先輩ママの体験談・知恵袋の声
新生児期の育児は、とにかく不安と疑問の連続です。
特に「ミルクを飲んでもすぐ欲しがる」「何をしても泣き止まない」といった悩みは、夜中に一人で抱え込むとどんどん辛くなってしまいますよね。
でも、同じような経験をしているママ・パパはたくさんいます。
ここでは、実際に「飲んでも欲しがる赤ちゃん」に悩んだ先輩ママたちの声を、知恵袋やSNS、育児ブログなどから集めてご紹介します。
生後3週のころ、1時間半おきにミルクを欲しがるようになって「足りてないのかな?」と不安に。助産師さんに聞いたら「そのくらいの時期は成長スパートでよくある」と言われてホッとしました。結局、1週間くらいで自然に落ち着きました。
最初は泣くたびにミルクを足していたけど、飲んでも泣いてることに気づき「本当にお腹すいてる?」と考えるように。空腹サインをチェックして、そうじゃない時は抱っこやおしゃぶりで対応。赤ちゃんも自分も気持ちがラクになりました。
母乳オンリーで頑張っていたけど、夜中の頻回授乳が辛すぎて。思い切って夜だけミルクに変えてみたら、赤ちゃんがよく寝てくれて、私も睡眠がとれるようになりました。無理に完母にこだわらなくていいんだなと実感しました。
『新生児 ミルク飲んでも泣く』で検索しまくって、育児知恵袋の投稿を読んで「うちも一緒!」「私だけじゃないんだ」と涙が出ました。夜中の孤独が少し救われた気がしました。
ずっと泣かれるのがストレスで「母乳が足りてないのかな…」と自信をなくしていた私に、助産師さんが「赤ちゃんは泣いていろんなことを教えてくれるのよ。泣かせてもいいの」と言ってくれて、気持ちがとても軽くなりました。
-
「飲んでも欲しがる」時期は意外と多くのママが経験している
→ 自分だけじゃないことを知るだけで、気持ちが楽になります。
-
泣いたら=ミルクではなく、赤ちゃんのサインを観察することが大事
→ 空腹だけでなく、不安や眠気、スキンシップ不足の可能性も。
-
育児スタイルは柔軟に。混合育児・添い乳・おしゃぶりも“あり”
→ 完璧を目指さず、「楽にできるやり方」が一番。
「飲んでも欲しがる」「寝てくれない」「ミルクの間隔がもたない」――これらの悩みは、育児中の誰もが一度は通る道です。そして多くの先輩ママ・パパが、それぞれのやり方で乗り越えてきました。
赤ちゃんもママもひとりひとり違うからこそ、“正解”は一つではありません。体験談を参考にしながら、赤ちゃんにとってもママにとっても負担の少ない方法を、焦らずゆっくり見つけていきましょう。

(画像引用:モグモ公式サイト)
「今日のごはん、どうしよう…」
仕事から帰ってきて、保育園から子どもを迎えて、買い物して、夕飯を作って…毎日そんな繰り返しに疲れていませんか?
そんな忙しいママにおすすめなのが、幼児食宅配サービス mogumo(モグモ)。
1歳半〜6歳の子ども向けに、管理栄養士が考えた無添加・冷凍のおかずをお届けしてくれるんです。
✔ レンジでチンするだけ、調理はほぼゼロ!
✔ 栄養バランスもバッチリで偏食対策にも◎
✔ 忙しい夕食時に“あと1品”としても使える
「子どもがパクパク食べてくれる」だけで、ママの心もぐっと軽くなりますよ。
毎日の食事作りを少しラクにして、子どもと笑顔で過ごす時間を増やしてみませんか?
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ をタップ
をタップ

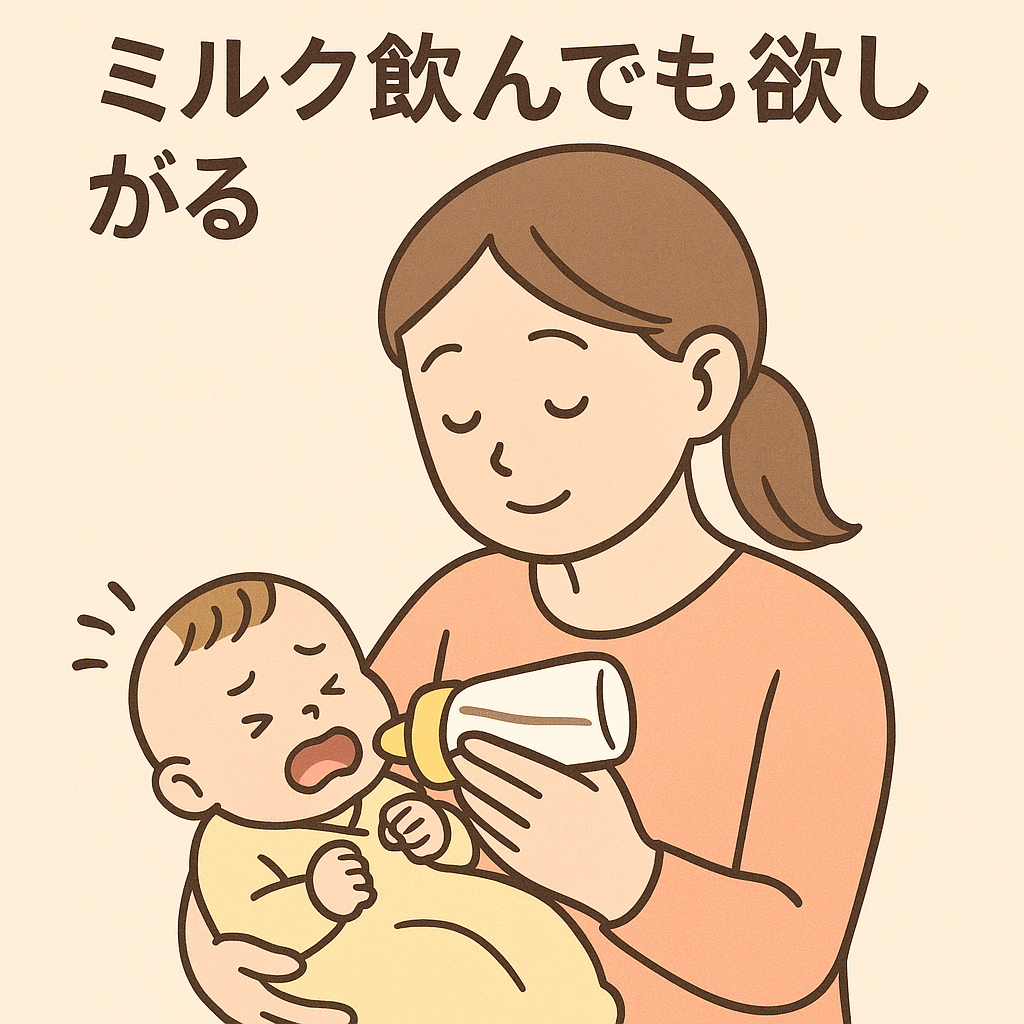





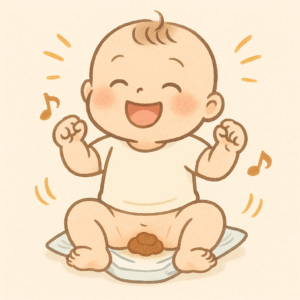


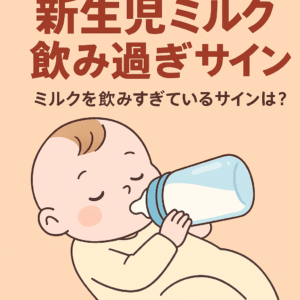
コメント