赤ちゃんが泣くたびに「お腹がすいたのかな?」とミルクを用意していませんか?
特に新生児期は授乳のリズムが安定しないため、「どれくらいあげればいいの?」「飲ませすぎてないかな?」と不安になるママやパパも多いはず。
実は、ミルクの“飲みすぎ”は赤ちゃんにとっても負担になることがあります。
吐き戻しや便の変化、機嫌の悪さなど、見逃しやすいサインも存在します。
この記事では飲ませすぎの見極め方や対処法をわかりやすく解説。さらに、混合育児や母乳育児での注意点、赤ちゃんが「まだ欲しがる」ときの対応まで、よくある疑問をまとめました。
「赤ちゃんにとってちょうどいい量って?」「これって飲ませすぎ?」と悩むすべての育児中の方に役立つ情報をお届けします。
【総額7,660円OFFクーポン】【特典付き】
初回限定キャンペーンでお得にGETできる!
(画像引用:モグモ公式サイト)
「子どもが小さいうちは、仕事も家事も育児も全部フル回転。気づけば自分の時間はゼロ…」
「健康的なご飯を準備してあげたいけど、うまく時間を作れない…」
そんなママの一番の悩みは“毎日のごはん作り”ではないでしょうか。そんな時におすすめなのが『モグモ』です。
モグモは1歳半〜6歳向けの幼児食宅配サービスで、無添加で栄養バランスに優れた冷凍ごはんが届くため、冷凍庫にストックしておけばいつでも使えるので安心です。
- 保育園帰りで子どもが「お腹すいた!」と言っても、レンジで数分チンするだけ
- 献立に悩む時間がなくなる
- 子どもが食べやすい味付け・サイズだから、食べムラが減る
「今日は疲れてごはんを作りたくない…」「子供にも栄養バランスが整った食事を摂らせたい」そんなときに助けてくれるんです。
家族の食卓を無理なく支えながら、ママに“心のゆとり”を取り戻してくれるはずです。今なら全額返金保証付きで安心して試せるので、気軽に始めてみてくださいね!
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ![]()
そもそも新生児のミルク量はどれくらいが適量?
新生児の育児で最も多く寄せられる疑問のひとつが、「ミルクの適量はどれくらいか?」というものです。
赤ちゃんは言葉で伝えることができないため、泣く=空腹と感じてついミルクを用意してしまいがち。
しかし、必ずしも「泣く=お腹がすいている」とは限らず、飲ませすぎてしまう原因にもつながります。
生後0〜1ヶ月の新生児は、体重1kgあたり1日150ml前後のミルクが必要とされています。
たとえば、体重3kgの赤ちゃんなら1日に約450ml。これを8回に分けて与えると、1回あたり約50〜60mlが目安になります。
ただし、これはあくまで目安であり、赤ちゃんによって飲む量には個人差があります。
吸う力が強い子、すぐ疲れて飲むのをやめてしまう子など、それぞれのリズムを見ながら調整することが大切です。
新生児期の赤ちゃんがミルクを飲んだ後にも泣いたり、哺乳瓶を探すようなそぶりを見せると、「足りていないのでは?」と心配になる親御さんも多いでしょう。
しかし、これは単に「吸いたい」という本能的な欲求であることが多く、必ずしも空腹によるものとは限りません。
特に新生児は、口を動かすことで安心感を得る「吸啜反射(きゅうてつはんしゃ)」が強く働いており、ミルクが出なくても吸いたいという欲求を示すことがあります。
また、「寝ぐずり」「抱っこされたい」「おむつが不快」など、別の理由で泣いている可能性もあります。
赤ちゃんがミルクを飲んだあと、すぐにまた欲しがるように見えても、以下のポイントをチェックしてから与えることが大切です。
-
直前にどれくらい飲んだかを記録しておく
-
満腹サイン(口を閉じる、吸いつかない、手足の動きが緩やかになるなど)を観察する
-
泣いている理由が他にないかを考えてみる
特に完ミ育児や混合育児では、「母乳に比べて消化が遅い」とされるミルクを続けてあげすぎると、胃腸に負担をかける恐れがあります。
新生児のミルク量には目安がありますが、それ以上に大切なのは「赤ちゃんの様子を見ること」です。
泣くたびにミルクをあげるのではなく、その泣き方や飲み方、満腹のサインをしっかり観察することで、飲みすぎを未然に防ぐことができます。
新生児がミルクを飲みすぎているサインとは?見極める4つのサイン!
赤ちゃんにとって栄養を摂る手段は「母乳」か「ミルク」だけ。
そのため、つい「いっぱい飲んでくれると安心」と思いがちですが、実は飲ませすぎが原因で赤ちゃんの体に負担をかけてしまうこともあるのです。
では、どのようなサインが「飲みすぎ」の兆候なのでしょうか?ここでは、ミルクの飲みすぎを見極めるためのポイントを詳しく解説します。
もっともわかりやすいサインが「吐き戻し」です。赤ちゃんの胃はまだ未発達で、入り口の筋肉も弱いため、少しの刺激でもミルクが逆流しやすくなっています。軽い吐き戻しは新生児期にはよくあることですが、以下のようなケースは飲ませすぎが原因かもしれません。
-
1回の哺乳で大量に吐く
-
毎回のように吐き戻す
-
苦しそうに吐く、顔を赤くしてむせる
特に、哺乳後すぐに勢いよく吐いたり、げっぷをしないまま寝かせて吐く場合は、ミルクの量や飲み方を見直す必要があります。
ミルクを飲みすぎると、赤ちゃんのお腹がパンパンに張ることがあります。お腹が膨れていて、触ると硬く、ガスがたまっているような場合は要注意。また、以下のような仕草も飲みすぎのサインかもしれません。
-
お腹を触ると嫌がる
-
足をバタバタさせる
-
苦しそうに顔をしかめる
-
いきんだり唸ったりする
このような症状は、胃腸に負担がかかっている状態を示しています。
ミルクを多く飲みすぎると、消化不良を起こして下痢のような便が出ることがあります。特に人工乳は母乳に比べて脂質やタンパク質が多いため、過剰になると未消化物が排出されやすくなります。
-
水っぽい便が頻繁に出る
-
においが強い・泡立っている
-
便の色が白っぽい、または黄緑がかっている
このようなうんちが続く場合は、小児科で相談してミルクの量や回数を調整したほうがよいでしょう。
赤ちゃんは満腹で満たされると、自然とリラックスして眠ったり穏やかな表情を見せます。
しかし、飲みすぎたときには逆に不快感から機嫌が悪くなることも。
以下のような変化があれば、飲みすぎを疑いましょう。
-
哺乳後にグズグズ泣く
-
うまく寝つけない、すぐ起きる
-
表情が険しい、眉間にしわを寄せる
赤ちゃんが「もっと飲みたい」と泣くと、足りないと思いがちですが、実際は「気持ち悪い」「お腹が苦しい」といった不快感から泣いていることもあります。
生後1ヶ月になると、飲む量が増えてくるため、「しっかり飲んでくれてよかった」と思いがちです。
しかし、胃の容量には限界があるため、1回で120ml以上など過剰に与えると飲みすぎになる可能性があります。
この時期は赤ちゃん自身の哺乳リズムが整ってくる一方で、欲しがる素振りだけに惑わされると、知らないうちに負担をかけてしまうことがあります。
1回量と授乳間隔、そして赤ちゃんの体重増加のペースなどを総合的に見て判断することが重要です。
ミルクをどれくらい飲ませるかに正解はありません。ただ、以下のチェックリストを参考にしながら観察してみてください。
- 哺乳後にすぐ吐かないか?
- お腹の張りや不快そうな仕草はないか?
- うんちの回数や状態が急に変わっていないか?
- 機嫌や睡眠に影響が出ていないか?
これらの項目のうち、複数が当てはまるようであれば、ミルクの量を少し減らしてみる、あるいは小児科で相談してみると安心です。
ミルクを飲みすぎたときの「うんち」でわかる兆候
赤ちゃんのうんちは、健康状態を知るための大切なバロメーター。
特に新生児期は、母乳やミルクの量や内容がうんちにダイレクトに影響します。
「いつもと違ううんちが出た」「ミルクをたくさん飲んだあとに下痢っぽくなった」など、気になる変化があれば、ミルクの飲みすぎが関係している可能性もあります。
ここでは、ミルクの飲みすぎがうんちにどんなサインとして現れるのかを詳しく解説します。
まずは、ミルクや母乳を飲んでいる新生児のうんちの正常な状態を知っておきましょう。
-
回数:1日5〜8回ほど(母乳育児の方が回数は多くなりがち)
-
色:黄色~黄褐色。母乳はマスタード色に近いことが多い
-
形状:やわらかめでペースト状、やや水っぽい
-
におい:あまり強くない、甘酸っぱいにおい
この範囲内であれば特に問題はありません。
ミルクを飲みすぎた場合、消化機能が追いつかず、うんちにさまざまなサインが現れることがあります。
以下のような特徴に当てはまる場合は、飲ませすぎを疑ってみましょう。
1.水っぽく回数が多い=下痢気味に
ミルクを過剰に飲んでしまうと、胃腸が未熟な新生児はきちんと吸収できず、そのまま排出されてしまうことがあります。
その結果、うんちが非常に水っぽくなったり、1日に10回以上出るようになることも。
また、白っぽい膜や泡立ちがある便は、未消化の脂質や糖質が多く含まれているサインです。
特に人工乳は母乳に比べて消化しにくいため、こうした状態が続く場合は注意が必要です。
2.においが強くなる・酸っぱいような発酵臭がする
普段はそれほど強くない赤ちゃんのうんちですが、飲みすぎが原因で腸内のバランスが崩れると、便が発酵して酸っぱいようなにおいが出ることもあります。
これは、腸内に未消化の糖分が残ることで細菌が繁殖し、ガスが発生するためです。発酵臭がある便が何日も続く場合は、腸に負担がかかっている可能性があります。
3.黄緑色や白っぽい色になる
通常は黄色〜黄土色の便が、飲みすぎにより消化吸収が追いつかないと、黄緑がかった色や白っぽくなることがあります。
黄緑色の便は胆汁の流れが速くなりすぎたときに見られることが多く、白っぽい便は脂肪の未消化によるものです。
このような色の変化が一時的でなく、何日も続くようであれば、一度ミルクの量を見直すか、小児科を受診するのが安心です。
便秘にも要注意
意外かもしれませんが、ミルクの飲みすぎで「便秘」になる赤ちゃんもいます。これは胃腸に負担がかかり、腸の動きが鈍くなるため。以下のようなサインがあれば、ミルクの量が適切かどうかチェックしてみましょう。
-
2〜3日うんちが出ない
-
お腹が張って苦しそうにしている
-
うんちがコロコロして硬い
-
排便時に泣き叫ぶほど痛がる
便秘が続くと、赤ちゃんの機嫌が悪くなったり、夜泣きの原因にもなることがあります。
ミルク量の調整と様子観察が大切
うんちに異常が見られたときは、以下のような点を見直しましょう。
-
1回量が多すぎていないか?(適量かどうか哺乳記録をチェック)
-
授乳間隔が短すぎていないか?(2〜3時間あけているか)
-
ミルクの濃度が適切か?(粉ミルクの調合ミスがないか)
-
飲んでいるスピードが早すぎないか?(哺乳瓶の乳首のサイズを見直す)
また、うんちの状態や回数を記録しておくと、医師に相談する際にもスムーズです。
体重の増え方や全身の様子とあわせて、うんちからも赤ちゃんの健康状態を読み取っていきましょう。
母乳や混合育児でも「飲みすぎ」はある?
ミルク育児の場合は、哺乳量が目に見えるため「飲みすぎ」が話題になりますが、母乳育児や混合育児の場合でも飲みすぎは起こるのでしょうか?答えは「はい、起こり得ます」。
特に混合育児では、母乳とミルクのバランスが難しく、知らず知らずのうちにミルクを足しすぎていた、というケースも珍しくありません。
ここでは、母乳育児や混合育児における飲みすぎのリスクや見分け方、上手な調整方法について解説します。
一般的に、母乳は赤ちゃん自身が「必要な分だけ飲む」ことができるため、飲みすぎは起こりにくいとされています。母乳は哺乳瓶と違って飲み出すのに力が必要で、飲む量のコントロールも自然と身につくからです。
しかし、以下のようなケースでは母乳でも飲みすぎになることがあります。
-
母乳の出が非常によく、勢いが強い
-
長時間の授乳を頻繁に繰り返している
-
吸啜反射が強く、満腹でも吸い続ける
特に新生児期は「お腹がすいているわけではないけど、吸いたい」という欲求が強いため、欲しがるままに与えていると、結果的に飲みすぎにつながることがあります。
母乳は量が見えないため、「飲みすぎかどうか」を判断するのは難しいですが、以下のような兆候が見られる場合は、母乳の量が赤ちゃんの胃腸にとって負担になっている可能性があります。
-
吐き戻しの回数が多い
-
授乳後に機嫌が悪くなる
-
お腹がパンパンに張っている
-
授乳後でも泣き続ける、興奮して眠らない
-
下痢・泡立つうんち・回数の増加
特に「げっぷがうまく出ていない」「授乳のたびに苦しそう」といった様子があれば、飲みすぎを疑ってみてもよいでしょう。
混合育児では「母乳で足りていないかも」という不安から、ミルクを余分に足してしまう傾向があります。
例えば、母乳を飲んだあとに毎回100ml以上のミルクを足している場合、それが習慣化すると飲みすぎに。
また、「母乳がどれくらい出ているかわからない」ために、ミルクを多めに与えて安心しようとする心理も働きやすくなります。その結果、以下のような状態になることがあります。
-
ミルクを飲んだ直後に吐く
-
授乳後、泣き止まずにさらに与える → さらに飲みすぎ
-
夜中も何度もミルクを足してしまう
-
一日に必要な総量を大きく上回る量を与えている
混合育児では、母乳を基本にして「必要な分だけミルクを補う」という意識が大切です。以下のポイントを押さえると、飲みすぎを防ぎやすくなります。
-
母乳を十分吸わせたあとに、様子を見てミルクを足す
→ 赤ちゃんが満足していれば無理に足さなくてもOK
-
1回量を多くしすぎず、50〜80ml程度から試す
→ 赤ちゃんの反応を見ながら量を調整する
-
体重の増加具合をチェックする(1日30g前後が目安)
→ 増えすぎる場合はミルクを控える調整を
-
母乳がどれくらい出ているかを助産師や小児科でチェックしてもらう
→ 母乳育児相談室の活用もおすすめ
「まだ欲しがるからあげるべき?」「もう十分飲んでる?」と迷うときは、以下のような視点で判断してみましょう。
- 哺乳後すぐに吐いたり、不快そうな様子はないか
- 睡眠時間は確保できているか(飲みすぎると逆に眠れないことも)
- 排泄のリズムが極端に変化していないか(下痢・便秘)
- 授乳直後に毎回ミルクを足していないか
不安なときは、助産師や保健師に相談することで、必要以上にミルクを足しすぎるリスクを減らすことができます。
母乳でも混合でも、「赤ちゃんが欲しがる=足りない」とは限りません。
赤ちゃんの満腹サインや様子を丁寧に観察し、安心のためにミルクを足しすぎないよう意識することが大切です。見えないからこそ、不安になりやすい母乳育児。
でも、その不安が“あげすぎ”を生まないよう、日々の変化を見守りながら調整していきましょう。
1ヶ月の赤ちゃんのミルク量、どこが「飲みすぎ」ライン?
生後1ヶ月を迎える頃、赤ちゃんの成長は目覚ましく、授乳リズムや飲む量も変化してきます。
「ミルクをぐんぐん飲むようになった!」と嬉しくなる反面、「飲みすぎていないかな?」と心配になる時期でもあります。
ここでは、生後1ヶ月の赤ちゃんにとっての「適量」と「飲みすぎライン」の目安、見極めのポイントを詳しく解説します。
生後1ヶ月の赤ちゃんは、1回の授乳でおよそ100ml〜140ml程度のミルクを飲むのが一般的です。
1日に6〜8回の授乳で、トータル600〜1,000mlが目安とされています。
ただし、赤ちゃんの体重によっても適切なミルク量は異なります。目安としては、体重1kgあたり1日150ml前後を基準にするとよいでしょう。
【例】体重4kgの赤ちゃんの場合
→ 4kg × 150ml = 600ml/日が基準
これを1日7回の授乳で分けると、1回あたり約85ml程度が適量となります。
では、どこからが「飲みすぎ」なのでしょうか?赤ちゃんは一時的にたくさん飲むこともありますが、以下のような状態が続くようであれば、“飲ませすぎ”の可能性があります。
一日の総量が体重基準を大きく超えている
体重に対して必要以上のミルク量を日常的に与えていると、胃腸への負担が大きくなります。
授乳間隔が短すぎる
通常は2.5〜3時間おきの授乳が推奨されていますが、1〜2時間おきに頻回授乳をしている場合、胃が休まらず、逆に不快感や吐き戻しにつながることがあります。
毎回の哺乳量が140mlを超えている
ミルク育児では1回に与える量が増えがちですが、生後1ヶ月で150mlを何度も与えるのは過剰なケースもあります。
生後1ヶ月の赤ちゃんは、消化機能も発達途上のため、過剰なミルク摂取はさまざまな不調の原因となります。
-
吐き戻しが頻繁になる
-
お腹が張って苦しそうにする
-
下痢や便秘など、排泄リズムが乱れる
-
夜泣きや睡眠の質の低下
-
必要以上に体重が増える(1日50g以上の増加が続く)
体重の増加は一見「順調」と思われがちですが、急激な増加は将来の肥満リスクや内臓への負担を引き起こす可能性もあるため注意が必要です。
1ヶ月頃の赤ちゃんは、吸いたい欲求(口唇欲求)が非常に強く、「吸う=飲みたい」と見られてしまいがちです。
しかし、実際には以下のような原因で泣いているだけのことも多いのです。
-
寝ぐずりしている
-
抱っこしてほしい、寂しい
-
おむつが気持ち悪い
-
眠たいけどうまく眠れない
このような場合にミルクを与えてしまうと、飲みすぎの悪循環に陥ってしまいます。
赤ちゃんが泣いたときはまず、ミルク以外の原因を探ってみることも大切です。
生後1ヶ月の赤ちゃんにおいて飲みすぎを防ぐためには、以下のような方法が役立ちます。
-
哺乳のペースをゆっくりにする(休憩をはさむ)
-
乳首のサイズを見直す(流量が多すぎると飲みすぎに)
-
飲んだ量・時間・排便などを記録して把握する
-
欲しがる時に毎回あげるのではなく、抱っこやスキンシップで対応する
これらの工夫をすることで、赤ちゃんの様子に合わせた適量の授乳がしやすくなります。
生後1ヶ月の赤ちゃんは、飲む量も欲求もどんどん強くなっていきますが、ミルクの「飲みすぎ」には注意が必要です。
適量の範囲を超えると、体に負担がかかるだけでなく、吐き戻しや下痢などの不調につながることも。
赤ちゃんの様子や排泄、体重の増え方をよく観察しながら、必要に応じて量を調整していきましょう。

(画像引用:モグモ公式サイト)
共働きで毎日バタバタのわが家。夕飯作りはどうしても「時短」「手軽」重視になりがちで、栄養バランスに不安を感じていました。
そんなときに知ったのが【mogumo】。
管理栄養士監修・無添加で安心できる上、冷凍庫から出してレンジで温めるだけ。
最初は「子どもが食べてくれるかな?」と半信半疑でしたが、思った以上に完食してくれて驚きました。
野菜も入っていて栄養も取れるし、罪悪感もゼロ。
ママの“心のゆとり”を取り戻してくれるサービスだと思います。
>>mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ
新生児がミルクを飲みすぎているのに「まだ欲しがる」理由
「さっきしっかりミルクを飲んだのに、また泣いてる」「哺乳瓶を離すと大声で泣き出す」
そんな様子を見ると、「もしかしてまだ足りていないの?」と不安になりますよね。
ですが、実は新生児がミルクを飲みすぎていても“まだ欲しがる”そぶりを見せることはよくあること。
ここでは、赤ちゃんが飲みすぎているにもかかわらず“欲しがるように見える理由”を、心と体の発達の面からわかりやすく解説します。
新生児期の赤ちゃんは、“吸う”という行為そのものに強い欲求を持っています。
これは「口唇欲求(こうしんよっきゅう)」と呼ばれ、生まれながらに備わった本能です。吸うことで安心感を得たり、自律神経が整ったりするため、空腹でなくても「吸いたい」という行動を見せるのです。
このため、「まだ飲みたい」ように見えても、実際にはミルクを欲しているのではなく、“吸いたい”だけのことが多いのです。
大人の私たちが「満腹=満足」だと思いがちなのに対して、赤ちゃんの場合は「心の満足」が得られないと落ち着かないことがあります。たとえば、以下のような状況では、飲んだばかりでもまた泣いてしまうことがあるのです。
-
ママにくっついていたい(不安で泣く)
-
抱っこしてほしい(触れ合いが足りない)
-
胃がムカムカしている(げっぷが出ない、張っている)
-
眠いのにうまく寝つけない
これらはすべて「ミルクが足りないから泣いている」わけではありません。
にもかかわらず、哺乳瓶を差し出せば吸ってしまうのが赤ちゃん。結果的に飲みすぎて、さらに不快になる…という悪循環につながることもあります。
赤ちゃんが泣いていると「お腹がすいてるのかな?」とすぐに思ってしまいがちですが、実際は以下のように、さまざまな理由で泣いている可能性があります。
|
泣く理由 |
特徴的なサイン |
|---|---|
|
お腹がすいた |
探すように顔を動かす、手を口に持っていく |
|
おむつが不快 |
足をバタつかせる、背中を反らせる |
|
抱っこしてほしい |
目を合わせようとする、泣き止まないがミルクは拒否 |
|
寝ぐずり |
目をこすったり、グズグズして落ち着かない |
|
胃が苦しい(飲みすぎ) |
吐き戻し、唸る、反り返るように泣く |
このように、「泣く=空腹」という単純な図式ではないことを知っておくことが、飲みすぎを防ぐ第一歩です。
では、飲んだばかりなのに欲しがるそぶりを見せたとき、どのように対応すればよいのでしょうか?
以下のような“ミルク以外の対応”をまず試してみることをおすすめします。
-
縦抱きしてげっぷを促す
→ 飲んだ直後に泣く場合は、空気がたまって苦しいことがあります。
-
おしゃぶりを使って吸啜欲を満たす
→ ミルクではなく、“吸いたい”気持ちの発散に有効。
-
しっかり抱っこして安心させる
→ 胸の音やぬくもりが不安を解消してくれます。
-
音楽やホワイトノイズで気分転換させる
→ 胎内音やゆったりした音楽は、新生児を落ち着かせる効果があります。
これらを試しても泣き止まない場合は、ミルクを少量追加するか、小児科に相談してみましょう。
毎回のように“まだ欲しがる”様子が見られる場合は、次の点を見直してみてください。
-
哺乳量が多すぎないか?
-
授乳間隔が短くなりすぎていないか?
-
ストレスや環境変化がないか?(来客、部屋が暑いなど)
-
吸啜欲を満たす時間が足りているか?(おしゃぶりや抱っこを活用)
こうした環境を整えても改善しない場合は、ミルクの調整や授乳の間隔を助産師や小児科医と一緒に考えるとよいでしょう。
「さっき飲んだばかりなのに、まだ欲しがる…」そんな時こそ、“量”ではなく“気持ち”に目を向けてみてください。
新生児の泣きは、ミルクだけで解決できない心のサインかもしれません。
吸いたい、安心したい、眠りたい…そんな欲求に寄り添いながら、ミルクのあげすぎを防ぐことが、赤ちゃんにとってもママ・パパにとっても心地よい育児につながります。
飲みすぎを防ぐミルクのあげ方と調整のコツ
赤ちゃんが「まだ欲しがる」ように見えると、つい多めにミルクをあげてしまいがち。
しかし、ミルクの飲みすぎは胃腸への負担や体調不良につながることもあるため、日頃から“適切な量とタイミング”を意識した授乳を心がけることが大切です。
ここでは、ミルクの飲みすぎを防ぐためのあげ方・工夫・調整のポイントを、すぐに実践できる形で紹介します。
赤ちゃんの適切なミルク量は、体重1kgあたり1日150ml前後が基本です。たとえば、体重4kgなら600mlが1日の目安となります。
そこから1日の授乳回数(通常6〜8回)に分けて考えると、1回あたり約75〜100mlが適量ということになります。ただしこれはあくまで「目安」。実際には赤ちゃんの性格や飲むペースによっても異なります。
【POINT】
-
1日の総量を意識しながら調整する
-
欲しがるからといってその都度足すのではなく、次の授乳で様子を見る
飲みすぎの原因として意外と多いのが、「乳首の流量が赤ちゃんに合っていない」ということ。
流れが早すぎると赤ちゃんは短時間で多くのミルクを飲み込み、満腹中枢が働く前に飲みすぎてしまいます。
【チェックポイント】
-
飲むスピードが早すぎないか?
-
哺乳中にむせたり吐いたりしていないか?
-
5〜10分程度で適量を飲み終えるくらいのペースか?
月齢や赤ちゃんの吸う力に合った乳首サイズを選ぶことで、無理なく、ゆっくり飲めるようになります。
赤ちゃんが勢いよく飲んでいるときほど、一気に飲ませるのではなく途中で小休憩を入れることが大切です。
-
途中で一度哺乳瓶を離してみる
-
ゲップを出すタイミングをつくる
-
飲んでいる様子が落ち着いてきたら終了のサインかも
小休憩を挟むことで、「本当にまだ飲みたいのか?」「落ち着いて満腹感が出てきたのか?」を見極めやすくなります。
泣いた=ミルクの合図、とは限りません。泣いた時にはまず以下の対応をして、「ミルク以外の理由」を探るクセをつけましょう。
-
抱っこ・スキンシップをしてみる
-
おむつをチェックする
-
眠たいサインかどうか確認する
-
胃が張って苦しそうにしていないか見る
-
おしゃぶりで“吸いたい欲”を満たす
これだけで、本当にミルクが必要かどうかの判断がつきやすくなります。
記憶だけに頼ると、「いつ飲んだ?」「どれくらい飲んだ?」が曖昧になります。育児アプリやノートなどを使って、以下の情報を記録しておきましょう。
-
授乳時間・間隔
-
ミルクの量
-
うんち・おしっこの回数
-
機嫌や睡眠の状態
この記録を続けることで、赤ちゃんのペースや飲みすぎの傾向に気づくことができ、「この時間はよく飲む」「午後は飲みすぎやすい」などの調整もしやすくなります。
「うちの子、飲みすぎかも…?」と思ったら、ひとりで抱えずに医師や助産師に相談しましょう。特に以下のようなケースでは、専門家の意見を取り入れることが重要です。
-
毎回のように吐き戻す
-
一日で1リットル以上飲んでいる
-
体重が1日50g以上増加し続けている
-
機嫌が悪く、うんちの状態も気になる
保健センターや産婦人科、小児科での体重測定や育児相談は、定期的に活用すると安心です。
赤ちゃんの「ミルクの飲みすぎ」は、ちょっとした工夫で防ぐことができます。
重要なのは、「量」よりも「様子」を観察し、「与えること」よりも「必要かどうかを見極めること」。
赤ちゃんの欲しがるサインに敏感になりすぎず、余裕を持って授乳と向き合うことで、健やかな成長につながります。
実際のママたちの体験談:「飲ませすぎだったかも?」
「赤ちゃんが泣くたびにミルクをあげていた」「たくさん飲んでくれることが嬉しかった」――。
育児の現場では、ミルクを飲ませることに一生懸命になりすぎて、「実は飲ませすぎだったかも」と後から気づくママも多くいます。
ここでは、実際のママたちの体験談を紹介しながら、飲みすぎに気づいたきっかけや、その後どう対処したのかをお伝えします。
「うちの子は飲みっぷりが良くて、1回140mlを8回、1日で1リットル以上飲んでいました。よく吐くのも“飲んだからだろう”と思ってたけど、助産師さんに『飲ませすぎてるかも』と言われてびっくり。量を調整したら吐かなくなりました。」(30代/混合育児)
→ 体重増加や飲む様子ばかりに目が行きがちですが、吐き戻しの頻度は大切なサインです。ミルク量を見直すことで、赤ちゃんも楽になります。
「授乳後すぐに泣くから『まだ足りないのかも』と追加でミルクを足してました。でも、あとで知ったのが“吸いたい欲求”だけってこともあると…。おしゃぶりや抱っこで落ち着くことがあるって知って、今では様子を見てから対応するようにしています。」(20代/完ミ育児)
→ 赤ちゃんの泣きには“吸いたい”という理由も。満腹サインを見極める力がついてくると、必要以上にミルクをあげずに済みます。
「母乳をあげたあと泣くのが不安で、毎回ミルクを足してました。でも気づけば母乳の分泌が減ってしまい、結果的にミルクの割合が増えてしまって…。今は母乳外来で相談しながら、母乳の量を戻しています。」(30代/混合育児)
→ 混合育児では、ミルクの足しすぎが母乳育児の妨げになることも。泣いていてもミルクだけが解決策ではないと気づくことが、育児の転機になることがあります。
「1ヶ月健診で『体重の増え方がハイペースですね』と指摘されて。毎回120〜150ml飲ませていたけど、どうやら飲みすぎだったみたいです。今は1回量を少し減らして、赤ちゃんの様子を見ながら調整しています。」(20代/完ミ育児)
→ 医師や保健師のフィードバックは、客観的な判断のヒントになります。定期的な体重測定で早めに気づけると安心です。
「育児ノートに授乳時間とミルク量を書き始めて、1日900mlを毎日飲んでいるとわかってびっくり。記録がなかったら気づかなかったと思います。今は6回に分けて700mlを目安にしています。」(30代/完ミ育児)
→ “見える化”することで自分の育児を客観視でき、調整のきっかけになります。記録アプリやメモの活用もおすすめです。
X(旧Twitter)や知恵袋などを見ても、「飲ませすぎてないか不安」「欲しがるからつい足してしまう」など、飲みすぎに関する悩みは非常に多く見られます。
よくある悩みの声:
-
「体重が増えすぎって言われて不安になった」
-
「ミルクを減らしたら泣くようになって迷った」
-
「母乳の後に毎回ミルクを足すのが正解かわからない」
同じような悩みを持つママたちの声を読むだけでも、「自分だけじゃない」と安心できることもあります。
飲みすぎに気づいたママたちの多くが口を揃えて言うのは、「あのときは“よかれと思って”やっていた」ということ。
赤ちゃんの機嫌が悪かったり、うんちや吐き戻しが気になったり、“ちょっとした違和感”がサインになっているケースがたくさんあります。
育児に正解はありませんが、体験談から学び、自分の赤ちゃんに合ったペースを見つけていくことが、親子にとって無理のない育児につながります。
ありがとうございます。
この記事のまとめ:「飲みすぎかも」と思ったら、焦らずチェック!
赤ちゃんがよく泣く、ミルクをよく飲む――それ自体は決して悪いことではありません。
しかし、だからといって「とにかくたくさん飲ませればいい」というわけでもありません。大切なのは、「赤ちゃんの様子を観察しながら、必要な量を見極めること」です。
ミルクの飲みすぎかどうかは、1回の授乳量だけでは判断できません。以下のような複数のサインを総合的に見て判断することが大切です。
- 体重の増加ペースが急激(1日50g以上増える日が続く)
- 毎回のように大量の吐き戻しがある
- 授乳後もグズグズして機嫌が悪い
- うんちが水っぽい、泡立っている、白っぽいなど明らかな変化がある
- 授乳間隔が短すぎる(1〜2時間おきに飲ませている)
- 1日のミルク総量が体重×150mlを大きく超えている
このようなサインがいくつも当てはまる場合、まずは授乳の方法やミルクの量を見直してみましょう。
泣く=空腹とは限らない
「泣いたからミルクをあげる」は、赤ちゃんの泣き方の意味を単純化しすぎてしまうことも。赤ちゃんはさまざまな理由で泣きます。
-
眠い
-
不安
-
抱っこしてほしい
-
おむつが気持ち悪い
-
胃がムカムカする(飲みすぎで不快)
そのすべてにミルクで対応していると、結果的に飲ませすぎにつながってしまうことがあります。泣く理由を「観察」する視点を持つことが、飲ませすぎを防ぐコツです。
不安になったら相談しよう
「足りてるのか分からない」「飲ませすぎてるかもしれない」――そんなときは、ひとりで抱え込まずに、助産師さんや小児科医に相談するのがおすすめです。
-
体重増加のペースは正常?
-
ミルクの量や回数は適切?
-
母乳とミルクのバランスはどう調整すればいい?
地域の保健センターや母乳外来など、頼れる場所は意外とたくさんあります。「ちょっと心配だから聞いてみた」でいいのです。
ミルクを飲んでくれると安心する、でも飲みすぎて体に負担がかかるのは避けたい――そのバランスを取るのが育児の難しさでもあります。
赤ちゃんの様子をよく観察し、飲んだ量だけにとらわれず、うんち・睡眠・機嫌など全体のバランスを見て判断することが大切です。
完璧である必要はありません。「飲みすぎかも」と思ったら立ち止まり、赤ちゃんと一緒に“ちょうどいいリズム”を見つけていきましょう。

(画像引用:モグモ公式サイト)
「今日のごはん、どうしよう…」
仕事から帰ってきて、保育園から子どもを迎えて、買い物して、夕飯を作って…毎日そんな繰り返しに疲れていませんか?
そんな忙しいママにおすすめなのが、幼児食宅配サービス mogumo(モグモ)。
1歳半〜6歳の子ども向けに、管理栄養士が考えた無添加・冷凍のおかずをお届けしてくれるんです。
✔ レンジでチンするだけ、調理はほぼゼロ!
✔ 栄養バランスもバッチリで偏食対策にも◎
✔ 忙しい夕食時に“あと1品”としても使える
「子どもがパクパク食べてくれる」だけで、ママの心もぐっと軽くなりますよ。
毎日の食事作りを少しラクにして、子どもと笑顔で過ごす時間を増やしてみませんか?
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ をタップ
をタップ
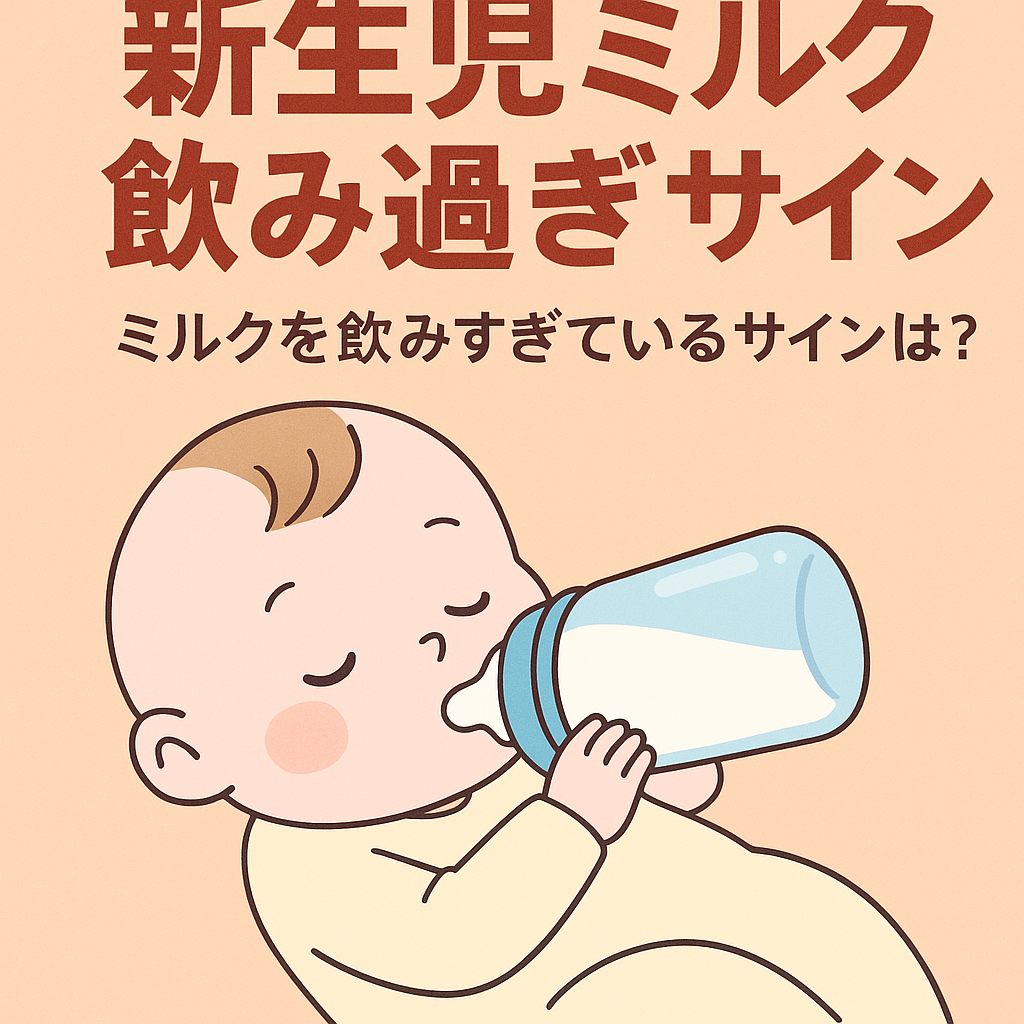





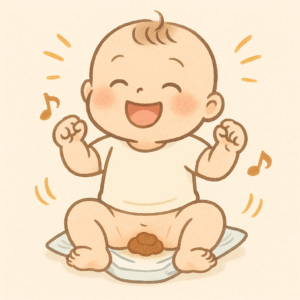



コメント