夜中の授乳…毎日続くと、ママやパパの体力も限界に感じてしまいますよね。
「夜だけでもミルクに切り替えたら、少しは眠れるのでは?」と思ったことがある方も多いのではないでしょうか。
実際、混合育児のなかで“夜だけミルク”を取り入れるご家庭も増えています。
でも気になるのが、「どれくらいの量をあげればいいの?」ということ。
少なすぎると赤ちゃんがすぐ起きてしまいそうだし、あげすぎても体に負担がかからないか心配…。
この記事では、混合育児で夜間だけミルクを使う場合の目安量や注意点をわかりやすく解説します。
赤ちゃんもママ・パパも、ぐっすり眠れる夜を目指して、一緒に最適な量を見つけていきましょう。
【総額7,660円OFFクーポン】【特典付き】
初回限定キャンペーンでお得にGETできる!
(画像引用:モグモ公式サイト)
「子どもが小さいうちは、仕事も家事も育児も全部フル回転。気づけば自分の時間はゼロ…」
「健康的なご飯を準備してあげたいけど、うまく時間を作れない…」
そんなママの一番の悩みは“毎日のごはん作り”ではないでしょうか。そんな時におすすめなのが『モグモ』です。
モグモは1歳半〜6歳向けの幼児食宅配サービスで、無添加で栄養バランスに優れた冷凍ごはんが届くため、冷凍庫にストックしておけばいつでも使えるので安心です。
- 保育園帰りで子どもが「お腹すいた!」と言っても、レンジで数分チンするだけ
- 献立に悩む時間がなくなる
- 子どもが食べやすい味付け・サイズだから、食べムラが減る
「今日は疲れてごはんを作りたくない…」「子供にも栄養バランスが整った食事を摂らせたい」そんなときに助けてくれるんです。
家族の食卓を無理なく支えながら、ママに“心のゆとり”を取り戻してくれるはずです。今なら全額返金保証付きで安心して試せるので、気軽に始めてみてくださいね!
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ![]()
混合育児で夜だけミルクの場合の量は?やり方は?
混合育児をしていると、「夜だけミルクにして、少しでもまとまった睡眠をとりたい」と考えるママ・パパは多いのではないでしょうか。
特に産後の疲れがたまりやすい時期、夜間の授乳は体力的にも精神的にも負担になりがち。
そんなときに、夜の授乳をミルクに切り替えるという選択肢は、赤ちゃんだけでなく、親にとってもメリットがあります。
母乳よりもミルクのほうが消化に時間がかかるため、赤ちゃんが比較的長く眠ってくれることが多いです。
そのため、「夜だけミルク」を取り入れることで、夜間の授乳間隔が空き、親の睡眠時間を確保しやすくなります。
また、パパが夜間のミルクを担当することで、ママの負担を軽減することもでき、家族全体のバランスが取りやすくなるという声も。
赤ちゃんの月齢や体重、飲む力によって適量は変わりますが、おおよその目安として以下を参考にしてみてください。
-
生後1ヶ月頃:100〜120ml
-
生後2ヶ月頃:120〜140ml
-
生後3ヶ月頃:140〜160ml
-
生後4〜5ヶ月頃:160〜200ml
-
生後6ヶ月以降:200ml前後(離乳食の進み具合によって変動)
あくまで目安量なので、赤ちゃんがどれくらい飲めるか、飲み終えたあとに満足していそうか(寝付きや機嫌)をよく観察して調整していくことが大切です。
-
タイミングを見極める
夜間に母乳からミルクに切り替えるときは、授乳リズムが安定してきたタイミングがベターです。まだリズムが整っていない新生児期は無理に切り替えず、生後1〜2ヶ月以降に試すとスムーズなことが多いです。
-
授乳時間を固定する
例えば「夜9時の授乳はミルク」と時間を決めておくと、赤ちゃんも生活リズムが作りやすくなります。また、同じ時間にミルクをあげることで、ママの母乳のリズムも崩れにくくなります。
-
ミルクの準備をスムーズにしておく
夜中にバタバタしないよう、寝る前に哺乳瓶を準備しておいたり、湯冷ましを保温しておくとスムーズに対応できます。ミルク作りに手間取ると赤ちゃんが泣き出して焦る…という負のループを避けられます。
-
母乳とのバランスに注意
夜にミルクをあげることで、その時間の母乳分泌が減ることがあります。母乳の分泌を保ちたい場合は、夜間でも搾乳をしたり、昼間にしっかり母乳を与えるように意識しましょう。
ミルクの量が多すぎると、吐き戻しや腹痛の原因になることがあります。
逆に少なすぎると、すぐに起きてしまうことも。
最初は様子を見ながら少なめからスタートし、赤ちゃんの満足度を見て量を調整するのが良いでしょう。
また、夜だけミルクにしたことで便の状態が変わる、授乳の回数が減るなどの変化もあるかもしれません。
母乳とミルクでは腸内環境への影響も違うため、気になる場合はかかりつけ医や助産師さんに相談するのもおすすめです。
夜だけミルクにすることで、赤ちゃんも親もぐっすり眠れる日が増えるかもしれません。
大切なのは、赤ちゃんの様子をよく観察しながら、家族のペースに合ったやり方を見つけていくこと。
無理なく続けられる混合育児のスタイルを、一緒に探していきましょう。
混合育児のやり方について最適な方法を紹介!
母乳だけじゃ足りていない気がする…」「でも完全ミルクに切り替えるのは少し不安」
そんな思いから混合育児を選ぶママ・パパは多くいらっしゃいます。
混合育児とは、母乳とミルクを組み合わせて赤ちゃんを育てるスタイル。実はとても柔軟性があり、ライフスタイルに合わせたやり方ができるのが大きな魅力です。
しかし一方で、「母乳とミルクのバランスは?」「どんなタイミングでミルクを足せばいい?」など、やり方に迷ってしまうことも少なくありません。
ここでは、混合育児のやり方や最適な方法について、赤ちゃんにもママにも負担の少ないスタイルをご紹介します。
まずは混合育児にはどんなタイプがあるのかを知って、自分の家庭に合った方法を探してみましょう。
-
母乳メイン+必要なときにミルクを足すタイプ(補足型)
母乳のあとに足りなさそうなときだけミルクを足す方法。
→「母乳はできるだけ続けたいけど、授乳後にまだ泣くからミルクも」という場合におすすめです。
-
母乳とミルクを交互に与えるタイプ(交互型)
1回目は母乳、2回目はミルクというように交互に与えるスタイル。
→ママの休息時間を確保しやすく、パパも授乳に参加しやすいメリットがあります。
-
時間帯で分けるタイプ(時間帯分け型)
昼は母乳、夜はミルクといったように時間帯で与える方法。
→夜間に赤ちゃんが長く寝てくれることも多く、ママの体力回復にも◎。
① 最初は「母乳からスタート」が基本
母乳の分泌を促すためにも、まずは母乳から与えるのが一般的です。
赤ちゃんが吸う刺激で母乳の出が安定してくるため、最初の5〜10分はできるだけ母乳を与えてみましょう。
② 飲み足りなそうなサインを見逃さない
母乳のあとに赤ちゃんが不機嫌そうだったり、すぐ泣いたりするようであれば、ミルクを少し足してみましょう。
1回につき20〜60ml程度からスタートして、様子を見ながら調整していくと安心です。
③ 授乳リズムを意識して
赤ちゃんの月齢によって授乳間隔は変わりますが、3時間おき(1日8回程度)を目安にリズムを整えると、混合育児も安定しやすくなります。
スケジュールに合わせて、ミルクの回数やタイミングを決めておくと楽になりますよ。
④ ミルクの量は月齢・体重に応じて調整
生後1〜2ヶ月の赤ちゃんであれば、1回のミルク量は100〜140ml前後が目安になります。
ただし母乳の量によっても調整が必要なので、「母乳+ミルクでお腹が満たされていそうか?」を観察しながら決めましょう。
-
哺乳瓶に慣れさせておく
最初は哺乳瓶を嫌がる赤ちゃんもいます。少しずつ慣れさせることで、ママ以外の人でも授乳が可能になります。
-
ミルクは飲みすぎに注意
ミルクを足しすぎると、母乳を飲む意欲が減ることも。赤ちゃんの体重や便の状態をチェックしながら、適量を意識しましょう。
-
ママの気持ちも大切に
「母乳じゃないとダメ」「ミルクばかりでいいのかな」と不安になることもあるかもしれません。でも、赤ちゃんが元気に育っていればどちらも立派な愛情です。自分を責めずに、自信を持って混合育児を進めていきましょう。
混合育児には、母乳育児とミルク育児の“いいとこ取り”ができるという大きなメリットがあります。
赤ちゃんの様子とママ・パパの生活スタイルに合わせて、柔軟に取り入れていくことが成功のカギ。
正解はひとつではないので、「我が家にとっての最適」を見つけていきましょう。
混合育児でミルクと交互にあげて母乳の量が減る。原因は何?
「混合育児で母乳とミルクを交互にあげていたら、最近母乳の出が悪くなってきた気がする…」
そんな悩みを抱えていませんか?育児の中でも“母乳の出”は、思うようにいかないことで不安や焦りを感じやすいポイントです。
特に混合育児をしていると、「ミルクを使うことで母乳が減ってしまうのでは?」という疑問や心配は、多くのママが経験しています。
実際に、母乳とミルクを交互にあげている中で、母乳の分泌が徐々に減ってしまうケースはあります。
では、どうしてそのようなことが起きるのでしょうか?
ここでは、母乳量が減ってしまう原因と対処法について、わかりやすく解説していきます。
母乳の分泌は、赤ちゃんが乳首を吸うという“刺激”によって促されます。
つまり、頻繁に吸ってもらうことで脳が「もっと母乳を出そう」と指令を出す仕組みになっているのです。
しかし、ミルクを交互にあげるスタイルだと、単純に母乳を飲む回数が減ってしまいます。
そうすると脳への刺激も減り、「あまり必要ないのかな?」と判断されて、母乳の量が徐々に少なくなっていくのです。
ミルクは消化に時間がかかり、腹持ちが良いため、赤ちゃんが長く寝たり、次の授乳のタイミングでお腹がすいていないことがあります。
その結果、母乳を飲む量や時間が短くなり、分泌が促されにくくなるのです。
また、「ミルクの方が出てくるのが早いから好き」という赤ちゃんもいて、母乳への吸い付きが弱くなることも。
これもまた、母乳量が減る要因のひとつになります。
混合育児では「昼は母乳、夜はミルク」「疲れたときはミルクにする」など、生活に合わせたリズムをとりやすいですが、母乳をあげる時間帯が極端に減ると、分泌に影響が出ることがあります。
特に夜間授乳は、母乳を増やすホルモン(プロラクチン)の分泌が活発になる時間帯とされているため、夜にミルクばかりだと、母乳の維持が難しくなることもあるのです。
意外と見落としがちですが、母乳の量はママの体調にも大きく影響されます。
混合育児はミルクの安心感からつい母乳をおろそかにしてしまいがちで、加えて産後の疲労やストレス、水分不足、栄養の偏りがあると、母乳が減ってしまう原因になります。
「ミルクがあるから」と安心することも大切ですが、母乳を続けたい場合は、ママのケアも忘れずに。
1. 母乳の回数を意識して増やす
少しでも母乳を続けたい場合は、「できるだけ吸ってもらう機会を増やすこと」がポイントです。
交互にしていた場合でも、ミルクの回数を減らして、まず母乳を吸わせてからミルクを足すスタイル(補足型)に変えるだけでも効果があります。
2. 授乳後に搾乳して刺激をプラス
赤ちゃんが吸う時間が短くなってしまったときは、授乳後に搾乳して乳房を刺激することで、母乳分泌の維持をサポートできます。
出なくても「刺激を与えること」が目的なので、プレッシャーを感じすぎなくても大丈夫です。
3. 夜間授乳を取り入れる
夜中に1回でも母乳をあげることで、ホルモン分泌を促しやすくなります。
負担が少ないタイミングを選んで、できる範囲で取り入れてみてください。
4. 水分・食事・休息をしっかりと
水分は1日2Lを目安に、バランスのとれた食事と睡眠も意識しましょう。
母乳育児はママの体が資本です。がんばりすぎず、自分を大切にしてくださいね。
混合育児はとても柔軟で、家庭に合ったスタイルを選べる素晴らしい方法です。
ただ、やり方次第では母乳が減ってしまうことも。
大切なのは、「自分にとっての心地よいバランス」を見つけることです。
母乳でもミルクでも、どちらを選んでも愛情に変わりはありません。
赤ちゃんと自分にとって無理のない方法で、混合育児を前向きに続けていきましょう。
混合育児のメリットは?
育児をしていると、「完全母乳でいきたいけどうまくいかない」「でも全部ミルクに切り替えるのも不安…」と、授乳スタイルに悩むことがありますよね。
そんな中で、多くの家庭が取り入れているのが「混合育児」。
母乳とミルクの“いいとこ取り”ができる方法として、いま多くのママたちに選ばれています。
でも、混合育児って実際どうなの?どんなメリットがあるの?と疑問に感じる方もいるかもしれません。
ここでは、混合育児を実際に取り入れてみて「よかった!」と感じる声が多い理由や、その魅力を詳しくご紹介します。
母乳は赤ちゃんにとって栄養バランスが良く、免疫力を高めると言われています。
混合育児では、母乳を続けることでこうしたメリットを取り入れながら、ミルクを足すことで「足りているかな?」という不安を減らすことができます。
特に新生児期は母乳の出が安定せず、不安になるママも多いもの。
そんな時、ミルクがあるというだけで気持ちに余裕ができるという声もたくさんあります。
母乳は消化が早く、赤ちゃんが頻繁にお腹をすかせてしまうことも。
一方、ミルクは腹持ちが良いので、赤ちゃんがぐっすり眠ってくれる時間が長くなる傾向があります。
「夜だけミルクをあげて、朝まで眠れるようになった」「まとまって寝てくれるので、私も回復できた」
このような声は、混合育児ならではのメリットとしてよく挙げられます。
完全母乳育児だと、授乳はどうしてもママ一人にかかってしまいます。
ですが、混合育児なら哺乳瓶を使う機会があるため、パパや家族も授乳に参加しやすくなります。
例えば夜中の授乳をパパにお願いしたり、ママの外出中に家族が対応できるなど、ママの負担をぐっと軽くすることができます。
「ママがひとりで抱え込まなくていい」というのは、精神的にも大きなメリットです。
混合育児は「いつでも母乳」「いつでもミルク」ではなく、その日のママや赤ちゃんの体調、予定に合わせてスタイルを変えられるのが魅力です。
たとえば、
-
昼は母乳、夜はミルク
-
疲れている日はミルクをメインに
-
母乳のあと、まだ足りなさそうならミルクを足す
といった具合に、臨機応変に授乳を調整できるのは、育児を続けていくうえで大きな安心感につながります。
赤ちゃんが成長し、離乳食が始まる頃になると、授乳のスタイルを見直す時期がやってきます。
そんなとき、混合育児をしていれば、ミルクや哺乳瓶に慣れている分、スムーズに移行できることも。
「完全母乳だったら断乳が大変だったかも…」
「混合にしていたおかげで、夜間断乳が思ったより楽だった」
というママの声もあり、後々の負担軽減にもつながることがあります。
育児は理想どおりにいかないことの連続です。
そんな中で「母乳が足りないのかも」「ちゃんと育っているかな」と自分を責めてしまうママも少なくありません。
混合育児は、「母乳でできるところは頑張る」「足りないときはミルクで補えばいい」と、柔軟に対応できる方法です。
無理にどちらかにこだわらなくていいというのは、ママ自身の心の安定にもつながります。
母乳にもミルクにも、それぞれに良さがあります。
混合育児は、そのどちらも取り入れながら、赤ちゃんとママにとって一番バランスのよい方法を選べるスタイルです。
「母乳が出ない自分はダメ…」「ミルクを足すのは甘え…」そんな風に思う必要はありません。
混合育児は、がんばるママの味方。
自分たちに合ったスタイルを選びながら、赤ちゃんとの毎日を無理なく楽しんでいきましょう。
混合育児はいつまで続ける?
「混合育児っていつまで続ければいいの?」
「気づいたらミルクばかりになってきたけど、これでいいの?」
母乳とミルクを組み合わせる“混合育児”は、それぞれのご家庭に合わせて柔軟に対応できる一方で、終わりどきや切り替えのタイミングに迷う方も少なくありません。
特に初めての育児では、「周りはどうしているの?」「混合のままじゃダメなのかな…」と不安になることもありますよね。
ここでは、混合育児をいつまで続けるのが理想的なのか、その目安や判断ポイントについて詳しく解説します。
まず前提として、混合育児には「◯ヶ月までにやめなければならない」というルールはありません。
母乳にもミルクにもそれぞれメリットがあるため、ご家庭のライフスタイルや赤ちゃんの成長、ママの体調や気持ちに合わせて続ける期間を自由に決めることができます。
赤ちゃんが元気に育っていて、ママ・パパが無理なく続けられていれば、それが“最適なやり方”です。
混合育児を続けているママたちの中には、次のような節目でスタイルを変える人が多くいます。
① 母乳が安定してきたら、徐々にミルクを減らす(生後1~3ヶ月)
母乳がよく出るようになってきたと感じたら、ミルクの量を少しずつ減らしていくことで、母乳中心に切り替えていく方法です。
ただし、「母乳の出が安定していても、夜間だけはミルクのまま」というように、無理のないスタイルを継続する方も多数います。
② 離乳食が始まるタイミング(生後5~6ヶ月)で見直す
離乳食の開始により、授乳回数そのものが減ってきます。
このタイミングで、「ミルクをやめて母乳だけ」「母乳を卒業してミルク+離乳食」に切り替えるケースもあります。
赤ちゃんの食べ具合や飲み具合によって、徐々に授乳の回数やスタイルを調整していきましょう。
③ 1歳を目安に授乳全体を見直す
1歳頃になると、栄養の中心が「離乳食」に移行していきます。
そのため、ミルクや母乳の量・回数も自然に減っていきます。
この頃に「卒乳」や「断乳」を考え始める家庭も多く、混合育児を終えるきっかけになることも。
こんなときは無理せず“今のまま”でOK!
-
母乳が出にくくてミルクに頼る日が増えてきた
-
仕事復帰で日中はミルク、夜は母乳というスタイルが合っている
-
赤ちゃんが哺乳瓶もおっぱいも好きで、どちらでもよく飲む
上記のように、特に困っていないのであれば、無理に切り替えたり、終わりを急ぐ必要はありません。
混合育児は“どっちつかず”ではなく、“その時の最適を選んでいる”柔軟な方法です。
「いずれは母乳メインに戻したい」と考えている場合、ミルクの回数が多くなると母乳の分泌が減ってしまう可能性もあります。
母乳の量を保ちたい場合は、赤ちゃんが飲まない時間帯でも搾乳で刺激を与えるなど、分泌維持の工夫を続けるとよいでしょう。
混合育児をやめるタイミングが来たと感じたら、いきなりすべてを切り替えるのではなく、少しずつ授乳の回数や量を減らしていくのがポイントです。
例えば:
-
ミルクを1日1回だけにする
-
寝る前の授乳を母乳だけにする
-
離乳食をしっかり食べた日は授乳を1回省く
といったように、段階的に移行していくと、赤ちゃんもママの体もスムーズに慣れていきます。
混合育児は、赤ちゃんの様子や家庭の状況に合わせて柔軟に対応できる、安心で便利な育児スタイルです。
いつまで続けるかは人それぞれ。正解はありません。
「母乳が出にくくても、赤ちゃんが笑ってくれるならそれでいい」
「ミルクがあるからこそ、私も少し心の余裕が持てた」
そんな風に、“我が家らしい育児”ができていれば、それが一番の成功です。
焦らず、自分たちのペースで、混合育児を楽しんでくださいね。

(画像引用:モグモ公式サイト)
「今日のごはん、どうしよう…」
仕事から帰ってきて、保育園から子どもを迎えて、買い物して、夕飯を作って…毎日そんな繰り返しに疲れていませんか?
そんな忙しいママにおすすめなのが、幼児食宅配サービス mogumo(モグモ)。
1歳半〜6歳の子ども向けに、管理栄養士が考えた無添加・冷凍のおかずをお届けしてくれるんです。
✔ レンジでチンするだけ、調理はほぼゼロ!
✔ 栄養バランスもバッチリで偏食対策にも◎
✔ 忙しい夕食時に“あと1品”としても使える
「子どもがパクパク食べてくれる」だけで、ママの心もぐっと軽くなりますよ。
毎日の食事作りを少しラクにして、子どもと笑顔で過ごす時間を増やしてみませんか?
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ をタップ
をタップ




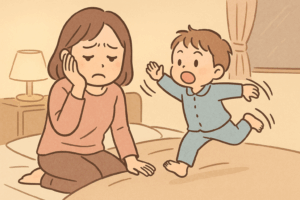
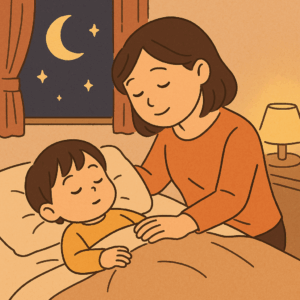
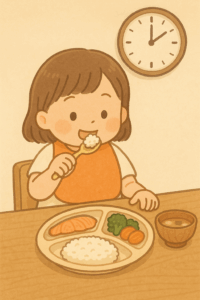



コメント