「生後4ヶ月の赤ちゃんって、ミルクどれくらい飲めばいいの?」「最近飲む量が減ったけど大丈夫?」そんな不安を抱えているママやパパは少なくありません。
完ミや混合育児をしていると、母乳と違って「量が目に見える」からこそ悩みやすいもの。
特にこの時期は赤ちゃんの成長が著しく、飲み方にも個人差が出始め、「100mlしか飲まない日もある」「逆に1日1000ml超えるけど平気?」などの声も。
本記事では、生後4ヶ月の赤ちゃんにおけるミルクの量の目安や回数、完ミと混合の違い、飲みが悪くなったときの理由や対処法まで、ママ・パパの疑問に寄り添いながら丁寧に解説します。
赤ちゃんの「今」に合った最適なミルク量を知ることで、日々の授乳がもっと安心で楽しいものになるはずです。
【総額7,660円OFFクーポン】【特典付き】
初回限定キャンペーンでお得にGETできる!
(画像引用:モグモ公式サイト)
「子どもが小さいうちは、仕事も家事も育児も全部フル回転。気づけば自分の時間はゼロ…」
「健康的なご飯を準備してあげたいけど、うまく時間を作れない…」
そんなママの一番の悩みは“毎日のごはん作り”ではないでしょうか。そんな時におすすめなのが『モグモ』です。
モグモは1歳半〜6歳向けの幼児食宅配サービスで、無添加で栄養バランスに優れた冷凍ごはんが届くため、冷凍庫にストックしておけばいつでも使えるので安心です。
- 保育園帰りで子どもが「お腹すいた!」と言っても、レンジで数分チンするだけ
- 献立に悩む時間がなくなる
- 子どもが食べやすい味付け・サイズだから、食べムラが減る
「今日は疲れてごはんを作りたくない…」「子供にも栄養バランスが整った食事を摂らせたい」そんなときに助けてくれるんです。
家族の食卓を無理なく支えながら、ママに“心のゆとり”を取り戻してくれるはずです。今なら全額返金保証付きで安心して試せるので、気軽に始めてみてくださいね!
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ![]()
生後4ヶ月の赤ちゃんの成長と1日の生活リズム
生後4ヶ月になると、赤ちゃんの成長はますます活発になります。首がすわってきたり、声を出して笑ったりと、ママやパパとのコミュニケーションも増えてくる時期です。
そして、ミルクの量や授乳間隔にも変化が現れやすくなり、「本当にこの量で足りているのかな?」と不安になることもあるかもしれません。
まずは、4ヶ月頃の赤ちゃんの平均的な発達や生活リズムを知ることから始めましょう。
厚生労働省の乳幼児身体発育調査によると、生後4ヶ月の赤ちゃんの平均的な身長・体重は以下のとおりです。
|
性別 |
平均身長 |
平均体重 |
|---|---|---|
|
男の子 |
約61.7~67.2cm |
約6.4~8.3kg |
|
女の子 |
約60.2~65.7cm |
約5.9~7.7kg |
もちろんこれはあくまで目安であり、個人差があります。この時期の赤ちゃんは、1日30g前後のペースで体重が増えているかどうかが成長の確認ポイントです。
生後4ヶ月になると、授乳のリズムも少しずつ整ってきます。完ミや混合育児の場合、授乳間隔は3~4時間おきが一般的で、1日5~6回程度に落ち着いてくる赤ちゃんも多いです。
ただし、お腹の空き具合や赤ちゃんの性格によって、2時間でお腹をすかせる子もいれば、5時間以上ぐっすり寝てしまう子もいます。
また、夜間の授乳回数が減る子も増えてきており、「朝までぐっすり寝るようになった」「夜1回だけの授乳で済むようになった」という声も。反対に、夜中に2~3回起きてミルクを欲しがる子もいて、それぞれのペースでの成長が見られます。
生後4ヶ月頃の赤ちゃんの1日のスケジュールは、下記のようなイメージです。
|
時間帯 |
活動 |
|---|---|
|
7:00 |
起床・ミルク |
|
9:00 |
お昼寝(30分〜1時間) |
|
10:00 |
ミルク・遊び |
|
12:00 |
お昼寝(1〜2時間) |
|
14:00 |
ミルク・遊び |
|
16:00 |
夕寝(30分程度) |
|
18:00 |
ミルク・お風呂 |
|
20:00 |
就寝(夜中に1~2回授乳) |
このように、日中は授乳・お昼寝・遊びのリズムが交互に訪れるようになってきます。
ミルクの量や間隔も、この生活リズムに合わせて安定してくると、赤ちゃん自身も過ごしやすくなります。
生後4ヶ月のミルクの量の目安は?完ミと混合で違う?
赤ちゃんの栄養の大部分をミルクが担う生後4ヶ月。この時期の赤ちゃんにとって、ミルクの量と頻度は非常に重要なポイントです。
ただし、完全ミルク(完ミ)育児なのか、母乳とミルクの混合育児なのかによって、目安となるミルクの量は異なってきます。
また、個人差も大きく、「平均通りに飲まないけど大丈夫?」と悩むママやパパも少なくありません。
ここでは完ミと混合、それぞれの育児スタイルにおけるミルクの量の目安やポイントを紹介します。
完ミで育てている場合、1回の授乳量の目安は180〜200ml程度、1日5〜6回の授乳が一般的です。つまり、1日トータルで900〜1200mlが目安となります。
➤ よく検索されている関連キーワードへの対応:
-
「生後4ヶ月 ミルクの量 完ミ」→ 目安は900〜1200ml/日
-
「生後4ヶ月 ミルクの量 700」→ 少ない可能性あり(後述)
-
「4ヶ月 ミルク量 1日1000 超える」→ 飲みすぎ?と心配になるが、個人差で許容範囲の場合も
特にミルクメーカーによってもパッケージに「目安量」が記載されていますが、それはあくまで一般的なガイドラインであり、すべての赤ちゃんに当てはまるものではありません。
ポイント:
大切なのは、「1日トータルの摂取量」だけでなく、赤ちゃんの体重増加・機嫌・睡眠の質・うんちの状態などを合わせて判断することです。
混合育児の場合は、母乳の量が目に見えないため、「どれくらいミルクを足せばいいのか分からない」という悩みがよく聞かれます。
この場合のミルク量は、以下のように調整するのが一般的です。
【混合育児の基本パターン】
-
母乳+ミルク補足(ミルク寄り)
→ 1回につき100~120mlのミルクを足す
-
母乳中心で1日数回だけミルク(母乳寄り)
→ ミルクは1日1~2回、100~160ml程度
母乳の分泌量や赤ちゃんの飲み方によって、必要なミルク量は変わります。特に生後4ヶ月頃は、赤ちゃん自身が「満腹」を感じられるようになってくるため、急に飲む量が減ることもあります。
➤ よく検索されているキーワード対応:
-
「生後4ヶ月 ミルクの量 混合」→ パターン別の補足量を説明
-
「生後4ヶ月 ミルク トータル量 600」→ 母乳の量が多ければ問題ないケースも
💡ポイント:
母乳を飲んでいる時間や、赤ちゃんの吸う力、満足度の観察が重要です。体重増加が順調であれば、ミルク量が少なめでも問題ない場合が多いです。
生後4ヶ月の赤ちゃんは、消化力や胃の容量、飲むスピードにも個人差が出てくる時期です。
同じ月齢でも「200mlゴクゴク飲む子」もいれば、「100mlでお腹いっぱいになる子」もいて自然なことです。
「○○ml飲まなきゃ」と焦るよりも、赤ちゃんのペースを尊重する姿勢がとても大切。
飲みムラがあっても、体重・おしっこ・機嫌などが順調であれば、過度に心配する必要はありません。
生後4ヶ月のミルクの飲みが悪くなった?よくある理由と対処法
「これまでゴクゴク飲んでいたのに、急に飲まなくなった…」
「哺乳瓶を見ると嫌そうな顔をする」
「途中で飲むのをやめて遊び始める」
生後4ヶ月頃の赤ちゃんによく見られるのが、ミルクの飲みが悪くなる現象です。
ママやパパからすれば、「病気?」「飽きた?」「何か変?」と心配になりますよね。
でもご安心ください。多くの場合、生後4ヶ月特有の成長過程に起因する自然な変化です。
ここでは、よくある原因とその対処法をまとめて紹介します。
生後4ヶ月頃になると、赤ちゃんの脳の発達により「満腹中枢(おなかいっぱいと感じる機能)」が少しずつ働き始めます。
それまで反射的に飲んでいたミルクを、「おなかいっぱいだからもういらない」と感じて自分で飲む量を調整し始めるのです。
このため、飲み残しが増えたり、途中で遊び始めたりするのは自然なことでもあります。
赤ちゃんの口の発達も進み、これまで気にしていなかった乳首の硬さ・形・流量に違和感を感じるようになることがあります。
特に、
-
吸っても出てこない(流量が少ない)
-
出過ぎてむせる(流量が多すぎる)
-
硬すぎて疲れる
といった理由で、途中で飲むのをやめてしまうケースがあります。
💡対処法:乳首のサイズ(S→Mなど)や形状を見直すだけで改善することもあります。月齢に合ったものに切り替えてみましょう。
生後4ヶ月の赤ちゃんは視覚・聴覚も発達し、ママの顔や部屋の音・動きに敏感になります。
そのため、飲んでいる途中に気が散ってそっちに興味が向いてしまうことも。
この「遊び飲み」はまさに成長の証。「集中力がついてきた」「周囲への関心が高まってきた」ことの現れです。
💡対処法:
-
テレビや音を消して静かな環境で授乳する
-
照明を落として、赤ちゃんが集中しやすい空間を作る
-
ママと目を合わせながら静かに飲ませる
赤ちゃんは体調の変化にも敏感です。
鼻づまりやのどの違和感、暑さ・寒さなど、ちょっとした不快感でもミルクを拒否することがあります。特に気温や湿度が高い日などは、食欲が落ちることも。
💡対処法:
-
鼻づまりがある時は、授乳前に鼻吸い器などでケア
-
ミルクの温度を少し調整(冷たい日や暑い日はぬるめに)
-
様子がおかしいときは、無理に飲ませず休憩をはさむ
「飲みが悪い」=「すぐに異常」とは限りませんが、以下のような様子がある場合は医療機関への相談をおすすめします。
-
毎回ほとんど飲まない
-
明らかに体重が増えていない
-
機嫌がずっと悪い・ぐったりしている
-
おしっこの回数が極端に少ない
親が感じる“何かおかしい”という直感は大切です。
心配なときは遠慮せず、小児科や助産師に相談してみましょう。
「生後4ヶ月 ミルク100しか飲まない」「トータル600」でも大丈夫?
「1回のミルク量が100mlしか飲めていない…」
「1日トータルでも600mlくらい。明らかに少ない気がする…」
こうした悩みは、生後4ヶ月頃のママやパパから特によく聞かれます。
完ミであっても混合であっても、赤ちゃんが「少なめしか飲まない」ように見えると、「栄養が足りていないのでは?」「体重が増えないのでは?」と不安になって当然です。
ですが、ミルクの量が少なく見えても“足りている”場合も意外と多いのです。以下で詳しく見ていきましょう。
1回の授乳量の目安としては、完ミの場合で180〜200ml程度と言われています。
そのため、「100mlしか飲まない」と聞くと、「かなり少ない」と感じるかもしれません。
しかし、以下のようなケースでは問題ない場合もあります。
例)1日の回数が多い場合
-
100ml × 7回=700ml
-
100ml × 8回=800ml
このように、1回量は少なくても回数が多ければ、1日のトータルはしっかり摂取できていることになります。
「生後4ヶ月 ミルク トータル量 600」で検索している方も多いですが、これは確かにやや少なめの部類に入ります。ただし、一概に“ダメ”とは言えません。
以下のような場合には問題ないこともあります。
混合育児で母乳の量が多いケース
ミルクは600mlでも、母乳をしっかり飲んでいれば栄養は足りている可能性が高いです。
赤ちゃんの体重が順調に増えているケース
目安としては、1日平均で20~30g程度の体重増加があるかどうか。これは個人差もありますが、成長曲線を大きく外れていなければ心配ないことが多いです。
機嫌がよく、うんち・おしっこがしっかり出ている場合
授乳後にご機嫌だったり、睡眠が安定していれば、赤ちゃんの満足度は高い状態です。おしっこが1日6回以上出ていれば、水分が足りているサインとも言われています。
ミルク量が600ml前後でも、以下のような様子が見られる場合は要注意です。
|
注意サイン |
内容 |
|---|---|
|
機嫌が悪い |
授乳後に泣き止まない、ぐずぐずが続く |
|
体重が増えない |
1週間〜10日で変化がない、成長曲線の下限を下回る |
|
おしっこが少ない |
1日5回以下しか出ていない |
|
便秘・脱水傾向 |
うんちが何日も出ない、唇が乾く、泣いても涙が出ない |
このような状態が見られる場合は、早めにかかりつけの小児科や保健師に相談しましょう。
-
授乳間隔を少し空けてみる(お腹が空いてからの方がよく飲む場合も)
-
授乳中の姿勢を変えてみる
-
ミルクの温度を微調整する(少しぬるめ・少し熱めなど)
-
授乳中の周囲の刺激を減らす(テレビや話し声など)
また、飲んだ量だけでなく、赤ちゃんの全体的な様子を観察することがとても大切です。
逆に飲みすぎ?生後4ヶ月でミルクが1日1000ml超えるのは問題?
「最近ミルクを1回200ml以上ゴクゴク飲む…」
「1日トータルで1000mlを軽く超えてしまうけど、大丈夫?」
このように、飲む量が多すぎるのでは?と不安になるママ・パパも少なくありません。
生後4ヶ月頃になると、赤ちゃんの胃の容量も大きくなり、1回に飲める量も増えてきます。
しかし、1日1000mlを超えると“飲み過ぎ”なのかどうか、判断に迷いますよね。
ここでは、ミルクをたくさん飲む赤ちゃんの特徴と、注意すべきポイントを詳しく解説します。
まず結論から言うと、「必ずしも問題ではありません」。
多くのメーカーが推奨する生後4ヶ月の目安量は、1日900〜1000ml前後。それをやや超える程度であれば、赤ちゃんの食欲や成長による自然な変化とも考えられます。
特に以下のような赤ちゃんは、1日1000mlを超えることも珍しくありません。
-
体格が大きめ
-
活動量が多く、泣く時間が長い
-
よく汗をかく
-
飲むのが好きなタイプ
ただし、飲みすぎが体に負担をかけているサインが出ていないかどうかは確認しておく必要があります。
ミルクを大量に飲んでしまうことで、以下のような症状が見られる場合は要注意です。
|
症状 |
内容 |
|---|---|
|
吐き戻しが頻繁 |
飲みすぎにより胃がパンパンになっている可能性 |
|
うんちが水っぽくなる |
消化が追いつかず、下痢気味になることも |
|
機嫌が悪い |
お腹が張って苦しい、げっぷ不足などのサイン |
|
夜中に何度も起きる |
胃腸が休まらず、睡眠の質が下がっている可能性 |
これらの症状が続くようであれば、一度飲む量を見直すことが大切です。
-
泣くたびにミルクをあげてしまう(実は眠い・抱っこしてほしいだけ)
-
間隔を空けずに授乳(消化時間が足りず、満腹感が伝わりにくい)
-
ミルクの飲み方にクセがあり、ダラダラ飲みが多い
特に完ミ育児の場合は、泣いた=ミルク欲しいと考えてしまいやすく、知らず知らずのうちに飲ませすぎてしまうこともあります。
-
ミルクの回数や間隔を調整する(1回量を少し減らして回数を見直す)
-
満腹感を意識して、少しずつ飲ませる
-
飲み終わったらすぐに次を足さず、様子を見る
-
「泣き=空腹」ではないときもあることを意識する(眠い・さびしい・おむつなど)
また、どうしても判断に迷う場合は、保健師さんや小児科の先生に相談するのが一番安心です。
飲み過ぎかどうかは、体格や成長具合、消化力なども関係するため、赤ちゃん一人ひとりで“適量”が違うのです。
成長によって変わる飲み方のクセ・量の個人差
赤ちゃんのミルクの飲み方には、大人が想像する以上に個性や変化があります。
生後4ヶ月頃になると、その差がますますはっきりと表れてきて、「うちの子、変なのかな?」「他の子と違う…」と悩むママやパパも増えてくる時期です。
でも、それは心配することではなく、むしろ「成長の証」とも言える変化なのです。ここでは、赤ちゃんの飲み方のクセや個人差について詳しく解説します。
赤ちゃんには、それぞれ自分なりの飲み方があります。たとえば…
-
最初の数分は勢いよく飲み、途中からペースダウンする
-
途中で一度手を離して、また飲み始める
-
片手で哺乳瓶を触ったり、足をバタバタさせながら飲む
-
周囲が気になるとそっちを見て飲むのをやめる(=遊び飲み)
これらの行動は、集中力や感覚の発達が進んできた証拠です。
赤ちゃんの飲み方が変わるのは珍しいことではなく、成長段階に応じて自然に変化していくものです。
新生児の頃は「お腹が空いてなくても出された分を全部飲む」ような傾向が強かった赤ちゃんも、4ヶ月を過ぎる頃になると、満腹感や空腹感を自分で感じて、飲む量を調節できるようになってきます。
これは脳の発達により、「満腹中枢」が働き始めることが関係しています。そのため、これまで180ml飲んでいたのに急に100mlしか飲まない、あるいは逆にたくさん飲みたがる…というような変化が出てくるのです。
ポイント:飲む量の変化は成長と連動していることが多いので、一時的な減少でも神経質になりすぎなくてOKです。
育児書やSNS、周囲のママ友との会話の中で、「うちの子は○○ml飲んでるよ」と聞くと、つい比べてしまいがちですよね。
でも、赤ちゃんのミルク量は本当に人それぞれ。たとえば…
-
体格が大きめな子は自然とたくさん飲む
-
消化力が強い子は短い間隔で少量をこまめに飲む
-
お昼にたくさん飲んで、夜は少なめになる子も
1日の中でもムラがあるのが普通です。
比べるべきは「他の子」ではなく、“昨日の自分の赤ちゃん”です。
昨日よりもご機嫌、体重が少し増えている、よく眠れている。
そんな日々の積み重ねが一番の安心材料になります。
赤ちゃんの飲みムラやクセに合わせて、次のような対応をしておくと気持ちが楽になります。
-
飲んだ量や時間をアプリで記録して「見える化」
-
飲みたがらないときは無理に飲ませず、間隔を空ける
-
日中の授乳リズムをある程度決めておくと生活リズムが整いやすい
-
泣いた=空腹とは限らないと意識する(眠い・不安・退屈など他の理由も)
成長するにつれて、赤ちゃん自身が“自分に合ったペース”を身につけていきます。
それを大人がサポートする感覚で関わると、ミルク時間もぐっと穏やかになりますよ。
ミルク量を記録して悩みを見える化!おすすめの管理方法
「うちの子、ミルク少ないかも…」
「昨日と比べて全然飲まないけど大丈夫かな?」
そんな不安を抱えたとき、ミルク量を“記録”しておくことが、悩みを解決する大きな助けになります。
頭の中だけで管理しようとすると、思い違いや見落としが起こりがち。
特に育児中は睡眠不足や慌ただしさで記憶があいまいになりやすいため、「記録して見える化する」ことはとても有効です。
-
飲んだ量の全体像が見える
「少ない気がする…」と思っていても、1日トータルで見ると案外飲めているということも。
ミルク量を可視化することで、客観的に判断できるようになります。
-
飲みムラや変化の傾向がつかめる
特定の時間帯だけ飲みが悪い、曜日によって量が変わる、などのパターンが見えてくることで、生活リズムの改善にもつながります。
-
病院や保健師に相談するときに役立つ
「だいたい◯mlくらい…」よりも、「この3日間は1日600〜650mlです」と記録がある方が、正確に状況を伝えることができ、医療者側の判断材料にもなります。
アナログ派:母子手帳や育児ノートに手書き
昔ながらのスタイルですが、自分で文字を書くことで記憶に残りやすく、育児の振り返りにも役立ちます。
記録する項目の例:
-
飲んだ時間
-
飲んだ量(ml)
-
機嫌・睡眠の様子
-
うんち・おしっこの有無
📱 デジタル派:スマホアプリで簡単に記録
おすすめアプリ:
|
アプリ名 |
特徴 |
|---|---|
|
ぴよログ |
授乳・ミルク・おむつ・睡眠などをワンタップで記録可能。夫婦共有も◎ |
|
授乳ノート |
授乳・ミルクだけでなく、赤ちゃんの成長記録も可能。グラフ表示で見やすい |
|
育児日記アプリ「ninaru baby」 |
日記感覚で記録でき、過去との比較もできる |
スマホなら外出先でもすぐに記録でき、通知機能で授乳時間を忘れにくくなるのも嬉しいポイントです。
最初は気合いを入れて毎回記録していても、数日で挫折してしまう…ということも少なくありません。
でも、それで大丈夫です。大切なのは**完璧を目指すのではなく、「無理のない範囲で続ける」**こと。
たとえば…
-
朝・昼・夜のうち、どこか1回だけでも記録
-
飲みが悪かった日だけ記録する
-
おしっこの回数とミルク量だけメモする など
記録を習慣化すると、不安が減り、赤ちゃんのことをより深く理解できるようになります。
その積み重ねが、日々の育児の安心感にもつながっていくでしょう。
よくあるQ&A|4ヶ月のミルク育児の疑問を解消!
ここでは、生後4ヶ月の赤ちゃんのミルクに関するよくある疑問や不安に対する答えを、Q&A形式でわかりやすく解説します。
実際に多くのママ・パパが検索している内容をもとに、安心につながるヒントをまとめました。
|
質問 |
回答(要点) |
|---|---|
|
生後4ヶ月の赤ちゃんがミルク100mlしか飲まないけど大丈夫? |
1回量が少なくても、回数が多ければOK。体重増加やおしっこの回数も確認して判断を。 |
|
ミルクの1日トータルが600mlでも足りている? |
混合育児や母乳量によっては十分なことも。赤ちゃんの体調・成長曲線をチェックしよう。 |
|
ミルクを1日1000ml以上飲むけど飲みすぎ? |
吐き戻しや便の様子に問題なければ許容範囲。過飲症候群や胃もたれに注意。 |
|
夜中にミルクをあげなくても大丈夫? |
4ヶ月頃から夜間授乳が減る子も。日中にしっかり飲めていて体重も増えていれば問題なし。 |
|
毎回ミルクを飲み残すのはなぜ? |
満腹中枢が発達してきた証拠。無理に飲ませず、赤ちゃんのペースを大切にして◎ |
「〇〇ml飲んでないと少ない」「1日〇回じゃ足りない」と数値ばかり気にしてしまうと、不安ばかりが募ってしまいます。
でも、赤ちゃんにとっての“ちょうどいい”は一人ひとり違います。
以下のようなポイントを確認しながら、トータルで見て判断するのがベストです。
-
機嫌が良いか
-
体重が増えているか(母子手帳の成長曲線に沿っているか)
-
おしっこの回数(1日6回以上が目安)
-
授乳後に落ち着いているか
ちょっとしたことでも「気になる」「モヤモヤする」と感じたときは、保健センターや小児科、助産師さんに相談してOK!
何気ない質問が、安心に変わる第一歩になることも多いのです。
生後4ヶ月のミルクの量に正解はない。赤ちゃんの様子を見ながら調整を
生後4ヶ月の赤ちゃんのミルクの量について、「これが正解!」という絶対的な基準はありません。
完ミ・混合育児の違いや、赤ちゃんの体格、生活リズム、哺乳のクセなどによって、飲む量にもバラつきがあって当然です。
たとえば、1回に200ml飲む子もいれば、100mlをこまめに飲むスタイルの子もいますし、トータルで600mlしか飲まなくても問題ない子もいます。逆に、1日1000ml以上飲んでも平気な赤ちゃんもいます。
重要なのは、「飲む量」だけにとらわれず、赤ちゃんの全体的な様子を見ながら判断することです。
-
赤ちゃんの機嫌が良いか
-
体重が順調に増えているか(母子手帳の曲線に沿っているか)
-
おしっこの回数が1日6回以上あるか
-
授乳後に落ち着いているか、よく眠れているか
これらがクリアできていれば、多少飲む量にムラがあっても心配しすぎる必要はありません。
もし「やっぱり気になる」「なんとなく不安」というときは、迷わず保健師や小児科に相談を。
プロのアドバイスを受けることで、育児のストレスや不安も軽くなります。
赤ちゃんの数だけミルク育児の正解がある——そう思って、自信を持って向き合っていきましょう。

(画像引用:モグモ公式サイト)
「今日のごはん、どうしよう…」
仕事から帰ってきて、保育園から子どもを迎えて、買い物して、夕飯を作って…毎日そんな繰り返しに疲れていませんか?
そんな忙しいママにおすすめなのが、幼児食宅配サービス mogumo(モグモ)。
1歳半〜6歳の子ども向けに、管理栄養士が考えた無添加・冷凍のおかずをお届けしてくれるんです。
✔ レンジでチンするだけ、調理はほぼゼロ!
✔ 栄養バランスもバッチリで偏食対策にも◎
✔ 忙しい夕食時に“あと1品”としても使える
「子どもがパクパク食べてくれる」だけで、ママの心もぐっと軽くなりますよ。
毎日の食事作りを少しラクにして、子どもと笑顔で過ごす時間を増やしてみませんか?
mogumo公式サイト:初回限定で1食270円の冷凍幼児食モグモをお試しするならこちらをタップ をタップ
をタップ





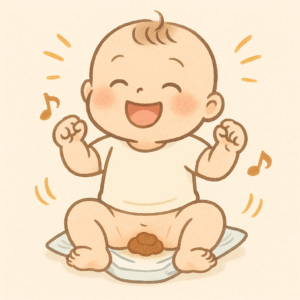



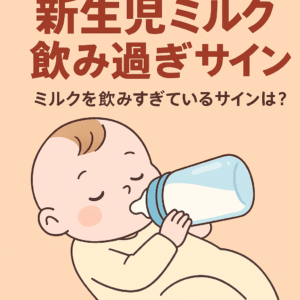
コメント